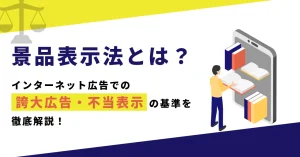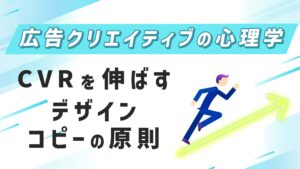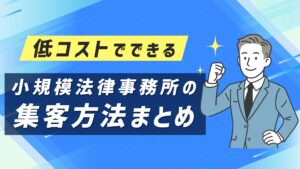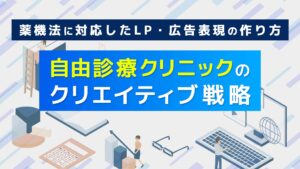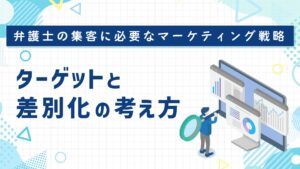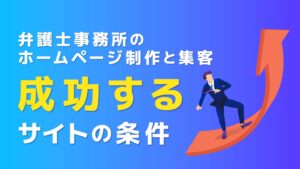近年、インターネット広告やEC市場の急拡大に伴い、消費者と企業との間で生じるトラブルが深刻化しています。
特に、特定商取引法(特商法)違反に関する摘発や行政処分件数は年々増加しており、ネット広告を活用する企業にとって、法令遵守は避けて通れない課題となっています。
特商法違反に該当すると、消費者庁などの行政機関から措置命令を受け、広告の差し止めや業務改善命令が下されることになります。措置命令は企業の社会的信用を大きく損ない、売上の急減や取引先からの信頼失墜、最悪の場合には事業存続にも関わるリスクを抱えることになりかねません。
こうした状況下で、多くの企業担当者が「自社の広告や販売手法は本当に問題ないのか」「知らないうちに法令違反になっていないか」といった不安を抱えています。しかし、特商法違反は故意ではなく、知識不足や軽微なミスから生じるケースも多く、他人事では済まされない問題です。
本記事では、特商法違反による行政指導・措置命令を受けた実際の事例を詳しく紹介するとともに、違反に至った原因や企業が講じた再発防止策についても具体的に解説していきます。
自社のリスク管理体制を見直し、安心してネット広告やECビジネスを推進していくための実践的なヒントを得られる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
特商法(特定商取引法)の概要とネット広告への規制強化の背景
特定商取引法(以下、特商法)は、訪問販売や通信販売など、対面以外で行われる取引において消費者トラブルを防止するために制定された法律です。
正式名称は「特定商取引に関する法律」であり、1976年に施行されて以来、時代の変化に応じてたびたび改正が行われています。
特商法の主な目的は、消費者の利益を保護し、公正な取引環境を整備することにあります。
対象となる取引形態は、訪問販売、通信販売(インターネット通販を含む)、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)など多岐にわたり、事業者に対して厳格な情報開示義務や誇大広告の禁止、適切な契約解除手続きなどが求められています。
特に近年では、インターネット広告を介した通信販売における違反が顕著になっており、スマートフォンの普及とオンラインショッピングの定着により、誰もが簡単に商品・サービスを購入できる一方で、虚偽や誤認を招く広告表現、不適切な契約条件による消費者被害も増加傾向にあります。
なかでも、健康食品、化粧品、情報商材などの無形商材といった分野は、特に違反リスクが高い領域とされ、行政からの監視が強化されています。
たとえば、健康食品では「飲むだけで痩せる」といった効果保証型の表現、化粧品では「シミが完全に消える」といった医薬品的な効能表示、情報商材では「短期間で必ず稼げる」と誤認させる広告などが問題視され、措置命令や業務停止命令に至った事例が数多く報告されています。
規制強化の背景には、消費者被害の未然防止を重視する社会的な流れがあります。政府は消費者基本計画において、違法・不当な取引行為の摘発を積極的に推進しており、特にインターネットを介した取引については、これまで以上に厳しい姿勢で臨んでいます。
今後もネット広告分野における特商法違反に対する監視は一層厳しくなることが予想されます。
企業側は、「知らなかった」では済まされないリスクを十分に認識し、法令遵守体制を強化することが求められています。特商法違反による措置命令を防ぐためには、最新の規制動向を正確に把握し、自社の広告・販売活動に適切に反映させることが不可欠です。
特商法違反の典型的なケースと措置命令の実態
特商法違反による措置命令や行政処分は、近年、特にインターネット通販や広告業界を中心に増加傾向にあります。
この章では、最近の措置命令・行政処分の動向を紹介するとともに、違反の典型パターンと、行政指導・措置命令の違いについて整理して解説します。
違反リスクを正しく理解し、自社のコンプライアンス体制強化に役立てましょう。
近年の措置命令・行政処分の発令状況・統計
特定商取引法に基づく措置命令は、年々増加傾向にあります。
消費者庁の発表する「令和4年度 特定商取引法及び預託法の施行状況」によると、令和4年度(2022年度)には、通信販売業者に対して42件の措置命令が発出されています。
特に目立つのが、インターネット広告を通じた健康食品、化粧品、ダイエット商材、情報商材などに関する違反です。
ネット広告の普及に伴い、消費者が簡単に商品にアクセスできる一方、誇大広告や不適切な取引条件によるトラブルが後を絶たないことが背景にあります。
また、消費者庁は、悪質な違反行為に対しては単なる指導にとどまらず、迅速に措置命令を発出し、再発防止命令を厳格に求める姿勢を強めています。
このため、これまで以上に広告表現や取引条件の適正性が厳しく問われる時代となっています。
措置命令の典型的なパターン
特商法違反で措置命令が発出される典型パターンは、主に以下の3つに分類されます。
- 広告表現の誇張・虚偽表示
- 事実の隠蔽・重要事項の不告知
- キャンセル・返品対応の不備
順に具体例を見ながら確認していきましょう。
広告表現の誇張・虚偽表示
例えば次のような事例です。
- 科学的根拠に基づかない効能・効果の強調
- 医薬品的な効能を謳う化粧品広告(例:「1週間でシミが消える」)
- 収益保証をほのめかす情報商材広告(例:「誰でも必ず月収100万円」)
こうした広告は、「不実告知」として特商法に違反する可能性があります。
(誇大広告等の禁止)
引用:特定商取引に関する法律第(十二条:誇大広告等の禁止)
第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
事実の隠蔽・重要事項の不告知
重要事項を告知しなかったり、事実を隠して販売する例です。
- 商品価格以外に高額な追加費用が発生することを事前に説明しない
- クーリングオフが適用されない条件を明示せず販売する
これらは、「不告知」「重要事項の不告知」として問題となり、消費者にとって不利益です。これも特商法に抵触することになります。
(通信販売についての広告)
引用:特定商取引に関する法律(第十一条:通信販売についての広告)
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
五 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
キャンセル・返品対応の不備
キャンセルや返金・返金を妨害する行為です。
- 「返品可能」と謳っていながら実際には返品を拒否する
- 解約申し込みを著しく困難にする行為(例:解約ページが存在しない、コールセンターが繋がらない)
こうしたケースも特商法違反に該当することがあります。
(不実の告知の禁止)
引用:特定商取引に関する法律(第十三条の二:通信販売についての広告)
第十三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
行政指導と措置命令の違い・意味を整理
特商法違反が疑われた場合、行政機関はまず「行政指導」を行うことがあります。
行政指導とは、事業者に対して改善や是正を勧告・助言するものであり、法的強制力はありません。
しかし、行政指導を無視して違反状態が続く場合、次のステップとして「措置命令」が発出されます。
措置命令は、法的根拠に基づく正式な命令であり、違反行為の中止や再発防止措置の実施、違反内容の公表を義務付けられるものです。命令に違反すると、罰則(刑事罰や過料)が科される可能性もあります。
まとめると、
- 行政指導
-
改善の「要請」。従う義務はないが、無視すれば措置命令リスクが高まる
- 措置命令
-
法的拘束力を持つ「命令」。従わなければ罰則対象となる
ということになります。
企業にとって、行政指導の段階で迅速かつ誠実に対応することが、措置命令という重大リスクを回避する鍵となります。
ネット広告で措置命令を受けた具体的事例を業界別に解説
ネット広告を通じて特商法違反を問われた企業は、実際に数多く存在します。
この章では、
- 健康食品
- 化粧品
- 通販販売
- 情報商材
といった分野ごとに、消費者庁が措置命令等を発出した事例を紹介し、どのような広告表現や販売方法が問題となったのかを具体的に解説します。
特商法違反は業界・商品ジャンルにかかわらず発生しており、特にネット広告における表現の仕方が厳しく問われています。
自社のリスク管理にぜひお役立てください。
【健康食品業界】根拠のない効果効能の訴求による措置命令
株式会社エムアンドエムが販売する「シボヘール」に関して、体脂肪減少効果を科学的根拠なく訴求した表示が問題視され、特定商取引法に基づく措置命令が発出されました。
違反内容は健康効果を謳うにもかかわらず、合理的な根拠資料(エビデンス)がなかったことが違反とされ、特商法違反だけでなく景品表示法違反も絡んだ違反となっており、広告表現の違反事例として良い参考になります。
引用に示すリンクから消費者庁が公表する具体的な措置命令内容をご確認いただけます。
消費者庁は、本日、株式会社エムアンドエムに対し、同社が供給する「ファイラマッスルサプリHMB」と称する食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
引用:消費者庁(株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく措置命令について)
【化粧品業界】医薬品的効能を謳った広告による措置命令
株式会社ゼノアが広告した「薬用クリーム」に関して、医薬品的な効能を謳った表現が問題となり、特商法違反による行政処分を受けました。
化粧品広告では「薬事法・景品表示法」と「特商法」が複合して規制されるケースが多く、特に効果を断言する表現には厳しいチェックが入ります。
【通販業界】返品条件の不備による措置命令
株式会社ビーボが販売する「ベルタ酵素ドリンク」について、返品・解約条件の不備があったとして、特定商取引法に基づく措置命令が発出されました。
消費者庁は、本日、株式会社ビーボに対し、同社が供給する「ベルタ酵素ドリンク」と称する食品及び当該食品を含む「ダイエットパック」と称するセット商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
引用:消費者庁(株式会社ビーボに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について)
このような「定期購入契約における返品・解約条件の不告知」は、最近特に問題視されており、通販業界全体に警鐘が鳴らされています。
【情報商材業界】収益保証表現による措置命令
株式会社WITHが提供していた「無料副業アカデミー」に関して、「誰でも簡単に高収入を得られる」と誤認させる広告表示が問題となり、特定商取引法違反により業務停止命令等が発出されました。
情報商材の広告において、「必ず稼げる」と保証するかのような表現は、特商法・景品表示法双方から規制対象となります。
場合によっては、刑法としての詐欺罪に問われる可能性もあります。
措置命令が企業に与える影響は?
特商法違反による措置命令を受けた企業は、単に広告を修正すれば済むという話ではありません。
措置命令は、企業の信用、経営、そして将来の事業展開に深刻な影響を及ぼします。
この章では、措置命令によって企業がどのようなダメージを受けるのかを具体的に解説します。自社に置き換えて、リスク管理の重要性を改めて認識しましょう。
顧客・消費者からの信頼低下
措置命令が発出されると、企業名と違反内容が消費者庁の公式サイト上に公表されます(※特定商取引法第14条に基づく公表義務)。
(指示等)
引用:特定商取引に関する法律(第14条:指示等)
第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
四 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
公表により、企業名がインターネット検索結果に残り続け、消費者や取引先からの信頼が大きく損なわれることになります
一度傷ついたブランドイメージを回復するには、多大な時間とコストが必要です。
特にBtoC(一般消費者向け)ビジネスでは、評判の悪化がそのまま売上減少に直結するリスクが高まります。
売上や業績への直接的なダメージ
措置命令を受けると、違反広告の停止や販売自粛を余儀なくされるため、短期的な売上が急減するケースが少なくありません。
さらに、既存顧客が解約や返品を希望する動きが加速し、返金対応によるコスト負担も重くのしかかります。
特に、定期購入ビジネスやいわゆるDtoC通販のように「リピート収益」を柱とする業態では、契約者の大量離脱が経営危機に直結することもあります。
実際に、措置命令を受けた一部の企業では、違反発覚後数か月以内に売上が30〜50%以上減少し、事業縮小や撤退を余儀なくされた例も報告されています。
競合他社との市場競争力の低下
消費者から見れば、同じような商品やサービスが存在する中で、「違反歴がある企業」よりも「クリーンな企業」を選ぶのは当然の流れです。
措置命令によって信用を落とした企業は、市場での競争力を大きく失い、競合他社にシェアを奪われるリスクが高まります。
また、取引先(代理店・卸売業者など)や金融機関からの信用も低下し、販売チャネルの縮小や資金調達の難航といった二次的なダメージにもつながる可能性があります。
刑事罰や行政処分の追加リスクも
特商法において措置命令に従わない場合や、悪質な違反が認定された場合、さらに重い処分(業務停止命令や刑事罰)が科されることもあります。
たとえば、特商法第58条によれば、措置命令に違反した場合には「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性が明記されています。
企業だけでなく、担当役員個人にも責任が及ぶリスクがあるため、法令遵守の意識を全社的に徹底する必要があります。
特商法違反が起こる根本原因と企業側が見落としやすいポイント
特商法違反は、悪意を持った事業者だけが起こすものではありません。
実際には、善意の事業者であっても、体制の不備や認識不足によって違反に至ってしまうケースが数多くあります。
この章では、特商法違反が起こる根本的な原因と、企業が見落としやすいポイントを整理し、事前に対策を講じるためのヒントをお伝えします。
短期的な売上目標の重視による無理な広告表現
多くの企業で共通するのは、短期的な売上目標やノルマを達成するために、広告表現が徐々にエスカレートしていくことです。
「競合よりも目立たせたい」「購入を後押ししたい」という意識から、つい事実を誇張したり、科学的根拠が不十分な効能を謳ってしまうことがあります。
特にネット広告は、クリック率やコンバージョン率を数値で測定できるため、効果を追求するあまり、法令遵守よりもマーケティング優先になってしまう危険性が高い分野です。
広告主として、ルールを定めていても成果報酬型の広告の運用者(アフィリエイター)や広告代理店などがルールから逸脱してしまう可能性もあります。
特商法の条文理解・運用知識の不足
特定商取引法は条文が比較的シンプルですが、具体的な運用においては細かな規制や解釈が存在します。
例えば、
- 返品条件を「一応記載しているが目立たない場所にしか表示していない」
- 解約方法を「電話のみ」としているが、実際には電話が繋がりにくい
など、表面的には問題なさそうでも、実務上は違反と認定されるケースが少なくありません。
つまり、「一応書いてある」では不十分で、消費者がきちんと理解できる形で提示する必要があるのです。
広告審査体制・社内チェック体制の脆弱さ
特商法違反が発生する大きな要因のひとつが、広告審査体制の不備です。
- 広告クリエイティブ制作を外部委託しているが、納品物のリーガルチェックを行っていない
- 広告代理店に丸投げしており、自社内でのチェックフローが存在しない
- 形だけのチェックリスト運用にとどまり、実態のない形骸化した審査体制になっている
このような状態では、いくら「違反は絶対にしない」と意識していても、チェック漏れが生じ、知らず知らずのうちに特商法違反リスクを高めてしまいます。
関係者のコンプライアンス意識の希薄さ
違反リスクは、経営層、マーケティング担当者、営業担当者、カスタマーサポート担当者など、組織全体にわたる問題です。
「売上第一」の空気が組織に蔓延していると、誰も広告表現や販売方法のリスクに対して声を上げなくなり、小さな違反がエスカレートする原因になります。
特商法遵守のためには、経営層から現場担当者まで、一貫したコンプライアンス意識の浸透が不可欠です。
特商法違反を防ぐための具体的な対策と再発防止策
特商法違反は一度起こしてしまうと、企業に甚大なダメージをもたらします。
しかし、日頃から適切な対策を講じることで、違反リスクを大幅に低減することが可能です。
この章では、特商法違反を未然に防ぎ、万が一違反が発生しても再発を防ぐための具体的な施策を紹介します。
ネット広告・販売ページの適正化とリーガルチェック体制の構築
まず最優先で取り組むべきは、広告クリエイティブや販売ページの表現適正化です。
- 科学的根拠がない効能効果の記載を禁止
- 医薬品的な効能表現(例:「病気が治る」「即効で効く」)の禁止
- 契約条件(返品・解約条件、費用負担)を目立つ形で明示
- 特典や割引に関する条件も正確に表示する
これらを実現するためには、制作段階で法務部門・コンプライアンス担当者が広告内容を事前審査する体制を必ず整えるべきです。
また、外部制作会社や広告代理店に依頼する場合でも、「特商法遵守基準」を共有し、納品時に遵守確認を求めることが重要です。
この「特商法遵守基準」は、広告業界では「広告レギュレーション」と呼ばれ、NGとする表現や出稿可能な広告媒体など広告に関するルールが記載されています。
単に「レギュレーション」と呼ばれることもあり、代理店やアフィリエイターにレギュレーションを渡すことで、広告主・広告運用者・広告代理店にとって不要なトラブルが回避できるため、非常に重要ななくてはならない資料となります。
社内教育とコンプライアンス研修の定期実施
特商法違反は、担当者個人の知識不足から発生するケースも多いため、社内教育の強化が不可欠です。
具体的には、
- 特商法の基本ルールをまとめた「社内ガイドライン」の策定・配布
- 新入社員向け研修+年1回以上の既存社員向け更新研修
- 特定の広告表現に関するケーススタディ形式の研修
といった取り組みを行うことで、全社的なコンプライアンス意識を醸成できます。
特に「どのような広告表現が違反リスクを高めるのか」という具体例ベースで教育することが効果的です。
定期的な広告モニタリング・内部監査体制の整備
一度広告を審査して終わりではなく、運用開始後も定期的にモニタリングを実施することが必要です。
例えば、
- ランディングページ、広告バナー、SNS広告などを月に一度チェック
- 表現の変化や新たな販売方法(キャンペーンなど)にもレギュレーションなどを定めて運用を簡素化
- 違反の兆候が見られた場合は、すみやかに改善・修正を指示
定期的に、実際に運用されている広告・販売オペレーションに問題がないかを確認しましょう。
まとめ
特定商取引法違反は、企業にとって重大なリスクであり、たとえ軽微な違反であっても、措置命令や行政処分により、ブランドイメージや経営基盤に大きなダメージを与えかねません。
全体を通じて紹介してきた違反事例や原因分析、そして防止策から、特商法違反を避けるために押さえておくべき重要なポイントを改めて整理しておきます。
- 広告表現の適正化を最優先に取り組む
-
科学的根拠のない効果訴求、過度な収益保証、医薬品的な効能表示などは、すぐに違反リスクに直結します。
広告制作段階から法務部門や専門家によるリーガルチェックを徹底し、表現の適正化を最優先で図るべきです。
- 販売条件(返品・解約条件など)の明確な開示
-
契約前に、返品・キャンセル条件、追加費用の有無などを明確かつわかりやすく表示することは、特商法上の義務です。
「書いてあるから問題ない」ではなく、消費者が正しく理解できる形で提示することが重要です。
- 広告・販売活動全体を継続的にモニタリング
-
一度作った広告や販売サイトでも、時間の経過とともに法令基準や消費者意識は変わります。
定期的な広告内容の点検、内部監査体制の整備を怠らないことが、違反を未然に防ぐためのカギとなります。
- 社内全体へのコンプライアンス教育の徹底
-
広告・営業・カスタマーサポートなど、消費者対応に関わるすべての部署で、特商法に関する基礎知識と遵守意識を共有することが不可欠です。
トップダウンだけでなく、現場レベルで自発的にリスクに気づき是正できる文化づくりが求められます。
- 法改正や行政動向を常にキャッチアップ
-
特商法をはじめとする関連法規は、消費者被害の実態に応じて適宜改正されています。
最新情報をキャッチアップし、変化に迅速に対応できる柔軟な運用体制を整えておくことが、長期的なリスク回避につながります。
特商法違反は、対策を怠れば誰にでも起こりうるリスクですが、適切な知識と体制があれば確実に防ぐことができます。
この記事が、読者のみなさまが特商法違反リスクを正しく理解し、安心してビジネスを推進していくための一助となれば幸いです。