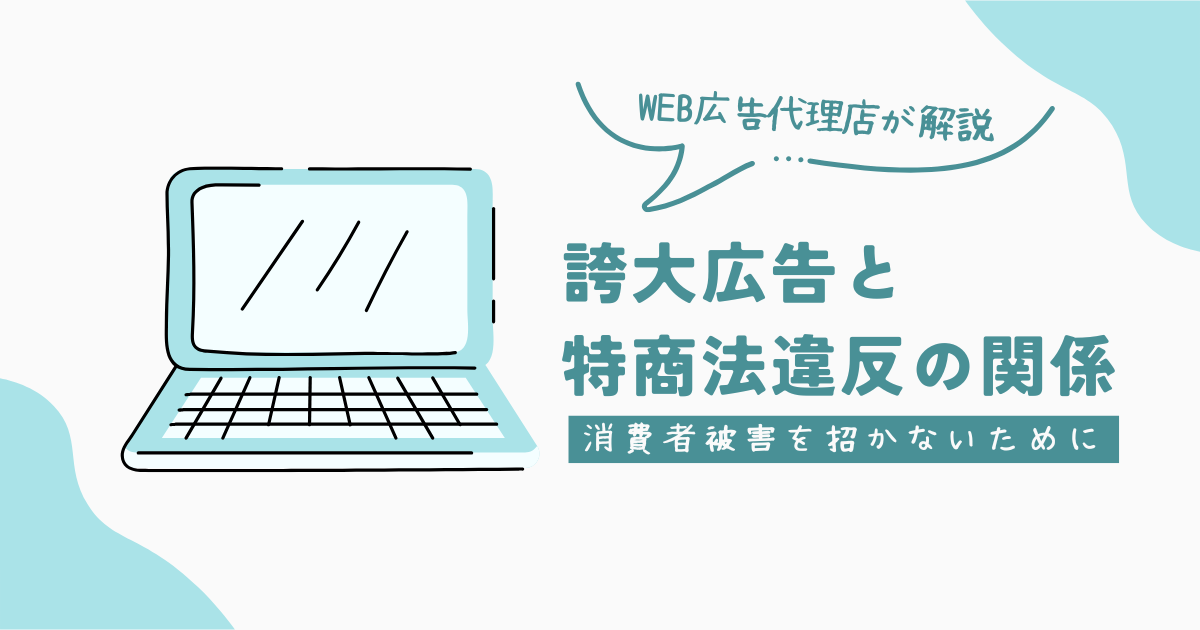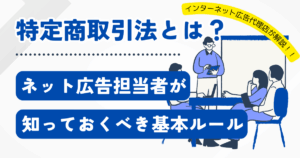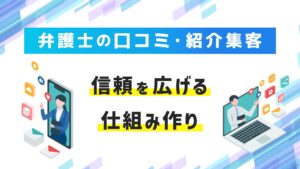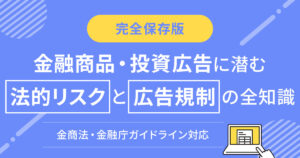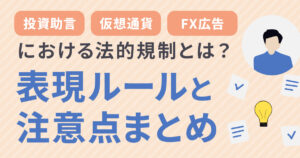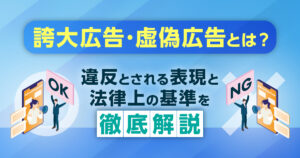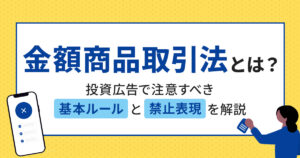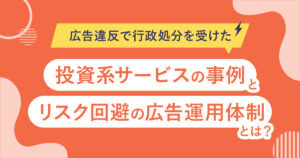「この表現は誇大広告に当たらないだろうか?」
「うちの広告、特商法違反してないかな…?」
ネット広告担当者として、このような不安や疑問を抱えたことはありませんか。
消費者の関心を引きたい一心で魅力的な表現を使いたくなる気持ちは理解できますが、その一歩間違えば法令違反となり、業務停止命令などの行政処分や多額の課徴金、さらには企業の信頼喪失という大きなリスクにつながります。
近年も消費者庁による誇大広告の監視により、健康食品や化粧品、情報商材などの分野で多くの行政処分事例が報告されています。
そして、これらの多くは「知らなかった」「意図していなかった」という事業者側の認識不足から生じているのです。
本記事では、誇大広告の定義から特定商取引法における規制、具体的な違反事例とその対策まで、ネット広告担当者が知っておくべき知識を体系的に解説します。
効果効能の過大表現、価格や割引率の虚偽表示、限定表現の偽装など、よくある違反パターンとその回避方法も具体的にご紹介。さらに、万が一違反してしまった場合の適切な対応方法についても解説していきます。
誇大広告とは
誇大広告とは、商品やサービスの効果・性能を実際以上に強調したり、虚偽の情報を含む広告表現のことを指します。
さらに誇大広告の法律や種類を解説していきます。
誇大広告の本質的問題
誇大広告が問題視される最大の理由は、消費者の適切な意思決定を妨げることにあります。消費者は広告情報をもとに購入を判断するため、誤った情報や過大な表現は、消費者に不適切な選択をさせる可能性があるのです。
景品表示法等、広告に関する法律や各ガイドラインでは、実際の商品・サービスの性能や取引条件とは異なる広告や表示を行い、消費者に誤解を与え、不利益をもたらし、自社の売上・利益を増大することを禁じています。
誇大広告を規制する法律
誇大広告は主に以下の法律によって規制されています。
- 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
-
商品・サービスの表示に関する最も基本的な法律で、優良誤認表示や有利誤認表示などを禁止しています。
- 特定商取引法
-
次に、社会的影響として、企業イメージの著しい悪化が避けられません。特にSNSの発達した現代では、ステマの発覚は瞬く間に拡散され、消費者からの信頼を大きく損なうことになります。また、メディアによる批判的な報道も相次ぎ、企業の評判は長期にわたって傷つくことになるでしょう。
- 薬機法(医薬品医療機器等法)
-
医薬品・医療機器・健康食品などの広告に関する規制を行っています。
- 健康増進法
-
健康食品等の広告について、効果・効能の表示を規制しています。
誇大広告の種類
誇大広告は大きく分けて以下の種類があります。
- 優良誤認表示
-
商品・サービスの品質や効果が実際よりも優れていると消費者に誤認させる表示を指します。例えば、「100%痩せる」「確実に効果がある」などの表現が該当します。
- 有利誤認表示
-
価格や取引条件が実際よりも有利であると消費者に誤認させる表示を指します。例えば、実際には値引きしていないのに「特別価格」と表示するケースなどが該当します。
- その他の不当表示
-
「おとり広告」のように準備がないなど取引に応じることができない商品やサービスについての表示も不当表示に該当します。
近年、インターネット広告の急増に伴い、誇大広告の問題も複雑化しています。誇大広告を掲載している事業者の数は増加傾向にあり、特にインターネット広告・SNS広告についての通報が大きな割合を占めています。
広告担当者は、短期的な売上向上のためではなく、消費者との長期的な信頼関係構築の視点から広告表現を検討する必要があります。適切な広告は、企業のブランド価値を高め、持続可能なビジネス成長につながるものなのです。
特定商取引法(特商法)における誇大広告
特定商取引法(特商法)は、消費者トラブルが発生しやすい取引形態を対象に、消費者保護を目的として規制を設けている法律です。誇大広告規制はその中でも重要な柱の一つとなっています。
ネット広告担当者が知っておくべき、特商法における誇大広告の定義、規制範囲、罰則などについて解説します。
特商法における「広告」の定義
特商法では、特に通信販売における広告を重要な規制対象としています。「販売業者等がその広告に基づき通信手段により契約の申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により契約の申込みをすることができるもの」が「広告」に該当します。
Webサイト上のどのような表示が「広告」に該当するかという点では、商品紹介ページやランディングページなど、消費者が表示を見て購入の申込みをできるものは広告となります。
特商法で規制される誇大広告の範囲
特商法では、主に通信販売における誇大広告について、以下の規制があります。
- 禁止される表示内容
-
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
具体的には、商品・サービスの内容や取引条件について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
- 表示義務との関係
-
価格や取引条件が実際よりも有利であると消費者に誤認させる表示を指します。例えば、実際には値引きしていないのに「特別価格」と表示するケースなどが該当します。
特に、2022年6月の改正特商法では、最終確認画面の表示義務を新たに規定するなど、規制が強化されている点にも注意が必要です。
改正特定商取引法により、事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となります。
引用:消費者庁
違反した場合の罰則
特商法の誇大広告規制に違反した場合、以下のような行政処分や罰則を受ける可能性があります。
- 業務改善指示
-
軽微な違反や初回のケースでは、まず必要な改善措置を指示されます。行政指導ですが公表されるため、企業イメージに悪影響を及ぼす可能性が高いです。
- 業務停止命令
-
指示に従わない場合や悪質なケースでは、一定期間の業務停止が命じられます。最近では「ナンバーワン表示」「虚偽の解除条件」「実在しない価格」などの誇大広告で処分を受けた事例があるため、特に注意しましょう。
- 業務禁止命令
-
悪質な場合には、個人に対する業務禁止命令も出されることがあります。
特商法における誇大広告規制は、消費者保護の観点から年々強化される傾向にあり、ネット広告担当者は自社の広告表現が法令に違反していないか、定期的に確認する必要があります。
景品表示法における誇大広告
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者に対する適正な商品・サービス選択を確保するために、不当な表示や過大な景品類の提供を禁止する法律です。
特商法が特定の取引形態を規制するのに対し、景品表示法はあらゆる商品・サービスの表示に適用される点が特徴となっています。
景品表示法における「不当表示」の定義
景品表示法では、誇大広告に相当するものを「不当表示」として規制しています。不当表示は主に以下の種類があります。
- 優良誤認表示
-
商品・サービスの品質、規格、性能などについて、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示を指します。
- 有利誤認表示
-
価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示を指します。
「通常価格10,000円のところ、今だけ3,000円」といった表現で、実際には通常価格が虚偽である場合などが含まれ、二重価格表示で比較対象となる価格が実在しない場合も違反となることがあります。
- 不実証広告規制
-
商品・サービスの効果や性能の表示について、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた事業者が、期間内に提出できない場合は不当表示とみなされる規制です。「科学的に効果が証明された」などと表現する場合には、客観的・科学的な裏付けが必要となります。
景品表示法における「表示」の範囲
景品表示法における「表示」は非常に広範囲にわたります。具体的には次のようなものが含まれます。
- Webサイト、ランディングページ
- SNS広告、リスティング広告
- メールマガジン、メールマーケティング
- 商品パッケージ、説明書
- チラシ、カタログ、ポスター
ネット広告担当者は特に、バナー広告やアフィリエイト広告、インフルエンサーマーケティングも規制対象となることを理解しておく必要があります。第三者を介した広告でも、広告主が表示内容に関与していれば責任を問われる可能性があるのです。
景品表示法違反の罰則
景品表示法に違反した場合、消費者庁から以下のような処分を受ける可能性があります。
- 措置命令
-
不当表示を行った事業者に対して、その表示の差止め、再発防止策の実施、一般消費者への周知徹底などが命じられます。インターネット広告では、違反した広告の削除だけでなく、訂正広告の掲載が求められることもあるため、企業イメージへの影響は大きいといえるでしょう。
- 課徴金制度
-
2016年に導入された課徴金制度では、優良誤認表示や有利誤認表示を行った事業者に対して、対象商品・サービスの売上高の3%に相当する課徴金が課せられます。年間売上高が5,000万円を超える場合、経済的なダメージは相当なものとなるでしょう。
- 自主申告による減免制度
-
課徴金対象行為を自主的に申告し、再発防止策を講じた場合には、課徴金額が減額または免除される制度も設けられています。コンプライアンス体制の整備と共に、問題が発覚した場合の早期対応も重要な視点となります。
特商法との違いと併用される法的規制
景品表示法と特商法は、広告表示規制において補完関係にあります。特商法が特定の取引形態(通信販売など)に限定して適用されるのに対し、景品表示法はあらゆる商品・サービスの表示に適用される点が異なります。
ECサイトやネット広告を運用する担当者は、両法律の規制内容を理解し、より厳しい基準に合わせた広告運用が求められます。さらに、薬機法(医薬品医療機器等法)や健康増進法など、商品カテゴリによって適用される業法にも注意が必要です。
特商法違反につながる誇大広告の具体例
インターネット広告において、意図せず特商法違反となってしまうケースは少なくありません。特に通信販売における広告表現では、消費者の購買意欲を高めようとするあまり、法的に問題のある表現を使用してしまうことがあります。
ここでは、実際に処分や指導の対象となった具体例を踏まえながら、特商法違反となりやすい誇大広告の具体例を解説します。
効果効能の過大表現
商品やサービスの効果・効能を過度に強調する表現は、特商法違反の中でも最も多い事例の一つです。科学的根拠のない効果を断定的に表現することは、消費者を誤認させる行為となります。
- 健康食品・サプリメントにおける違反例
-
健康食品やサプリメントの広告では、以下のような表現が特商法違反となります。
- 「飲むだけで○kg痩せる」「2週間で確実に体重が減少」など、痩身効果を断定的に表現
- 「高血圧が改善する」「花粉症が治る」など、医薬品的な効能を標榜する表現
- 「臨床試験で実証済み」という表現を使用しながら、実際には小規模な自社調査しか行っていない場合
特に「医学的に証明された」「〇〇医学博士が推奨」などの権威性を強調する表現と組み合わせることで、消費者の誤認を招きやすくなります。客観的な科学的根拠がない場合は、そうした表現を避けるべきでしょう。
- 課徴金制度
-
化粧品の広告においても、薬機法と特商法の両方に抵触する表現に注意が必要です。
- 「シミ・シワが消える」「たるみを解消する」など、医薬品的効能効果を標榜する表現
- 「使用後24時間以内に効果を実感」など、即効性を過度に強調する表現
- 「エイジングケアの決定版」「業界最高レベルの美白効果」など、客観的な比較根拠のない最上級表現
化粧品広告では「〜のような感じがする」「〜が期待できる」といった体感的・期待値を表す表現を用いることが一般的ですが、断定的な表現は避けることが重要です。
- 化粧品における違反例
-
化粧品の広告においても、薬機法と特商法の両方に抵触する表現に注意が必要です。
- 「シミ・シワが消える」「たるみを解消する」など、医薬品的効能効果を標榜する表現
- 「使用後24時間以内に効果を実感」など、即効性を過度に強調する表現
- 「エイジングケアの決定版」「業界最高レベルの美白効果」など、客観的な比較根拠のない最上級表現
化粧品広告では「〜のような感じがする」「〜が期待できる」といった体感的・期待値を表す表現を用いることが一般的ですが、断定的な表現は避けることが重要です。
価格や割引率の虚偽表示
価格や割引に関する虚偽表示も、特商法違反として摘発事例が多く見られます。消費者庁による監視が厳しい分野でもあります。
- 二重価格表示に関する違反例
-
二重価格表示とは、「通常価格」と「セール価格」を併記する表示方法です。以下のような表示が問題となります。
- 「通常価格10,000円→特別価格3,980円」と表示しながら、実際には10,000円で販売した実績がない
- 「メーカー希望小売価格の50%OFF」と表示しながら、実際にはメーカー希望小売価格が設定されていない
- 「期間限定特価」としながら、実質的に恒常的な価格である場合
適正な二重価格表示には、比較対象となる価格について、相応の期間・数量を通常価格で販売した実績が必要です。架空の高額価格を設定して割引率を大きく見せる手法は、明確な特商法違反となります。
- 送料無料表示に関する違反例
-
送料や手数料に関する表示も、消費者の誤認を招きやすい部分です。
- 「送料無料」と大きく表示しながら、実際には北海道・沖縄・離島は別途送料が必要な場合に、その旨の表示が小さい
- 「今だけ0円」と表示しながら、実際には定期購入が条件となっている
- 「実質無料」と表示しながら、別途手数料やシステム利用料が発生する
「無料」「0円」などの表現は消費者の注目を集めますが、条件がある場合は、同等の視認性をもって表示することが重要です。
こうした「焦らせ広告」は、消費者の冷静な判断を妨げる要因となるため、特商法では厳しく規制されています。
ネット広告担当者は、購買心理を刺激する表現と法令遵守のバランスを取ることを常に意識しましょう。広告効果を高めるための表現であっても、事実に基づかない内容は消費者の信頼を損なうだけでなく、法的リスクも発生します。
特商法を遵守した正しい広告表現方法
効果的な広告を展開しながらも法令を遵守するというバランスは、ネット広告担当者にとって重要な課題です。
特商法違反を避けながら、商品やサービスの魅力を伝える広告表現の方法について解説します。コンプライアンスと広告効果の両立が、持続可能なマーケティング活動の基盤となるでしょう。
誇大広告を防ぐ広告表現のチェックポイント
広告制作や承認の過程で以下のポイントをチェックすることで、誇大広告のリスクを大幅に軽減できます。
実務担当者が日常的に活用できるチェックリストとして参考にしてください。
- 表現の根拠確認
-
効果・効能に関する表現には、客観的な根拠が必要です。
以下のポイントを確認しましょう。
- 「最高」「最大」「最速」などの最上級表現には、比較対象と比較方法を明確にできるか
- 効果・効能に関する数値(「〇%向上」など)は、適切な試験結果に基づいているか
科学的な根拠が曖昧な場合は、「〜と思われます」「〜が期待できます」など、断定的でない表現を用いることが重要です。また、データの出典を明記することで、表現の信頼性を高めることができます。
- 条件表示の明確化
-
販売条件や制限事項は、消費者が容易に認識できる方法で表示する必要があります。
- 「送料無料」の条件(一定金額以上の購入など)は、同じ視認性で併記されているか
- 「期間限定」「数量限定」の具体的な期間や数量が明示されているか
- 特典や割引の適用条件が明確に表示されているか
- 注釈や但し書きが極端に小さな文字やクリックしないと表示されない場所にないか
消費者が見落とす可能性のある重要事項は、本文と同等の視認性を確保することがポイントです。特に、スマートフォンでの閲覧を考慮した表示設計が必要となります。
- 価格表示の適正化
-
価格に関する表示は、消費者の購買判断に直接影響する重要要素です。
- 二重価格表示をする場合、比較対象となる価格の根拠(販売実績など)があるか
- 割引率や値引き額の計算が正確か
- 総額表示(税込価格)が適切に行われているか
「実質無料」「〇円相当プレゼント」などの表現を使う場合も、その計算根拠を明確にしておくことが求められます。
- メディア特性に応じたチェック
-
広告メディアごとの特性に合わせた確認も重要です。
- リスティング広告:限られた文字数でも必要な表示事項が盛り込まれているか
- SNS広告:広告である旨(PR・広告表示)が明示されているか
- インフルエンサー広告:協賛や提供に関する情報が適切に開示されているか
- LP(ランディングページ):詳細情報へのアクセスが容易か
特に画像や動画主体の広告では、視覚に訴える演出と法的要件のバランスに留意する必要があります。
- 競合他社への言及
-
競合他社や他社製品に言及する場合は、特に慎重な表現が求められます。
- 「他社製品より優れている」などの表現には客観的な根拠があるか
- 比較広告の場合、比較方法と条件が公平で適切か
- 他社を誹謗中傷する表現になっていないか
競合との比較は、消費者に有益な情報提供となる場合もありますが、公正かつ客観的な根拠に基づいた表現が不可欠です。
社内でのコンプライアンス体制構築の方法
広告表現の適法性を担保するためには、個人の知識だけでなく、組織的なコンプライアンス体制の構築が重要です。
以下にて実践的な方法を紹介します。
- 広告審査体制の確立
-
社内で広告表現をチェックする仕組みを整備します。
- 法務部門や外部専門家を含めた広告審査委員会の設置
- 広告出稿前の承認フローの明確化(制作担当→部門責任者→法務確認など)
特に組織が大きい場合は、部門間の連携が円滑に進むよう、審査スケジュールの余裕を持った設定が必要です。また、外部委託している場合も、最終的な法的責任は広告主にあることを認識しておきましょう。
- チェックリストとガイドラインの整備
-
実務者が日常的に活用できるツールを整備します。
- 業界特性を踏まえた社内広告表現ガイドラインの作成
- NG表現・NG事例集の定期的な更新
- 広告チェックシートの標準化(前述のチェックポイントを含む)
特に表現のグレーゾーンについては、社内で判断基準を統一しておくことで、担当者によるバラつきを防ぐことができます。
ガイドラインは消費者庁や業界団体の最新情報を反映して定期的に更新することが望ましいでしょう。
- 定期的な研修・情報共有
-
広告担当者のスキル向上と知識のアップデートを図ります。
- 法改正や処分事例に関する情報の定期的な共有会
- 部署横断的な事例検討会(自社・他社の広告表現の検証)
特に事例を用いた情報共有は、抽象的な法律知識を具体的な広告表現に落とし込む上で効果的です。
- モニタリングと是正体制
-
公開後の広告についても継続的に監視する体制を整えます。
- 定期的な自社広告の表現点検(四半期に1回程度)
- 消費者からのクレーム・問い合わせ情報の集約と分析
- 問題発見時の迅速な是正プロセスの確立(責任者への報告フロー、差替え手順など)
問題が発生した場合の対応フローを事前に定めておくことで、パニックを避け、適切な対応が可能となります。また、他社の処分事例から学び、自社の広告に反映させる視点も重要です。
組織的なコンプライアンス体制の構築は、短期的にはコスト増となることもありますが、誇大広告による消費者被害や社会的信用の失墜といったリスクを考えれば、必要な投資といえるでしょう。
広告効果の追求と法令遵守の両立が、持続可能なマーケティング活動の基盤となります。
誇大広告がもたらす被害とリスク
誇大広告は、単なる法令違反という問題にとどまらず、消費者と企業の双方に様々な実害をもたらします。
誇大表現による一時的な売上増加の裏には、長期的な信頼失墜という大きな代償が潜んでいます。ここでは、誇大広告がもたらす具体的な被害とリスクについて解説します。
消費者側の被害
経済的な被害では、消費者は過大表現された商品に適正価格以上のお金を支払ったり、偽りの「限定」「特別価格」に惑わされて比較検討せずに購入したりします。「初回無料」で契約後、解約困難な定期購入に縛られるケースも増加中です。
国民生活センターの報告によれば、2022年度の通信販売での定期購入に関する相談件数は約9.8万件に上っています。
健康面では、医薬品的効能をうたった健康食品を信じて適切な治療を受けず症状が悪化するケースがあります。心理面でも、過大な効果を期待させる広告によって、効果が出ないときの失望感や自己肯定感の低下を招くことになるのです。
社会的には、誇大広告の横行によって広告全般への不信感が高まり、適切な広告まで疑われる風潮が生まれています。
日本インタラクティブ広告協会の調査では、インターネット広告の信頼度は22.3%と低く、情報提供の場としての広告機能が低下しています。
全国の消費生活センター等に寄せられた通信販売での「定期購入」に関する相談件数は、2021
引用:国民生活センター
年度が約5万 9,000 件、2022 年度が約9万 8,000 件と増加しています
企業側のリスク
法的な制裁では、特商法・景品表示法違反による行政処分、課徴金納付命令、刑事罰、損害賠償請求など、多岐にわたるリスクがあります。
景品表示法では不当表示を行った事業者に対して、対象商品・サービスの売上高の3%に相当する課徴金が課されることがあります。
社会的信用の喪失も深刻です。違反事業者としての公表はブランドイメージを低下させ、SNSでの批判拡散や否定的報道による顧客離れ、取引先からの信頼喪失につながります。行政処分後も「あの会社は処分を受けた」というイメージが長く残ってしまいます。
対応コストも無視できません。問題広告の差し替え・回収、クレーム対応、再発防止のための体制整備など、多大なリソースが必要となります。
長期的なビジネス面では、一度信頼を失った顧客の離反、リピート率低下、否定的口コミの拡散による新規顧客獲得困難といった悪循環が起きます。短期的な売上増よりも、顧客生涯価値(LTV)の毀損という大きな代償を払うことになるでしょう。
誇大広告がもたらすこれらの被害とリスクを考えれば、適正な広告表現を心がけることが、消費者と企業の双方にとって利益となります。コンプライアンスを重視した広告運用こそが、持続可能なビジネスの基盤を強化するものです。
違反してしまった場合の対応方法
特商法や景品表示法における誇大広告の規制に違反してしまった場合、その後の対応によって被害の拡大防止や行政処分の軽減につながる可能性があります。
違反が発覚した際の適切な対応方法について解説します。
違反の発覚と初動対応
誇大広告の違反が発覚したら、まず問題広告を即時停止します。消費者からのクレーム、業界団体からの指摘、行政機関からの調査が主な発覚経路です。
社内調査チームを編成し、広告内容、作成過程、エビデンス資料の有無を調査して事実関係を把握しましょう。
消費者への対応
透明性をもって問題の内容と対応方針を開示します。被害状況に応じた返金や交換などの補償措置も検討しましょう。
専用相談窓口を設置し、消費者からの問い合わせに丁寧に対応する体制を整えることが重要です。
行政機関への対応
消費者庁や都道府県からの報告徴収や立入検査には誠実に協力します。景品表示法の課徴金制度には自主申告による減免制度があるため、早期の自主申告も検討しましょう。
具体的な再発防止策を策定し、行政機関に提示することも効果的です。
再発防止策の実施
広告審査プロセスを見直し、多段階チェック体制や法務部門の関与を強化します。広告担当者やその関連部署に定期的な法令研修を実施し、コンプライアンス意識を高めましょう。
信頼回復への取り組み
問題内容と対応策について誠実に謝罪し、対応の進捗状況を定期的に公開します。
適正な広告表現による誠実なマーケティング活動を継続し、一時的な売上よりも長期的な信頼関係構築を優先する姿勢を示すことが、信頼回復への道となります。
誇大広告の違反対応は、単に行政処分を軽減するだけでなく、企業の危機管理能力と誠実さを示す機会でもあります。適切な対応と再発防止の取り組みによって、失った信頼を回復し、より強固なコンプライアンス体制を構築することが可能となるでしょう。
まとめ
本記事では、誇大広告と特商法違反の関係性、そしてそれらを回避するための対策方法について詳しく解説しました。改めて重要なポイントを整理します。
- 法的リスクを正しく理解すること
- 適切な広告表現のガイドラインを作成し、遵守すること
- 透明性のある広告運用を心がけること
- 広告主としての責任を認識し、適切な管理体制を構築すること
- 違反事例から学び、自社の広告運用を継続的に改善すること
これらの点に注意を払いながら広告運用を行うことで、消費者からの信頼を獲得し、持続可能なマーケティング戦略を実現することができます。
法令に準拠した広告運用は、短期的には手間がかかるように感じるかもしれません。しかし、長期的に見れば、消費者からの信頼獲得、ブランド価値の向上、そして安定した事業成長につながる重要な投資となります。
今後のネット広告運用に、この記事で学んだ内容をぜひ活用してください。適正な広告表現が、消費者と企業の双方にとって健全なデジタルマーケティング環境を構築する基盤となります。