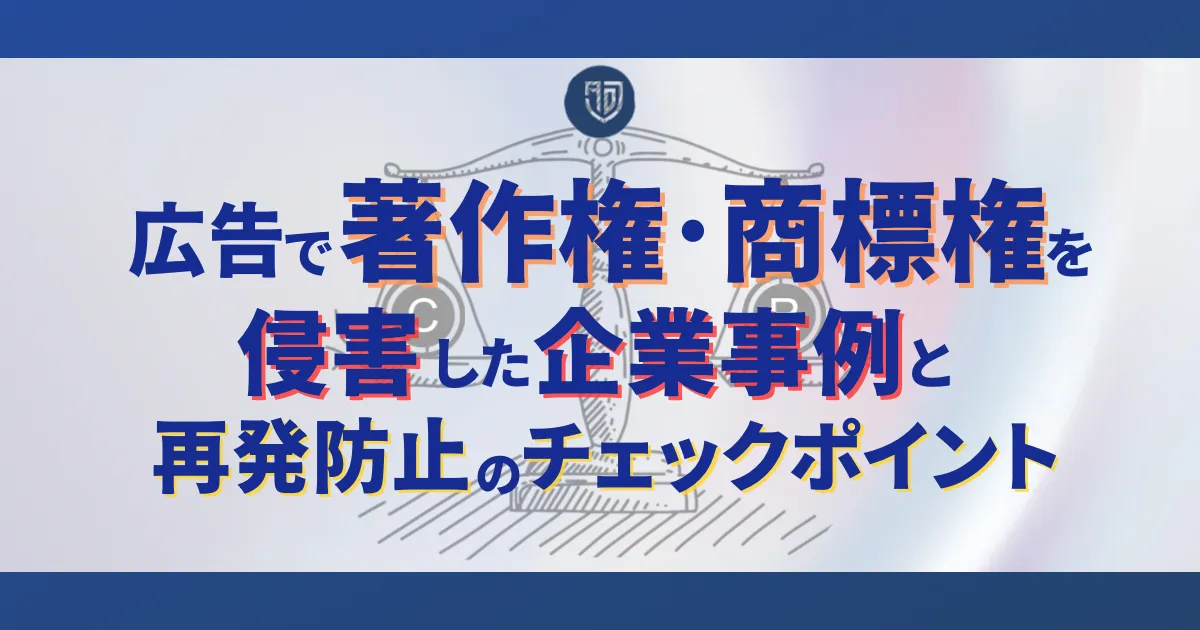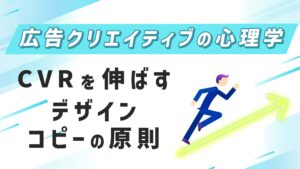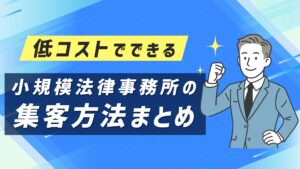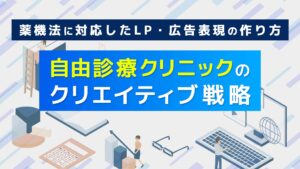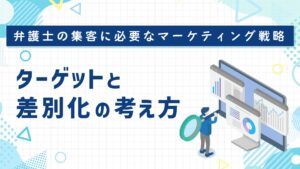- 似たデザインやフリー素材を「少し加工すればOK」と思い込んでいる
- 代理店・外注まかせで社内チェックが形骸化している
- 権利関係を確認する時間もノウハウも足りず、制作が〆切優先になりがち
広告制作の現場はスピードとインパクトが命。ところが 著作権 や 商標権 の確認が後回しになると、公開後に「権利者からのクレーム→広告停止→損害賠償」という最悪のシナリオに発展しかねません。特に近年はSNSでの炎上拡散が速く、企業イメージが一夜で失墜するケースも増えています。
本記事では、実際に問題となった企業広告の事例をひも解きながら、制作段階でどこをどうチェックすればよいのか、そして社内ルールをどう整備すれば再発を防げるのかを具体的に解説します。まずは「なぜ違反が起きるのか」を把握し、リスクの芽を早期に摘み取るための視点を共有しましょう。
著作権(ちょさくけん) … 音楽・文章・写真など創作物を一定期間、作者が独占的に利用できる権利。無断使用は複製・公衆送信など形態を問わず違法となる。
商標権(しょうひょうけん) … 商品名やロゴなどを区別する標識を独占的に使用できる権利。他社が同一・類似の標章を同一・類似商品に使うと侵害となり、差止・損害賠償の対象になる。
広告に関係する著作権・商標権とは
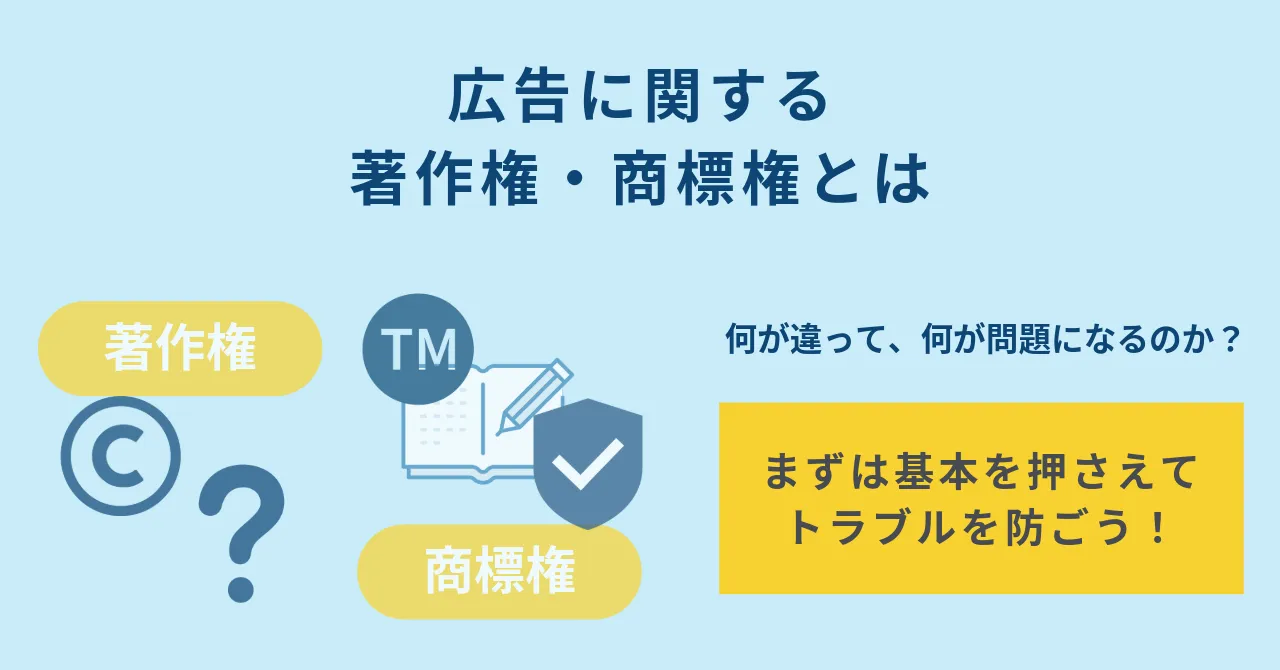
広告を制作するうえで避けて通れないのが「知的財産権」に関する問題です。中でも、著作権と商標権は最もトラブルが起こりやすく、違反すると企業にとって大きな損害につながるリスクがあります。
ここでは、広告表現において押さえておくべき著作権と商標権の基本知識と、現場で起きやすい誤解、実際に問題となるパターンを具体的に解説します。
著作権と商標権の違いを理解しよう
まず、著作権と商標権はそれぞれ守っている対象が異なります。
- 著作権は、音楽、写真、文章、動画などの「創作物」に自動的に発生する権利で、創作した人(著作者)に帰属します。
- 一方で商標権は、商品名やロゴ、キャッチコピーなどに関する「ブランドの識別標識」に与えられる独占的な使用権です。これは申請し登録されたものに限って効力が発生します。
つまり、「創作したもの」には著作権が、「ビジネスで使われる名称やロゴ」には商標権が関係してくるのです。
どんな表現が対象になるのか?
広告に関わる場面で著作権や商標権が発生する対象には、以下のようなものがあります。
- 写真・イラスト(フリー素材も含む)
- 音楽・サウンドエフェクト
- キャッチコピー・文章表現
- 映像・アニメーション
- 商品名・ロゴ・サービス名
たとえば、「SNSで見かけた写真を無断で自社広告に使う」「人気アーティストの楽曲をBGMにする」「有名企業のロゴに似たデザインをキャンペーンで使用する」といった行為は、いずれも権利侵害になる可能性があります。
よくある誤解とリスクの高い落とし穴
広告制作現場では、以下のような誤解が特に多く見られます。
- 「ネットにある画像だから使っていい」
- 「少し加工すれば別物になるから問題ない」
- 「出典を記載すれば引用になる」
- 「昔の曲だから著作権が切れているはず」
こうした認識のまま素材を使用すると、著作権や商標権の侵害となり、権利者からの訴訟リスクが発生します。とくに「フリー素材」とされるものも、利用条件や範囲が厳密に定められているケースが多く、注意が必要です。
広告で問題になりやすい表現とは?
以下のような広告表現は、著作権や商標権に抵触しやすい典型的なパターンです。
- 画像・イラスト:SNSやブログから転載、フリー素材の利用規約違反
- 楽曲:著作権者の許諾なしにCMやYouTube広告に使用
- キャッチコピー:他社の有名コピーを模倣または流用
- ロゴ・商品名:競合企業のブランドに酷似したロゴや表現
このような素材や表現を使う際は、「誰が作ったものか」「どこまでの使用許可があるのか」を明確に確認する必要があります。
知的財産権(ちてきざいさんけん)… 人間の知的な創作活動から生まれる成果物に対して与えられる権利。著作権・商標権・特許権などが含まれ、法律によって保護される。
創作物(そうさくぶつ)… 人が創意工夫をして生み出した音楽・文章・写真・映像などの作品のこと。著作権の保護対象になる。
識別標識(しきべつひょうしき)… 商品やサービスを他社のものと区別するための名称やロゴ、キャッチコピーなどのこと。商標権の保護対象となる。
フリー素材(ふりーそざい)… 無料で使えるとされる写真・音楽・イラストなどの素材。ただし「著作権が放棄されている」わけではなく、利用条件(商用利用可否、クレジット表記の有無など)が定められていることが多い。
引用(いんよう)… 他人の著作物を自分の著作物に正当な範囲で取り込む行為。出典を明示し、主従関係が明確であることなどの条件を満たす必要がある。
著作権切れ(ちょさくけんぎれ)… 著作権の保護期間(原則として作者の死後70年)が終了し、パブリックドメインとなった状態。誰でも自由に利用できるが、正確な期間の確認が必要。
実際に起きた著作権違反の広告事例

著作権の確認が甘かったことで、大手企業でも炎上や謝罪に追い込まれるケースは少なくありません。
ここでは、広告表現に関わる著作権違反の実例を2つ取り上げ、それぞれの背景や問題点、そして企業がどのように対応したかを解説します。チェック漏れの原因もあわせて分析し、再発防止に向けたヒントを探ります。
事例1:企業によるTikTok動画での流行曲無断使用
ある企業が公式TikTokアカウントに投稿した動画で、流行中の楽曲をBGMとして使用していたところ、その使用について著作権者の許諾を得ていなかったことが発覚しました。ユーザーから「企業が無断使用して良いのか」と疑問の声が上がり、楽曲を管理する音楽レーベルも公式に問題を指摘。SNS上で炎上が拡大しました。
当該動画は一定の再生数を獲得して注目を集めていたものの、著作権問題の指摘により削除され、企業は対応に追われることとなりました。
問題点の分析:
- 音楽使用に関する社内確認フローが存在せず、制作担当者が任意で楽曲を選定していた。
- 動画制作にスピード感を求めるあまり、許諾取得のプロセスが省略されていた。
- SNSでの露出が高い分、批判の拡散速度も速く、ブランドイメージへの悪影響が顕著だった。
事例2:商店街イベントでのアニメ主題歌無断演奏
ある地方の商店街イベントにて、地元のバンドが人気アニメの主題歌を無許可で演奏したことがSNS上で話題となり、著作権問題として注目を集めました。演奏の様子が来場者によって動画撮影・投稿されたことで拡散し、アニメ制作会社関係者がSNSで問題を指摘する事態に発展しました。
イベント主催者は、営利目的の演奏ではないという認識のもと使用していたものの、著作権管理団体を通じた適切な手続きを行っていなかったことが明らかになり、演奏中止と謝罪対応を行うことになりました。
問題点の分析:
- 主催者側が「小規模イベントだから問題ない」と誤認しており、演奏権の存在を正しく理解していなかった。
- 会場内での録画・投稿を想定しておらず、SNS経由での拡散リスクが過小評価されていた。
- 音楽の公衆への演奏はたとえ無料イベントであっても許諾が必要であるという基本的な著作権知識の不足が露呈した。
事例3:ケーズデンキCM著作権帰属事件
テレビCMの原版に関する著作権の帰属をめぐり、広告主であるケーズデンキと制作会社との間で紛争が発生しました。問題となったのは、制作会社がCM原版のコピーを広告主の許諾なく作成したとされ、著作権侵害であると主張した点です。
裁判では、CMの発注主体である広告主に著作権が帰属することが認められ、制作会社側の請求は棄却されました。この判決は、広告制作物における著作権の取り扱いについて、契約段階での明確な取り決めがいかに重要であるかを再認識させるものでした。
問題点の分析:
- 著作権の帰属に関する契約条項が不十分で、双方に解釈の違いが生じていた。
- 制作会社側が、成果物を「自社の著作物」とみなして扱ったことで、法的争いに発展した。
- 著作物の帰属を曖昧なまま納品するという慣行が、トラブルの原因となりうることが明らかになった。
事例4:味の素CM楽曲盗作疑惑
味の素が放送したテレビCMに使用された楽曲について、視聴者や関係者の一部から「既存の楽曲と似ているのではないか」との指摘が相次ぎ、楽曲の“盗作疑惑”としてメディアで取り上げられる事態となりました。
実際に法的な争訟には発展しなかったものの、複数の報道機関が作曲者や関係企業への取材を行うなど、注目が集まりました。CM自体は継続して放送されたものの、企業の対応や説明責任が問われる状況となりました。
問題点の分析:
- 楽曲の制作段階で、既存作品との類似性に対するチェック体制が不十分だった。
- 盗作の意図がなかったとしても、印象の類似により世間の批判や誤解を招いた。
- メディア報道を通じて企業や制作側に説明責任が生じ、CMの評価にも影響を与えた。
なぜチェックが漏れたのか?
今回紹介した4つの事例に共通して見られるのは、「確認体制の不備」「制作現場への過度な裁量委任」「著作権・商標権に対するリテラシー不足」です。
たとえば、TikTokでの無断使用やイベントでの無許諾演奏のように、「これくらいなら問題ないだろう」という現場判断が先行し、法的確認が行われないままコンテンツが公開されているケースがありました。また、CM制作をめぐる著作権の帰属問題では、契約書の不備や解釈のずれが、トラブルの原因となっています。
さらに、楽曲の盗作疑惑のように、明確な侵害がなくても「似ている」という印象だけで炎上や報道に発展するリスクもあるため、表現内容のチェックは法的な観点にとどまらず、社会的な受け止め方も考慮する必要があります。
現代の広告制作においては、短納期・高い表現力が求められる一方で、著作権・商標権の境界が複雑化・可視化される時代です。企業としては、法的な確認フローの明文化や、外部委託先も含めたルールの共有、さらには全体の意識レベルを引き上げる研修やガイドラインの導入が、リスク防止の土台となります。
許諾(きょだく)… 著作物の使用について、著作権者から正式な「使ってよい」という承諾を得ること。無断使用はたとえ悪意がなくても違法となる。
炎上(えんじょう)… SNSやインターネット上で、企業や個人の行動が大量の批判を集めて話題になる現象。著作権侵害などの倫理的問題が原因となることが多い。
帰属(きぞく)… 著作権などの権利が「誰にあるのか」を示す言葉。広告制作物などでは、発注者(広告主)と制作者のどちらに帰属するかを契約で明確にする必要がある。
ガイドライン… 社内やチームで統一的な対応をするために定められた基準や手順のこと。広告制作では「この素材は使っていいか」などを判断する際の指針となる。
商標権侵害で問題になった広告の企業事例
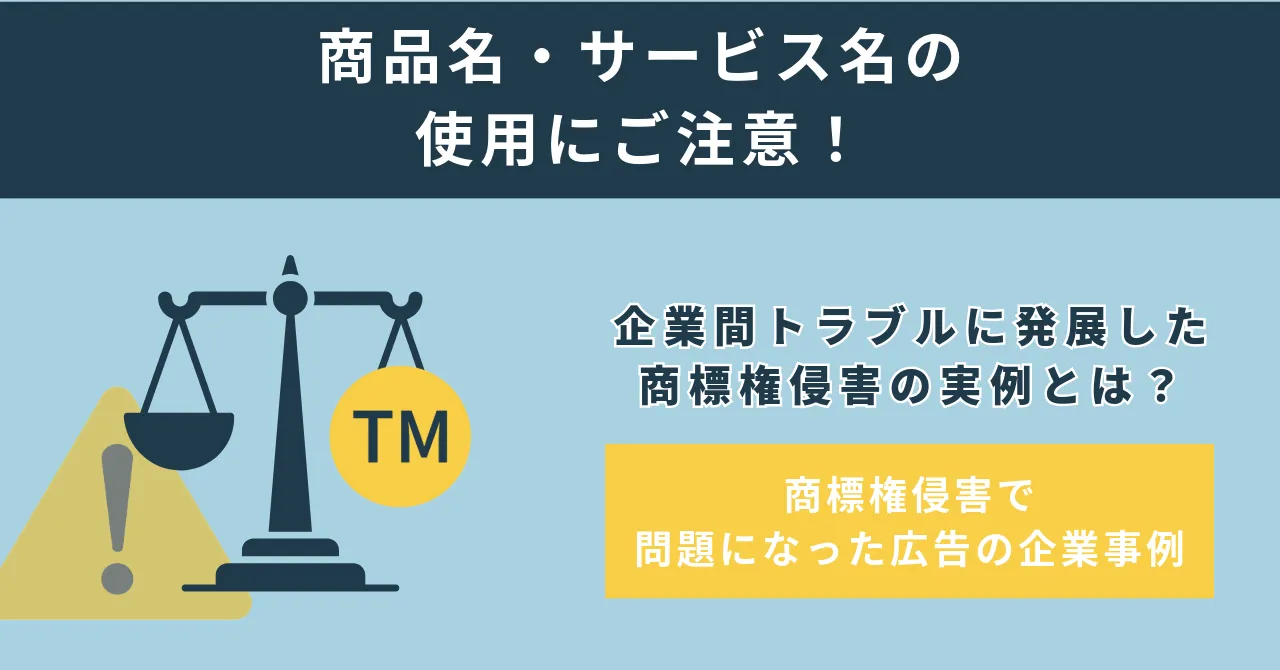
広告における商標権の侵害は、企業にとって法的リスクだけでなく、ブランド価値や社会的信頼を大きく損なう要因になります。特に名称やパッケージ、広告表現において「類似」「混同」を引き起こすケースでは、訴訟や損害賠償に発展することも珍しくありません。
ここでは、実際に商標権侵害をめぐって問題となった3つの企業間トラブルを紹介し、その背景と教訓を整理します。
事例1:石屋製菓 vs. 吉本興業「面白い恋人事件」
北海道銘菓「白い恋人」で知られる石屋製菓は、吉本興業が販売していた土産菓子「面白い恋人」が、自社の登録商標を侵害しているとして訴訟を提起しました。商品名の語感だけでなく、パッケージデザインも類似していたことから、消費者の混同が懸念されました。
結果として、両者は和解に至り、「面白い恋人」の販売は継続されたものの、パッケージの変更とライセンス料の支払いによって決着しました。
問題点の分析:
- 商品名およびパッケージの類似が、商標の出所混同を招くと判断された。
- ユーモアやパロディ性がある商品でも、商標権の観点からは明確なリスクがある。
- 商品企画段階での法的レビューや、権利者との交渉の必要性が示された。
事例2:日本郵便 vs. 札幌メールサービス「ゆうメール事件」
「ゆうメール」という名称をめぐり、日本郵便が商標権を有するにもかかわらず、札幌メールサービス社が自社の広告等でこの名称を使用したとして訴訟が発生しました。
東京地裁は、日本郵便の主張を認め、札幌メールサービスに対して名称使用の差止め命令を下しました。
問題点の分析:
- 登録済みの商標と同一の名称を無断使用した点が、侵害として明確に判断された。
- 公共性があるように見える言葉でも、実際には企業が商標登録している例は多い。
- 特定ワードの使用においても、商標登録の有無を事前に調査する必要がある。
事例3:ゴンチャロフ製菓 vs. モンシュシュ「モンシュシュ事件」
神戸の老舗製菓メーカーであるゴンチャロフ製菓は、自社商標「モンシュシュ」の無断使用に対して、モンシュシュ(大阪)を訴えました。被告側が堂島ロールの名称や広告に「モンシュシュ」を用いたことで、混同のおそれが生じたとされました。
裁判では、商標権侵害が認定され、モンシュシュ側に対して使用差止めと約3,500万円の損害賠償命令が下されました。
問題点の分析:
- 商標の同一性だけでなく、営業地域や商品ジャンルも考慮された上で判断が下された。
- 店舗ブランドや菓子名の類似性は、消費者の誤認リスクを高める。
- 意図的でなくても、「結果として混同を生じさせる表現」はリスクになる。
ブランド信頼と法的リスク、両面への配慮が必要
商標権侵害がもたらすのは、単なる裁判や賠償だけではありません。SNSやニュースでの報道によって、「模倣している企業」「信頼できないブランド」というレッテルが拡散され、長期的な信用の喪失につながることもあります。
広告や商品開発においては、「登録の有無」だけでなく、「混同のおそれ」「社会的評価」までを見越した判断が欠かせません。特に知名度の高い商標に似た表現を使用する場合は、必ず法務チェックを経る体制を構築することが重要です。
出所混同(しゅっしょこんどう)… 消費者が商品の出どころ(企業・ブランド)を誤認してしまう状態。商標権侵害の成立要件のひとつ。
ライセンス料… 商標や著作物などを使用する際に、権利者に支払う許可料。訴訟を避けるための和解条件として使われることも多い。
差止め命令(さしとめめいれい)… 裁判所が、違法な名称・ロゴ・広告表現などの使用を禁止するよう命じる措置。商標権の侵害が認定された場合に下される。
損害賠償命令… 商標や著作権の侵害によって被害を受けた企業に対し、加害側が損害の補償を命じられる法的措置。裁判によって金額が決定される。
なぜ広告現場で著作権・商標権のリスクが見逃されるのか
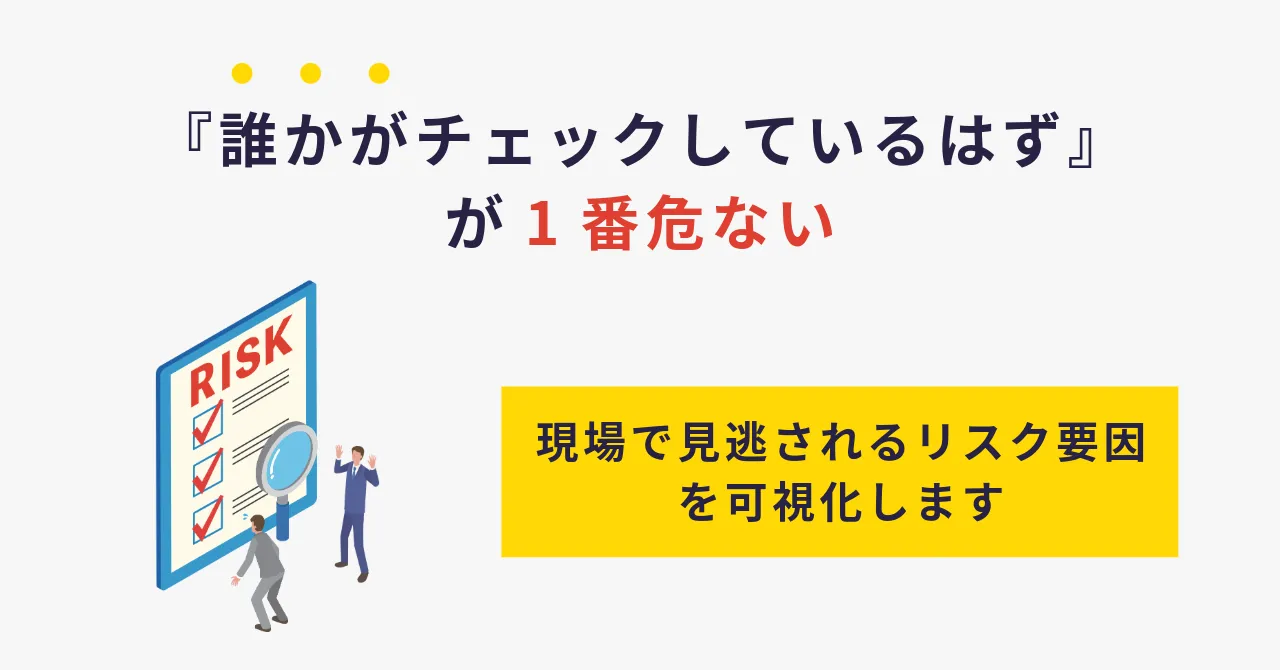
著作権や商標権の侵害は決して悪意をもって行われるわけではなく、多くは「気づかないうちに」発生しています。
では、なぜ広告制作の現場ではこうしたリスクが見逃されてしまうのでしょうか?その背景には、制作フローの複雑さや意識のズレ、知識不足など、いくつかの構造的な課題が存在しています。
広告制作フローにおける責任の分散とあいまいさ
広告は、社内の企画チーム、外部の制作会社、デザイナー、コピーライター、広告代理店など、複数の関係者が関わって作られます。そのため、「誰がどの段階で権利を確認すべきか」という責任があいまいになりがちです。
たとえば、社内では「制作会社が確認してくれているはず」、制作会社側では「指示がなかったから問題ないと思った」といった、責任の押し付け合いが発生することもあります。とくに外注化が進む現在、社内でのチェック体制が機能していないケースが増えています。
「なんとなく大丈夫」な現場思考の危うさ
広告制作の現場では、「前も使ったから大丈夫」「これくらいならバレないだろう」という感覚的な判断で素材を使ってしまうことが珍しくありません。納期やインパクト重視のプレッシャーから、「目立つ表現」が優先され、法的なチェックが後回しになる傾向も見られます。
特にSNSやYouTube広告などスピード重視の媒体では、「確認していたら間に合わない」という理由でチェックを省略するケースも少なくありません。
クリエイター側の知識不足と法務レビューの不在
外部のデザイナーや映像制作者、コピーライターの中には、著作権や商標権の法的知識に乏しい人も多く存在します。自身の表現力には自信があっても、法律面のリスクについては教育を受けていない、というケースが多いのです。
また、制作物に対して社内で法務部や知的財産部門のレビューを行っていない企業も珍しくありません。中小企業やスタートアップでは、そもそも法務担当がいない場合もあり、法的チェックが抜け落ちてしまうのが実情です。
素材管理や契約の不備もリスク要因に
広告に使われる素材(写真、音楽、イラストなど)は、社内外で多くのファイルが共有されるため、出どころや使用許可の状況が不明確になりがちです。たとえば「誰がいつどこから入手した素材か」が記録されていなければ、再使用時にリスクが高まります。
また、外注時の契約書において、「どこまで使用許諾されているのか」「商標や著作物の使用について明記されているか」といった点が不十分なまま契約していると、後からトラブルになる可能性があります。
こうしたリスクを防ぐには、素材管理のルール整備や契約時の確認項目の明文化など、制度面での強化が不可欠です。
外注化(がいちゅうか)… 業務を社外の企業やフリーランスに依頼すること。コストやスピード面ではメリットがあるが、社内での責任やチェック体制が不十分だと、リスク管理が難しくなる。
チェック体制(ちぇっくたいせい)… 制作物に問題がないか確認するための社内の仕組みや流れ。著作権や商標権などの法的リスクを未然に防ぐうえで重要。
インパクト重視(いんぱくとじゅうし)… 広告で目立つことや話題性を最優先に考える姿勢。法的リスクよりもクリエイティブの強さが優先されると、問題発生の可能性が高まる。
法務レビュー(ほうむれびゅー)… 法務部門が広告や契約書などの内容をチェックするプロセス。知的財産や契約の違反がないかを確認する役割を担う。
知的財産部門(ちてきざいさんぶもん)… 企業内で商標・著作権・特許などの知的財産を管理・保護する部署。広告制作時にも、使用する素材や表現が問題ないかを確認する役割を持つ。
使用許諾(しようきょだく)… 他人の著作物や商標などを使用する際、権利者から正式に「使ってよい」という許可を得ること。契約書などで明文化することが重要。
違反を防ぐためのチェックリスト
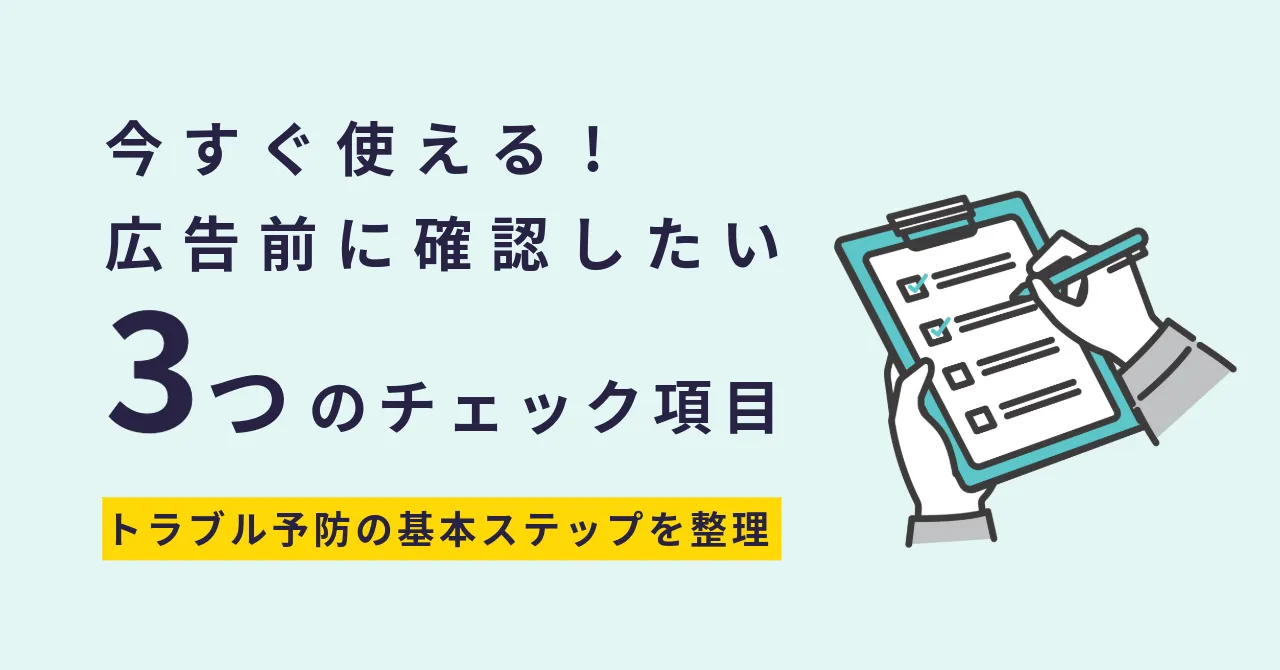
著作権や商標権の侵害を防ぐには、「気をつけよう」という意識だけでは不十分です。重要なのは、誰が・どのタイミングで・何を確認するのかを具体的に明文化し、日常業務の中に組み込むこと。
ここでは、実務で使えるチェック項目や、外注先とのルール整備のポイント、役立つ無料ツールまで、違反防止のための具体策を紹介します。
使用前に確認すべきチェックリスト
広告素材や表現を制作・公開する前に、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 著作権者・制作者が誰かを明記しているか
- 使用範囲(Web・SNS・印刷物など)について許諾を得ているか
- 二次利用の可否が明確になっているか
- 素材がフリー素材であれば、利用規約に違反していないか
- 企業名・商品名・ロゴに関して、登録商標の検索を行ったか
- 過去の広告や制作物との類似性について確認したか
- 社内に使用許諾書や契約書が保管されているか
これらのチェックは、制作担当者だけでなく、企画・広報・法務の複数人でクロスレビューを行うとより確実です。
外注先・代理店と共有すべきルール
著作権・商標権に関するトラブルは、外部の制作会社や広告代理店を通じて発生することも少なくありません。そのため、発注時に下記のようなルールを明確に伝えておく必要があります。
- 著作権・商標権を侵害しない素材・表現を使用すること
- 素材の出典や使用許可について、書面またはメールで証明を残すこと
- 納品物の権利帰属と使用範囲を契約書に明記すること
- 問題が発生した際の責任分担(免責条項)について合意をとること
- 再利用や転用が想定される場合の二次利用許諾を含めること
また、ガイドラインとして簡易的なチェックシートやテンプレートを共有しておくと、やり取りの手間も減り、ルール徹底の精度が上がります。
活用したい無料の確認ツール・サービス
広告制作における著作権・商標権の確認作業には、次のような無料ツールが役立ちます。
- J-PlatPat(ジェイ・プラット・パット)
特許庁が提供する無料の検索サービスで、商標・特許・意匠などの登録状況を確認可能。企業ロゴや商品名が登録されているかどうかを調べる際に必須のツールです。 - 著作権情報センター(CRIC)
著作権に関する法律解説や判例、著作物の取り扱いに関するガイドラインを提供。基礎知識を深めるのに最適です。 - 文化庁 著作権ページ
著作権の最新情報や制度変更について、公式な情報源として活用できます。
これらのツールは無料かつオンラインでアクセス可能なため、広告制作の初期段階で活用することをおすすめします。
許諾書(きょだくしょ)… 著作物や商標などを使用することについて、権利者からの正式な許可を得たことを証明する書面。使用範囲や期間、目的などが明記される。
二次利用(にじりよう)… 一度使用した素材を別の広告や媒体で再利用すること。初回の許諾だけでなく、再利用についても明確な許可が必要。
クロスレビュー… 異なる部署や役割の複数人で相互にチェックを行うこと。法的・表現的な観点から漏れを防ぐ手法として有効。
権利帰属(けんりきぞく)… 素材や制作物の著作権などが、誰に帰属しているか(制作者・発注者・第三者など)を明らかにすること。
免責条項(めんせきじょうこう)… 契約書において、「特定のトラブルが発生した際、どちらが責任を負うか(または負わないか)」を明示した取り決め。トラブル時の責任範囲を明確にするために重要。
テンプレート… 契約書やチェックシートなどの「ひな型」。ルールの抜け漏れ防止や確認作業の効率化に役立つ。
広告表現の社内ルール整備・ガイドライン化のすすめ
著作権や商標権のリスクを根本から防ぐには、個人の意識に頼るのではなく、組織としての仕組み=社内ルールを整備することが重要です。明確な基準と手順を共有することで、誰が関わっても一定の品質と法的安全性を担保できるようになります。
ここでは、広告制作における社内ガイドラインの作り方から、チェック体制、社員教育まで、実践的な整備ポイントを解説します。
広告制作時に使える「表現ガイドライン」の構築方法
まず着手すべきなのは、「広告表現に関するガイドライン」の文書化です。これは、どのような素材・表現がNGか、逆にどのような対応でリスクを回避できるかをまとめた社内基準書です。以下のような項目を盛り込むと実用的です。
- 著作物・商標の利用可否と確認方法
- 使用許諾が必要なケースと判断基準
- フリー素材利用時のチェックポイント(出典・規約確認など)
- 許諾書・契約書の保存ルールと管理体制
- 参考にすべき外部リソース(J-PlatPatや文化庁サイト等)
このガイドラインは、制作フローに自然に組み込める内容とし、現場の実務に即して設計することが重要です。
誰がいつチェックする?法務レビューの導入ポイント
ガイドラインを整備したら、それを「運用するための流れ」も明確にしましょう。特に重要なのは、法務部門との連携タイミングです。
- 制作初期(企画段階):使用予定の素材や表現に問題がないか、事前に法務部がアドバイス
- デザイン制作後:完成前に法務チェックを行い、修正の余地を確保
- 公開前:最終確認のワークフローを組み込み、見落としを防ぐ
上記のような「三段階の確認ポイント」を設定すると、制作現場と法務のすれ違いを最小限に抑えることができます。
社内研修やチェックリストでリテラシーを底上げする
ルールを作っても、それが社内に浸透しなければ意味がありません。そのためには、定期的な研修や啓発活動が欠かせません。
- 新入社員・異動者向けにガイドラインの研修を実施
- 制作担当者や外注管理者に対する実務ベースのチェック教育
- NG事例・炎上事例をもとにしたケーススタディの共有
- 簡易な「広告表現チェックリスト」を配布して日常的に活用できる環境づくり
特に「知っているつもり」のまま業務を進めてしまうことが、トラブルの温床になります。全社員に一定の知識レベルを持たせることが、最大の予防策となります。
トラブルを未然に防ぐ「仕組み」と「風土」をつくる
最終的には、「チェックするのが当たり前」という組織文化をつくることが、長期的な違反予防につながります。具体的には次のような取り組みが有効です。
- 権利関係に関するチェックを通過しなければ広告が公開できないワークフローの構築
- ルールに違反した際のリスクや責任範囲を明文化
- 他部門(営業、CS、広報など)とも共通理解をもつことで、社内全体のリスク感度を高める
制度と意識、両面からのアプローチを通じて、トラブルの芽を事前に摘み取ることが可能になります。
ガイドライン… 社内で守るべき基準や判断の目安をまとめた文書。広告表現では「NGな素材や表現」「確認すべき手順」などを明示し、トラブルを未然に防ぐ役割を果たす。
ワークフロー… 業務の流れや手順を体系的に整理したもの。広告制作では「企画→制作→法務チェック→公開」などの流れにそって確認作業を組み込む。
三段階チェック… 制作初期・中間・公開直前の3タイミングで権利関係を確認する方法。チェック漏れを防ぎ、修正の余地を確保しやすい仕組み。
リテラシー… ある分野における知識や理解、活用能力のこと。ここでは著作権や商標権に関する正しい理解・判断力を指す。
ケーススタディ… 実際に起きた事例をもとにした学習方法。炎上事例などを共有することで、注意すべきポイントを現場感覚で学べる。
組織文化(そしきぶんか)… 組織内で当たり前とされている価値観や行動様式。「チェックが当たり前」となるような文化づくりは、ルールの形骸化を防ぐ。
共通理解(きょうつうりかい)… 部門をまたいで同じ知識や判断基準を共有すること。広告制作に関わる他部署(営業・広報・カスタマーサポートなど)と連携することで、リスク感度が高まる。
法的リスクと企業が受ける制裁・損失
著作権や商標権の侵害は、単なる“うっかりミス”では済まされません。違反が発覚すれば、法的責任を問われるのはもちろんのこと、企業の信頼やブランド価値にも深刻なダメージを与えます。
このセクションでは、知的財産の侵害によって企業が実際に直面する「法的リスク」と「ビジネス上の損失」について、具体的に整理します。
民事責任:損害賠償や差止請求を受けるリスク
著作権者や商標権者は、侵害が確認された場合、民事訴訟によって損害賠償請求や広告の差止請求を行うことができます。これは、たとえ故意でなくても、違反行為があった事実に基づいて法的措置が取られます。
たとえば、無断で音楽を使用したCMが放送された場合、その楽曲の権利者から「CMの放送中止」や「使用料の何倍にも上る損害賠償金」を請求されることがあります。広告が大規模に展開されていた場合、数百万円〜数千万円単位の負担となるケースもあります。
また、商標侵害では、自社の商品やサービスの名称・ロゴの差し止め命令が下されることもあり、再ブランディングや在庫廃棄のコストが発生することもあります。
刑事責任:悪質な場合は罰金刑・懲役刑も
著作権法および商標法には刑事罰の規定も存在します。特に営利目的で悪質な侵害を行った場合は、企業だけでなく担当者個人が処罰される可能性も否定できません。
たとえば、著作権法では10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)が科されることがあり、商標法でも同様に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科が適用されます。
実際には民事での解決を目指すケースが多いものの、違法性が明白で悪質な場合や、権利者の怒りを買った場合には刑事告訴に発展する可能性もあるため、リスクとして十分に認識しておく必要があります。
企業イメージや信用の失墜が長期的に響く
知的財産権の違反は、法的制裁よりも企業イメージへのダメージのほうが長期的な影響を及ぼします。たとえば次のような事態が想定されます。
- SNSや報道で炎上し、「著作権侵害企業」のレッテルを貼られる
- CM放送停止によりマーケティング施策が頓挫
- 取引先企業からの信頼が失われ、パートナー契約を打ち切られる
- 株式市場でのイメージ悪化により、株価が下落
- 新卒・中途の応募が減るなど、採用にも影響
たとえ迅速に謝罪や対応を行ったとしても、「炎上した過去がある企業」というイメージはネット上に半永久的に残り続けます。短期的な損失以上に、企業としての信頼回復に長い時間とコストがかかる点が最大のリスクです。
CM放送停止や報道被害など、実例に基づく損失の重み
過去には、著作権侵害が認定されたことにより、テレビ番組やCMで使用されていた楽曲の利用が中止となり、損害賠償が命じられた事例があります。たとえば「記念樹事件」では、著作権侵害が最高裁で認定された結果、フジテレビが番組での楽曲使用を中止し、関係各社に対して約2,300万円の損害賠償が命じられました。また、JASRACも利用許諾を中止し、公の場での演奏も事実上不可能となるなど、長期的にブランドや事業活動に影響を与えました。
さらに、海外ではザ・ブラック・キーズの楽曲がピザハットやホーム・デポのコマーシャルに無断で使用され、バンド側が訴訟を起こし、各社に対して損害賠償と楽曲使用の差止めを求める事態となりました。
また、商標権侵害が原因で広告や商品表示が問題視され、企業が謝罪やパッケージ変更、損害賠償を余儀なくされた「面白い恋人事件」などの実例もあります。これらはすべて、知的財産権の軽視が企業に多大な経済的・社会的損失をもたらすことを示しています。
損害賠償(そんがいばいしょう)… 他人の権利を侵害したことによって生じた損害を、金銭で補償すること。著作権や商標権を侵害した場合、権利者から訴えられ、賠償金の支払いを命じられることがある。
差止請求(さしとめせいきゅう)… 違法な広告や商標の使用などをやめるよう裁判所に求める法的手続き。広告の放送停止や商品名の変更などが命じられる。
併科(へいか)… 懲役と罰金の両方が同時に科されること。たとえば「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科」と記されている場合、両方の刑を受ける可能性がある。
刑事告訴(けいじこくそ)… 被害者(著作権者・商標権者など)が、警察や検察に対して加害者の刑事責任を問うよう求めること。営利目的の侵害行為などで発展するケースがある。
ブランドイメージ… 消費者や社会が企業・商品に対して持っている印象や信頼感。炎上や違法行為によって傷つくと、売上や採用、株価など幅広い面で悪影響が出る。
差し替え対応… 問題が発覚した広告やCMなどを、別の内容に切り替える対応。制作費用の再発生だけでなく、スケジュールやメディア枠の調整にも多大なコストがかかる。
まとめ&取り組むべきアクションは
著作権や商標権の侵害は、たとえ故意でなくても「知らなかった」では済まされません。広告という多くの人の目に触れる表現だからこそ、企業には高い法令遵守意識と確認体制が求められます。
ここでは、これまでの内容をふまえ、企業が今すぐ取り組むべきアクションを整理します。
トラブルを防ぐために、まず現状を見直すことから始めよう
広告表現におけるリスク対策の第一歩は、自社の現状を客観的に把握することです。以下のような視点でチェックしてみましょう。
- 素材使用に関するルールやガイドラインが存在するか
- 使用許諾・著作権の確認フローが整備されているか
- 外注先・代理店と適切な契約・運用ルールを締結しているか
- 社内に著作権・商標権のリテラシーが根づいているか
もしこれらの点に不安があるようであれば、まずは「基準の明文化」と「社内ルールの整備」から始めましょう。
関係者全員で“リスク共有”する仕組みを
リスク対策は一人の担当者が背負うものではありません。広告制作に関わるすべての関係者――企画、広報、デザイン、法務、外部パートナーまで、全員が共通のリスク意識を持つことがトラブル防止のカギです。
そのためには、ルールを作るだけでなく、チェックリストの運用や研修の実施、確認フローの定着といった「日常の実践」が重要です。
今すぐ取り組むべき具体的なアクション
- 社内ガイドラインの整備・見直し
- 外注先との契約書の再確認(権利関係・責任分担など)
- 制作フローに法務チェックの工程を追加
- 著作権・商標権に関する研修・資料の共有
- 無料ツール(J-PlatPatなど)を活用した商標調査の導入
小さな取り組みの積み重ねが、重大な法的トラブルを防ぎ、健全な広告文化の育成につながります。
法令遵守(ほうれいじゅんしゅ)/コンプライアンス… 法律や規制、社内ルールを守ること。広告においては、著作権法・商標法などの知的財産関連法も含まれる。企業の社会的信頼を保つうえで不可欠。
確認フロー… 制作物や素材の使用可否を判断するための一連の確認手順。誰が・いつ・何をチェックするかを明確にすることで、リスクの見逃しを防ぐ。
基準の明文化(きじゅんのめいぶんか)… 暗黙のルールや慣習を、文書として明確に示すこと。ガイドラインやチェックリストとして形にすることで、誰でも同じ基準で判断できるようになる。
リスク共有(りすくきょうゆう)… ある業務に関わる複数の人・部署が、同じリスク意識と責任を持つこと。広告制作では、関係者全員が知的財産の問題を自分ごととしてとらえることが重要。
責任分担(せきにんぶんたん)… トラブルが起きた場合に「誰がどこまで責任を負うか」を明確にすること。契約書で事前に定めておくと、万一の際の混乱を防げる。