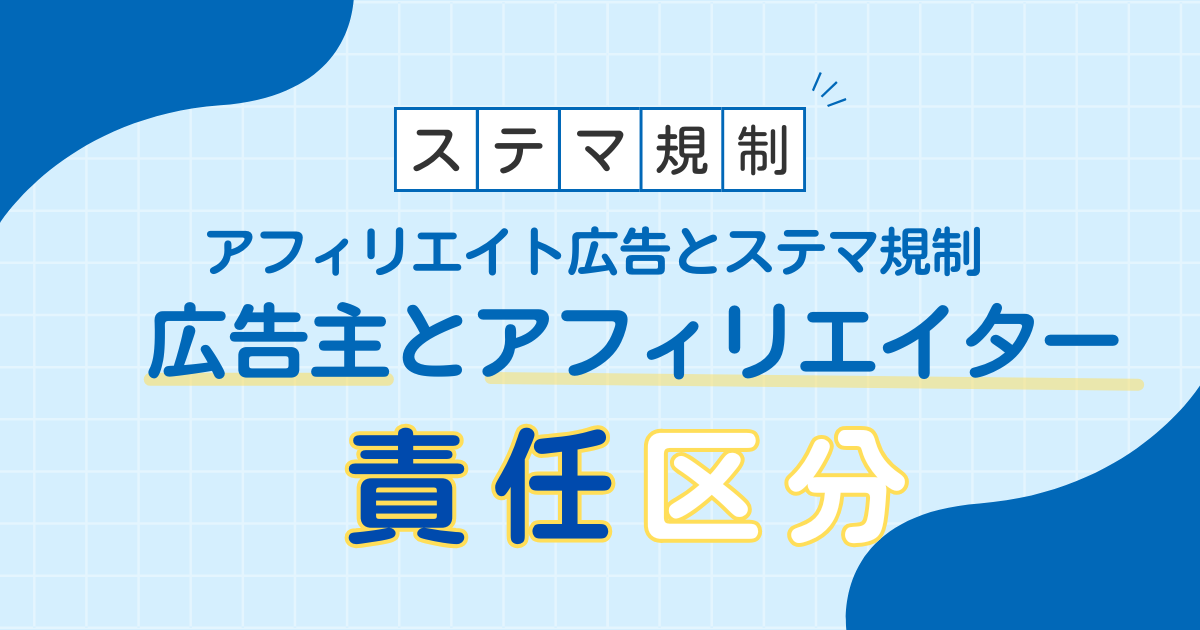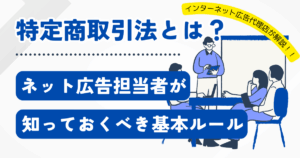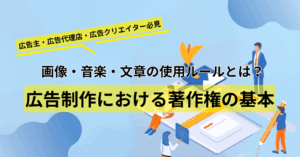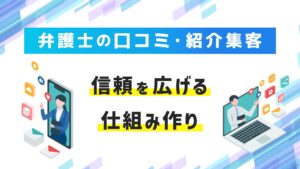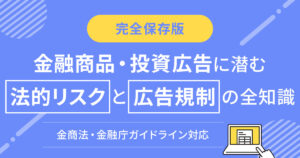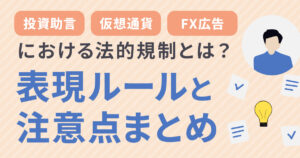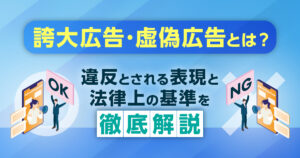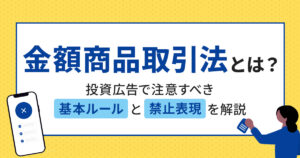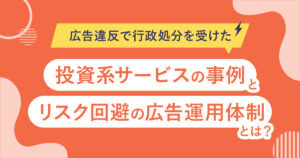「アフィリエイト広告でもステマ規制の対象になるって本当?」
「広告主として、アフィリエイターの投稿内容まで責任を負わなければならないの?」
2023年10月のステルスマーケティング規制導入により、多くの広告担当者やアフィリエイターがこうした疑問を抱えています。
これまでグレーゾーンとされてきたアフィリエイト広告も、景品表示法改正により明確な規制対象となりました。
しかし、規制の詳細や責任の所在について正確な情報が浸透していないため、現場では混乱が生じているのが現状です。
特に深刻なのは、広告主とアフィリエイターの責任範囲が曖昧なことです。「アフィリエイターが勝手に投稿した内容だから関係ない」と考える広告主や、「広告主の指示通りに書いているから問題ない」と思い込むアフィリエイターも少なくありません。
本記事では、2023年のステマ規制導入の背景から、アフィリエイト広告における具体的な規制内容、広告主とアフィリエイターそれぞれの責任範囲、リスク回避策を網羅的に解説します。
この記事を読むことで、ステマ規制の正確な理解とリスク回避策を身につけ、安心してアフィリエイト広告を運用できるようになるでしょう。
法的リスクを避けながらも効果的なマーケティング活動を実現しましょう。
ステマ規制とは?2023年の景品表示法改正の変更点
2023年10月1日、日本でステルスマーケティング(ステマ)を規制する新たな法的枠組みが施行されました。この規制は景品表示法改正により導入され、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を不当表示として禁止するものです。
従来は自主規制や業界ガイドラインに委ねられていたステマ対策が、法的拘束力を持つルールとして明文化されました。違反した場合は措置命令の対象となり、悪質なケースでは刑事罰も科される可能性があります。
消費者庁は、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(以下、「指定告示」という。)について、別紙1のとおり指定を行い、別紙2のとおり指定告示の運用基準(以下、「運用基準」という。)を策定しました。
引用:「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」 | 消費者庁
アフィリエイト広告も対象となった背景
アフィリエイト広告がステマ規制の対象となった背景には、インターネット広告市場の急速な拡大と消費者トラブルの増加があります。
ブログやSNSでの商品レビューが広告であることを明示せず、個人の体験談や感想として装う手法が横行していました。
消費者庁の調査では、「広告だと知らずに購入した」「実際の商品と印象が大きく異なった」といった相談が年々増加していることが判明しています。
インフルエンサーマーケティングの普及も規制導入の要因の一つです。フォロワーからの信頼を基盤とする投稿が実は対価を伴う広告であったという事例が相次ぎ、消費者の不信が高まりました。
明示義務の要件と違反時の罰則
ステマ規制における明示義務は、「事業者の表示であることを一般消費者が明瞭に判別できるようにすること」です。単に「広告」と記載すれば良いのではなく、消費者が容易に認識できる方法での表示が求められます。
具体的な明示方法として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言を投稿の冒頭や目立つ位置に記載しましょう。文字の大きさや色、配置にも配慮し、一般的な消費者が見落とさない程度の視認性を確保する必要があります。
SNSでは「#PR」「#広告」「#提供」といったハッシュタグによる明示も認められています。ただし、「#thanks」や「#gift」のような曖昧な表現では不十分とされる可能性があるでしょう。
動画コンテンツでは、冒頭での音声による明示か、画面上への文字表示の継続が必要です。説明欄のみの記載では不十分とされるケースも少なくありません。
違反時の罰則として、まず措置命令が下されます。不当表示の差止め、再発防止策の策定、消費者への周知が求められ、命令内容は消費者庁で公表されます。
措置命令に従わない場合や悪質な違反は刑事罰の対象となり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人では3億円以下の罰金が科される可能性があります。
また、行政処分による企業の信用毀損やブランドイメージの低下といった間接的な損害も予想されるでしょう。
第六章 罰則
引用:不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov 法令検索
第四十六条 措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
ステルスマーケティングとアフィリエイト広告の関係
ステルスマーケティングとアフィリエイト広告の関係を理解するには、「広告であることを隠す行為」の本質を把握する必要があります。
アフィリエイト広告は第三者による客観的な商品評価として受け取られやすく、その影響力の大きさゆえにステマの温床となりやすい構造を持っています。
どのような表現がステマと判断されるのか
ステマと判断される基準は「一般消費者が事業者の表示であることを判別できるかどうか」です。
まず、対価性の有無が重要な判断基準となります。商品提供、金銭授受、アフィリエイト報酬など、経済的利益が発生する状況では明示が必要です。
表現の客観性も重要な判断材料のひとつです。「たまたま使ってみたら良かった」「友人に勧められて」といった偶然性や第三者性を装う表現は、ステマと判断される可能性が高くなります。
広告主との関係性を曖昧にする表現も問題となるでしょう。「愛用者」として紹介しながら実際は商品提供を受けている場合などがこれに該当します。
投稿のタイミングや頻度も判断材料です。商品発売と同時期に複数のインフルエンサーが似た内容で投稿している場合、組織的な広告活動として認識される可能性があります。
PR表記が必要となる具体例
媒体別のPR表記が必要な具体例を解説します。
- ブログ
-
商品レビュー記事の冒頭に「PR」「広告」「アフィリエイト広告を含みます」といった表記が必要です。記事末尾のみでは不十分とされる場合があります。
- SNS
-
投稿文冒頭やハッシュタグでの明示が求められます。「#PR」「#広告」「#提供」などを使用し、Twitterでは文頭に「【PR】」といった表記を入れることが推奨されています。
- YouTube動画
-
冒頭での音声明示と画面上への継続的な文字表示が効果的です。説明欄への記載も重要ですが、それだけでは不十分なケースが多いでしょう。
- 比較サイト
-
各ページの目立つ位置に「アフィリエイト広告を掲載しています」といった包括的な表記が必要です。
表記が不十分なアフィリエイト広告のNG例
表記が不十分とされる具体的なNG例を説明します。
- 位置や視認性の問題
-
ブログ記事の最下部に小さな文字での記載や、SNS投稿のハッシュタグ最後尾に英語で記載するケースは不十分とされる可能性があります。
- 曖昧な表現
-
「#gift」「#thanks」といったハッシュタグのみや、「商品をいただきました」という表現だけでは、広告であることが明確に伝わりません。
- 隠蔽的な表現
-
「偶然見つけた商品ですが」「友人に教えてもらった」といった自然発生的な紹介を装いながら、実際にはアフィリエイト報酬を得ている場合は明らかなステマ行為です。
- 動画
-
冒頭数秒間のみの表示で、その後一切表記がないケースがNG例となります。長時間動画では継続的な表示や定期的な音声言及が必要です。
複数商品紹介時の部分的な表記も問題です。10個の商品中3つがアフィリエイト広告にも関わらず、どれが広告商品か特定できない表記方法は不適切とされます。
これらを避けるには、消費者の立場で「この表記で広告だと分かるか」を常に自問し、明確で分かりやすい表示を心がけることが重要です。
広告主とアフィリエイターの責任区分
ステマ規制において最も重要な問題が、広告主とアフィリエイターの責任区分です。
従来「アフィリエイターが勝手に書いた内容だから関係ない」と考える広告主や、「指示通りだから問題ない」と思うアフィリエイターが多く存在しましたが、実際は両者ともに法的責任を負う可能性があります。
景品表示法上、「事業者」が規制対象となりますが、アフィリエイト広告では広告主だけでなく、一定条件下でアフィリエイター自身も事業者として扱われる場合があります。
広告主の責任:表示管理義務と監督責任
広告主は、自社商品・サービスに関するすべての広告表示について責任を負います。これは直接制作した広告だけでなく、アフィリエイターによる表示も含まれます。
- 表示管理義務
-
広告主の責任として、まずアフィリエイターに対する適切な指導・管理です。アフィリエイト広告を開始する際、ステマ規制の内容や適切な表示方法について明確に伝達する必要があります。
また、定期的な表示状況の確認も重要で、アフィリエイターの投稿内容をモニタリングし、不適切な表示があった場合は速やかに修正を求めなければなりません。
- 監督責
-
広告主は「使用者責任」として位置づけられる場合があります。アフィリエイターが不適切な表示を行った場合でも、広告主の指導・監督が不十分であったと判断されれば、連帯して責任を負う可能性があります。
- 管理体制
-
具体的な管理体制として、契約書面での明示が重要です。アフィリエイト契約において、ステマ規制遵守条項を明記し、違反時の対応方法を定めておく必要があります。
さらに、定期的な研修や情報提供を通じて、アフィリエイターの法令理解を促進することも広告主の責務となります。
アフィリエイターの責任:正確な情報提供と明示義務
アフィリエイターも、一定の条件下で景品表示法上の「事業者」として扱われ、独立した責任を負います。特に、継続的に広告活動を行い、相当の収益を得ているアフィリエイターは事業者性が認められる可能性が高くなります。
- 明示義務
-
アフィリエイターには適切なPR表記を行う責任があります。これは広告主からの指示の有無に関わらず、アフィリエイター自身の法的義務です。
「広告主が指示しなかった」という理由で責任を免れることはできません。
- 正確な情報提供義務
-
アフィリエイターは、実際に商品を使用せずに体験談を作成したり、事実と異なる効果効能を記載したりしてはいけません。
これらの行為は、ステマ規制以外にも景品表示法の優良誤認表示として問題となる可能性があります。
- 継続的な表示管理責任
-
一度投稿した内容についても、法改正や新たなガイドラインに合わせて適宜修正を行う必要があります。過去の投稿についても「知らなかった」では済まされません。
個人のアフィリエイターであっても、事業的規模で活動している場合は法人と同様の責任を負います。副業として行っている場合でも、継続性や収益性が一定程度認められる場合には、事業者として扱われる可能性があるため注意が必要です。
両者にまたがる共同責任と連帯リスク
広告主とアフィリエイターの責任は、多くの場合において重複し、両者が連帯して責任を負う構造となっています。
- 共同責任の発生要件
-
まず表示内容の決定過程における両者の関与があります。広告主が具体的な表現内容を指示した場合や、アフィリエイターが独自に作成した内容を広告主が事前承認した場合は、明確な共同責任が発生します。
- 継続的な関係性
-
長期間にわたって同一のアフィリエイターと取引を続けている場合、広告主には適切な指導・監督責任があり、不適切な表示を放置した場合は共同責任を問われる可能性があります。
- 連帯リスク
-
措置命令が両者に対して同時に下される場合があります。この場合、広告主は自社の直接的な広告表示だけでなく、アフィリエイターの表示についても是正責任を負うことになります。
経済的リスクも連帯して発生します。課徴金制度の適用や、消費者からの損害賠償請求において、広告主とアフィリエイターが連帯責任を負う場合、どちらか一方の支払い能力が不足していても、もう一方が全額を負担する可能性があります。
- リスク回避のための対策
-
対策として明確な責任分担の合意が重要です。契約書において、それぞれの責任範囲と違反時の対応方法を明記し、定期的な見直しを行う必要があります。
また、両者間での情報共有体制を整備し、法令変更や新たなガイドラインについて迅速に情報を共有することも重要でしょう。
最終的に、ステマ規制下においては「責任の押し付け合い」ではなく、「協力しての法令遵守」が求められます。
広告主とアフィリエイターが互いの責任を理解し、適切な役割分担のもとで連携することが、リスク回避と効果的な広告運用の両立につながるのです。
アフィリエイト広告とステマ規制への対応方法
ステマ規制強化に伴い、アフィリエイト広告の適切な運用には単なる「PR表記」を超えた広告の透明性確保が必要となりました。
ここでは、各関係者がどのように対応すべきか解説していきます。
アフィリエイター側の対応
アフィリエイターは消費者と直接接点を持つ発信者として、広告であることを明確に示す責任があります。対応の中心となるのは「広告・PR表記の適切な掲載」です。
なぜならば、消費者が広告と認識できない形での情報発信はステルスマーケティングとなり、景品表示法違反に問われる可能性があります。
具体的には以下の対応が必要です。
- 目立つ位置への明確なPR表記
-
- 記事冒頭(スクロールなしで視認できる位置)に「PR」「広告」などの表記を配置する
- フォントサイズや色を工夫し、背景色との対比で視認性を確保すること
- SNS投稿の場合は本文の先頭に「#PR」などのハッシュタグを付ける
- 経済的利益の開示
-
- 「本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています」などの表記を明記
- 成果報酬の有無や形態(固定報酬か成果連動か)についても可能な範囲で開示
- 商品提供を受けている場合はその旨も明記することが望ましい
- 事実に基づいた情報発信
-
- 実際に使用・体験していない商品についてはその旨を明記
- 効果や性能について根拠のない誇大表現を避ける
- 比較記事の場合は比較条件や選定理由を明確にする
アフィリエイターにとっては、こうした透明性の確保が短期的には収益低下につながると懸念する声もあるでしょう。しかし長期的には、読者からの信頼構築につながり、持続可能なアフィリエイト活動の基盤となります。
広告主側の対応
広告主はアフィリエイターの表示内容に対して管理責任を負うことになりました。これは単にガイドラインを作成するだけでなく、実際の表示状況を監視し、必要に応じて是正を求める積極的な義務となっています。
その背景には、広告主が経済的利益を提供する立場として、不当表示を防止する責任があるという考え方があるのです。
広告主が実施すべき具体的な対応は以下の通りです。
- アフィリエイトガイドラインの整備
-
- PR表記の具体的な方法(位置、大きさ、表現など)を明示
- 禁止表現や使用可能な表現の明確化
- 違反時の対応フローを策定(報酬停止、契約解除など)
- 定期的な更新と周知徹底の仕組み作り
- 契約書面の見直し
-
- PR表記義務と表示管理義務を明記
- アフィリエイターの表示内容に対する修正要請権の確保
- 違反時のペナルティ条項の追加
- 共同責任の範囲を明確化すること
- モニタリング体制の構築
-
- 定期的なアフィリエイト記事のチェック体制の確立
- 自動監視ツールの導入や外部委託の検討
- 問題発見時の迅速な対応フローの整備
- 改善指導と是正確認のプロセス化
広告主にとって、これらの対応は人的・金銭的コストを伴うものです。しかしながら、消費者庁による措置命令や課徴金納付命令のリスクを考えれば、予防的措置として十分に合理的な投資と言えるでしょう。
ASPや代理店経由の場合の注意点
アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)や広告代理店を介してアフィリエイト広告を展開する場合、責任の所在が複雑になります。
ここで重要なポイントは、最終的な表示管理義務は広告主にあるという点です。その理由は、たとえASPや代理店を経由していても、法的には広告主が経済的利益提供者として位置づけられるからなのです。
ASPや代理店経由での運用における注意点は以下の通りです。
- 役割と責任の明確化
-
- 契約書面でASP・代理店・広告主・アフィリエイターの責任範囲を明確化
- 表示内容の承認フローを事前に設計
- 問題発生時の対応責任者と連絡体制の整備
- 定期報告の内容と頻度の取り決め
- 中間業者の選定基準の厳格化
-
- ステマ規制対応状況をASP・代理店選定の重要基準とする
- アフィリエイター管理体制の確認
- モニタリングツールや報告体制の充実度を評価
- コンプライアンス意識と実績の確認
- 重層的なチェック体制の構築
-
- ASP・代理店任せにせず、広告主自身も抜き打ち確認を実施
- 第三者による監査の導入検討
- 消費者からの指摘を受け付ける窓口の設置
- 定期的な合同レビュー会議の開催
実務上の課題として、ASPを通じた数百〜数千のアフィリエイターすべてを監視することは困難という点があります。
そのため、リスクベースアプローチが有効であり、影響力の大きいアフィリエイターや過去に問題のあったアフィリエイターを重点的に監視する方法が取られています。
アフィリエイト広告とステマ規制への対応は、単なる法令遵守の問題ではなく、消費者との信頼関係構築という観点からも重要です。
ステマと認定されないためのチェックリスト
アフィリエイト広告がステルスマーケティング(ステマ)と認定されないためには、具体的なチェックポイントを押さえておくことが重要です。
ポイントは、「消費者が広告と認識できる明確さ」を確保することにあります。その理由は、ステマ規制の本質が「広告であることを隠す」行為を禁止することにあるからです。
具体的なチェックポイントを見ていきましょう。
PR表記の位置・表現・明瞭性の基準
PR表記は単に「どこかに書いてある」だけでは不十分であり、消費者が確実に認識できる形で提示する必要があります。これは景品表示法の趣旨が「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保する」ことにあるためです。
PR表記に関する具体的なチェックリストは以下の通りとなっています。
- 位置に関するチェック
-
- コンテンツの冒頭(スクロールなしで視認できる位置)に配置されているか
- タイトルの近く、または目立つヘッダー部分に表示されているか
- 長文記事の場合、途中と末尾にも繰り返し表示されているか
- アフィリエイトリンクの近くにも表示があるか
- 表現に関するチェック
-
- 「PR」「広告」「アフィリエイト広告」など明確な表現を使用しているか
- 「※当サイトは広告を含みます」などの婉曲表現だけになっていないか
- 「Sponsored by」「提供:」といった表現は提供元を明記しているか
- 経済的利益の内容(成果報酬型か固定報酬型か)が示されているか
- 明瞭性に関するチェック
-
- フォントサイズは本文と同等以上か(小さすぎないか)
- 背景色と十分なコントラストがあり視認性が確保されているか
- 特殊な装飾で読みにくくなっていないか
- スマートフォン表示でも視認性が保たれているか
実務上のポイントとして、消費者庁は「一見して広告であることが分かる」ことを重視しています。そのため、記事下部だけに小さく記載する、背景と同系色で目立たなくするといった表示方法は避けるべきでしょう。
最近では、記事上部に枠囲みで「この記事はアフィリエイト広告を含みます」と明記するスタイルが一般的になっています。
誤認を招かないレビューや体験談の書き方
レビューや体験談は消費者の購買意思決定に大きな影響を与えるため、特に注意が必要です。アフィリエイト広告における体験談やレビューは、事実に基づいた正確な情報提供が求められるのです。
なぜなら、虚偽・誇大な表現は景品表示法第5条の優良誤認にあたる可能性があるからです。
誤認を招かないレビュー作成のチェックリストは以下の通りです。
- 体験の真実性に関するチェック
-
- 実際に使用・体験していない商品の場合、「お試しではなく情報をまとめました」など明記しているか
- 使用期間や使用条件を正確に記載しているか
- 個人の感想と客観的事実を区別して記述しているか
- 典型的な使用結果と異なる場合はその旨を説明しているか
- 表現の適切性に関するチェック
-
- 「絶対」「必ず」「驚異の」などの断定的表現を避けているか
- 効果・性能について科学的根拠のない表現をしていないか
- 比較表現を用いる場合、比較対象と条件を明記しているか
- 「業界最高峰」「No.1」などの最上級表現には客観的根拠があるか
- バランスの取れた情報提供
-
- メリットだけでなくデメリットや注意点も記載しているか
- 商品・サービスの対象者や適合条件を明確にしているか
- 複数の視点や意見を紹介しているか
- 価格や支払条件などの重要情報を明記しているか
実務上のアドバイスとして、「100%満足」「誰でも成功」といった全ての人に当てはまるような表現は避け、「私の場合は効果がありました」「私の肌質では相性が良かった」といった個人の体験として限定する表現を心がけることが重要です。
また、公正取引委員会は「口コミサイトのための景品表示法上の問題点と留意事項」において、サクラレビューの禁止も明確にしています。
法律に基づいた対応をする際に参考にすべきガイドライン
ステマ規制への対応を検討する際には、公的機関が発行する各種ガイドラインを参照することが有効です。これらのガイドラインは法的拘束力はないものの、規制当局の解釈や運用方針を示すものであり、実務上の重要な指針となるからです。
参考にすべき主要なガイドラインは以下の通りです。
- 消費者庁:「景品表示法におけるステルスマーケティングに関する執行方針」
-
- ステマ規制の対象範囲と判断基準
- 「広告であることの表示」の具体例
- 表示管理措置の考え方と事例
- 違反時の措置命令や課徴金納付命令の基準
- JIAA(日本インタラクティブ広告協会):「ネイティブ広告ハンドブック」
-
- Web広告におけるPR表記の推奨方法
- プラットフォーム別の表示ガイドライン(SNS、ブログなど)
- 消費者視点での判別性確保の工夫
- 業界自主規制の動向
- JAA(日本広告主協会):「アフィリエイトマーケティング適正化ガイドライン」
-
- 広告主の表示管理義務の実施方法
- アフィリエイターとの契約時の留意点
- モニタリング体制の構築例
- 問題発生時の対応フロー
これらのガイドラインを活用する際のポイントとして、ガイドラインは「最低限の基準」を示すものであり、より安全性を高めるためには上乗せした対応を検討することが賢明です。
消費者庁ガイドラインでは「広告である旨の表示」が求められていますが、実務上は「広告である旨」に加えて「経済的利益の内容」や「広告主名」まで明記することで、より透明性を高める対応が増えています。
ステマと認定されないためのチェックポイントは、単なる法令遵守の問題ではなく、消費者との信頼関係構築の基盤となるのです。
まとめ
本記事では、アフィリエイト広告とステマ規制の関係性、そして広告主とアフィリエイターの責任区分について詳しく解説しました。
改めて重要なポイントを整理します。
- ステマ規制の本質と法的枠組みの理解
- 広告主とアフィリエイター双方の責任範囲を認識
- 適切なPR表記と透明性のある情報発信を徹底
- 実効性のある管理体制とモニタリングシステムを構築
- 公的ガイドラインを参照し、業界の最新動向に注意
これらの点に注意を払いながらアフィリエイト広告運用を行うことで、法的リスクを回避しつつ、消費者からの信頼を獲得し、持続可能なマーケティング戦略を実現することができます。
法令に準拠した広告運用は、短期的には手間やコストがかかるように感じるかもしれません。しかし、長期的に見れば、消費者からの信頼獲得、ブランド価値の向上、そして安定した事業成長につながる重要な投資となります。
今後のアフィリエイト広告運用に、この記事で学んだ内容をぜひ活用してください。適正な広告表現と責任の明確化が、消費者と企業の双方にとって健全なデジタルマーケティング環境を構築する基盤となります。
ステマ規制を単なる制約ではなく、業界全体の信頼性向上のためのチャンスと捉え、積極的な対応を心がけていきましょう。