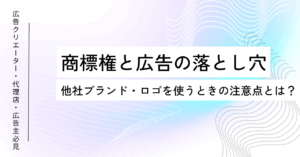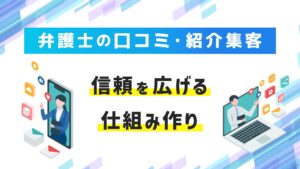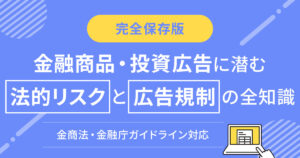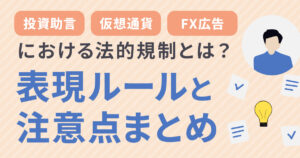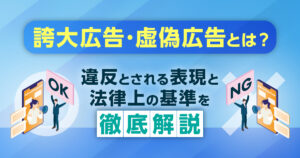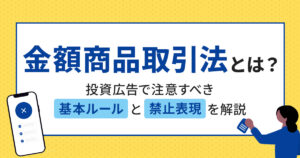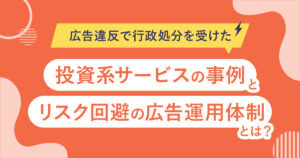「このInstagramの投稿、すごく良い写真だから広告に使わせてもらおう」
など、軽い気持ちでユーザーのSNS投稿を広告に流用していませんか?
近年、マーケティング業界でUGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用が急速に注目を集めています。
企業の作った広告よりも信頼性が高く、CVR向上に大きな効果があることから、多くの企業がユーザーの投稿を積極的に活用し始めているのです。
しかし、そこには大きな落とし穴が潜んでいます。ユーザーが投稿したSNSの写真や動画には著作権があり、無断で商用利用すれば著作権侵害となる可能性があるのです。
さらに人物が写っている場合は肖像権、有名人の場合はパブリシティ権の問題も発生します。
「効果的だから」「みんなやっているから」という理由で安易にUGCを流用すると、法的トラブルや企業の信頼失墜といった深刻な結果を招くおそれがあります。
この記事では、UGCを広告に活用する際に知っておくべき著作権・肖像権・パブリシティ権の基礎知識から、実際に起こりうるトラブル事例、そして安全にUGCを活用するための具体的な方法まで、広告担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
リスクを恐れてUGC活用を諦めるのではなく、正しい知識を身につけて安全で効果的なマーケティング施策を実現していきましょう。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは?広告との関係性を解説
デジタルマーケティングの世界で注目を集める「UGC(User Generated Content)」は、企業ではなく一般ユーザーが作成したコンテンツのことを指します。
SNSの普及によって、誰もが簡単に情報発信できる時代となり、今後もUGCの重要性は高まっていくと予想されます。
UGCの基本概念から広告活用の意義、具体的な活用シーンまでを詳しく解説していきましょう。
UGCの定義と種類(SNS投稿・口コミ・写真など)
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは、企業や専門家ではなく、一般ユーザーや消費者が作成したあらゆるコンテンツのことです。
日本語では「ユーザー生成コンテンツ」や「消費者作成コンテンツ」とも呼ばれ、ブランドやサービスに関連して自発的に作られた投稿を指すのが一般的となっています。
UGCの種類は多岐にわたり、主に以下のようなものがあります。
- SNS投稿
-
InstagramやX(旧Twitter)、TikTok、Facebookなどへの投稿が代表的です。商品の写真や動画、使用レビュー、日常での利用シーンなどが含まれます。
特にハッシュタグを用いた投稿は、企業やブランドにとって貴重なUGCとなることが多いでしょう。
- カスタマーレビュー・口コミ
-
ECサイトやGoogle、食べログなどのレビューサイトに投稿される評価・感想です。
星評価だけでなく、テキストや写真を含む詳細なレビューは、購入検討者にとって重要な判断材料となります。企業にとっても商品改善の貴重なフィードバックソースとなるでしょう。
- 写真・動画コンテンツ
-
ユーザーが撮影した商品や体験に関する写真・動画です。InstagramやTikTokでの投稿だけでなく、YouTubeでの製品レビュー動画なども含まれます。
特に「開封の儀」や「使ってみた」系の動画は高い注目を集めることがあります。
- ブログ・記事
-
個人ブログや note などでユーザーが執筆する商品レビューや体験談です。専門家や一般消費者の視点からの詳細な分析が含まれることもあります。
- Q&A・フォーラム投稿
-
Yahoo!知恵袋などの質問サイト、各種掲示板での商品やサービスに関する質問・回答も重要なUGCです。実際の利用者からの生の声が集まる場となっています。
これらのUGCは、単なる消費者の声にとどまらず、マーケティング資産として大きな価値を持っています。しかし、その活用には著作権をはじめとする様々な権利関係への配慮が不可欠です。
広告にUGCを活用するメリット
企業がマーケティング活動においてUGCを活用する理由は多岐にわたりますが、最も重要なのは「共感性」と「信頼性」の獲得です。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 高い信頼性の獲得
-
消費者は企業の自社宣伝よりも、実際のユーザーの声を信頼する傾向があります。
2023年の調査によると、消費者の約77%が他のユーザーのレビューを参考に購入を決定するという結果が出ています。
- 共感を生み出す親近感
-
プロが作成した完璧な広告写真よりも、実際のユーザーが日常生活で撮影した写真の方が、多くの消費者に共感を生み出します。「自分と同じような人が使っている」という親近感は、商品への心理的距離を縮める効果があるでしょう。
- 多様な使用シーンの提示
-
企業が想定していなかった商品の使い方や活用法が、UGCを通じて発見されることもあります。
さまざまなユーザーの創意工夫は、新たな商品価値の発掘につながることがあるでしょう。これは商品開発のヒントにもなります。
- コスト効率の良いコンテンツ獲得
-
質の高いプロモーション素材を企業が自ら制作するには多額のコストがかかりますが、UGCは基本的にユーザーが自発的に作成したものです。
適切な許諾を得た上で活用することで、効率的にコンテンツを獲得できます。ただし、権利処理の手間やリスク管理は別途必要となります。
こうした様々なメリットから、UGCはマーケティング戦略において重要な位置を占めるようになっています。ただし、活用には著作権や肖像権などへの十分な配慮が必要です。
活用シーンの例(バナー・SNS・LPなど)
UGCは様々なマーケティングチャネルで活用できます。効果的な活用シーンとその特徴を見ていきましょう。
- SNS公式アカウントでの再投稿(リポスト)
-
最も一般的なUGC活用法の一つが、ユーザーの投稿を企業の公式SNSアカウントで再投稿することです。Instagramのリポスト機能やXのリツイート機能を使えば、出典を明示しながら簡単に共有できます。
- Web広告のビジュアル素材
-
ユーザーが撮影した商品写真や使用動画は、バナー広告やディスプレイ広告、動画広告の素材として活用できます。
プロが撮影した完璧な写真よりも、実際のユーザーが日常で撮影した写真の方がクリック率が高くなるケースもあります。ただし、広告利用の場合は明確な使用許諾が必要です。
- ECサイト・商品ページへの掲載
-
商品詳細ページにユーザーレビューや使用写真を掲載することで、購入検討者の不安を軽減し、コンバージョン率向上につながります。
「着用イメージ」や「使用例」としてユーザー投稿を活用するECサイトが増えています。
- ユーザー参加型キャンペーンの展開
-
「〇〇ハッシュタグキャンペーン」など、ユーザーの投稿を促すキャンペーンを実施し、集まったUGCを様々な媒体で活用する総合的なアプローチも効果的です。
あらかじめキャンペーン応募規約で二次利用の許諾を得ておくことで、効率的にコンテンツを収集できます。
このように、UGCは様々な接点で活用できますが、いずれの場合も適切な権利処理と、プラットフォームごとの規約・ポリシーへの準拠が前提となります。
著作権・肖像権・パブリシティ権の違い
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を広告に活用する際には、様々な権利関係に配慮する必要があります。特に著作権・肖像権・パブリシティ権は、明確に区別して理解しておくことが重要です。
ここでは、各権利の基本的な概念と法的根拠、UGC活用における注意点について解説します。
著作権:創作物の保護に関する権利
著作権とは、創作物を保護するための権利であり、著作権法に基づいて規定されています。著作権は、創作的な表現物が創作された時点で自動的に発生し、特に登録などの手続きは必要ありません。
- 著作権の対象となるもの
-
- 文章(SNS投稿、ブログ記事など)
- 写真・イラスト・動画
- 音楽・音声
- プログラムコード
- その他の創作的表現物
- 著作権の主な権利内容
-
著作者人格権
著作者の人格的利益を保護する権利- 公表権:作品を公表するかどうかを決定する権利
- 氏名表示権:作品に著作者名を表示するかどうかを決定する権利
- 同一性保持権:作品の内容や形式を勝手に改変されない権利
著作財産権
著作物の利用によって生じる経済的利益を保護する権利- 複製権:著作物を複製する権利
- 公衆送信権:著作物をインターネット等で送信する権利
- 翻案権:著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化する権利
- 二次的著作物の利用に関する権利:翻案によって生じた二次的著作物を利用する権利
- UGC活用における著作権の注意点
-
- SNSに投稿された写真や文章を広告に流用する場合、原則として著作権者(投稿者)の許諾が必要です。
- SNSに投稿された写真や文章の著作権は投稿者に帰属します。ユーザー投稿を商用利用する場合、プラットフォームの規約では許諾されていないため、必ず投稿者本人から明示的に使用許諾を得る必要があります。
- 引用として使用する場合でも、「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」である必要があります。
- 著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年間(団体名義の著作物は公表後70年間)となっています。
「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。他人がその著作物を利用したいといってきたときは、権利が制限されているいくつかの場合を除き、条件をつけて利用を許可したり、利用を拒否したりできます。
引用:著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
肖像権:個人の顔・姿の無断使用を制限
肖像権とは、自分の容姿・姿態を撮影されたり、それを公表されたりすることを拒否できる権利です。憲法13条の幸福追求権に基づく人格権の一つとされており、肖像権侵害に関する判例も蓄積されています。
- 肖像権の保護対象
-
- 個人の顔や姿が写った写真・動画
- 似顔絵やイラストなどで特定の個人を描写したもの
- 個人を特定できる身体的特徴
- 肖像権侵害の判断基準
-
- 撮影・掲載の目的(公共性・社会性があるか)
- 撮影・掲載の必要性(その手段が相当か)
- 被撮影者の社会的地位(公人か私人か)
- 撮影方法・場所(プライバシー侵害の度合い)
- 掲載による不利益の程度
- UGC活用における肖像権の注意点
-
- SNSに投稿された他者の写り込んだ写真を広告に使用する場合、写っている人全員の同意が必要です。
- 投稿者本人が撮影した自分の写真(セルフィー)でも、商用利用する場合は改めて許諾を得るべきです。
- 人混みや公共の場で撮影された写真でも、特定の個人が識別できる形で使用する場合は注意が必要です。
- 未成年者の写真を使用する場合は、本人だけでなく保護者の同意も必要となります。
肖像権とは、勝手に写真に撮(と)られたり、撮られた写真を勝手に公開されない権利です。わたしたち全員が持つ大切な権利の一つです。
テレビや雑誌(ざっし)などでタレントやアーティスト、スポーツ選手などがコマーシャルに使われているのを見たことがあるでしょう。このような有名人が、名前や顔写真などを勝手に使われない権利も、肖像権に当たります。
引用:インターネットの安心安全な使い方:著作権・しょうぞう権って何?
パブリシティ権:有名人の顔・名前を守る権利
パブリシティ権とは、芸能人やスポーツ選手などの有名人が持つ、自分の氏名・肖像等を商業的に利用して経済的利益を得る権利です。
- パブリシティ権の保護対象
-
パブリシティ権は、有名人の氏名や肖像だけでなく、声や特徴的なフレーズ、ポーズなど、その有名人を連想させる要素全般を保護対象としています。
- パブリシティ権侵害の判断基準
-
裁判所は主に、有名人の氏名・肖像等を商品の宣伝に利用しているか、商品と明確に結びつけているか、また商品等の差別化を図る目的で利用しているかという点を判断基準としています。
これらの要素が該当する場合、パブリシティ権侵害と認められる可能性が高くなります。
- UGC活用におけるパブリシティ権の注意点
-
UGCを広告に活用する際は、有名人とのツーショット写真やイベント写真の使用には特に注意が必要です。有名人本人がSNSに投稿した内容であっても、商業利用には許諾が必要となります。
許諾を得る際は、タレントのマネージメント事務所や所属スポーツチームなどの正規ルートを通じて手続きを行うことが重要です。無断使用は高額な損害賠償請求につながるリスクがあります。
その他関連する権利(商標・意匠・プライバシーなど)
UGC活用の際には、上記の権利以外にも考慮すべき権利があります。
- 商標権
-
商標権は、特定の商品・サービスに使用されるマーク(ロゴ、名称など)を保護する権利です。商標法に基づき、登録することで発生します。
- UGCに他社の商標が写り込んでいる場合、それを広告利用すると商標権侵害となる可能性があります。
- 特に競合他社の製品が写り込んだUGCの利用には注意が必要です。
- 商標の使用が「商標的使用」に当たるかどうかが判断基準となります。
- 意匠権
-
意匠権は、物品のデザインを保護する権利で、意匠法に基づき登録することで発生します。
- 特徴的なデザインの商品が写り込んだUGCを使用する際は、その商品の意匠権に注意が必要です。
- インテリアや建築物のデザインも意匠権の対象となる場合があります。
- プライバシー権
-
プライバシー権は、私生活上の事実や情報を公開されない権利で、憲法13条に基づく人格権の一つです。
- 個人の生活状況や私的情報が含まれるUGCの利用は、プライバシー侵害となる可能性があります。
- 位置情報や訪問先などの情報も、プライバシーに関わる情報として注意が必要です。
- 特に医療情報や家族構成など、センシティブな情報には配慮すべきです。
UGCを広告に活用する際には、これらの権利について十分に理解し、必要な許諾を得た上で利用することが重要です。
法的リスクを避けるためには、権利処理のプロセスを明確にし、社内ガイドラインを整備しておくことをお勧めします。
SNS投稿を広告に流用する際のリスク
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を広告に活用することのメリットは大きいものの、適切な手続きを踏まないと様々なトラブルを招くリスクがあります。
SNS投稿を広告に流用する際に発生する可能性のあるトラブルについて解説します。
無断使用による削除要請・炎上のリスク
SNS上の投稿を投稿者の許諾なく広告に使用した場合、最も起こりやすいトラブルが削除要請や炎上です。
権利者からの指摘を受けて広告を急遽取り下げることになれば、広告効果が得られないだけでなく、追加コストや機会損失につながります。
- 削除要請のプロセス
-
投稿者が自分の写真や文章が無断で使われていることに気づくと、通常は次のような行動を取ります。
- 企業に対して直接削除を求める連絡
- SNSプラットフォームへの著作権侵害報告
- 法的手段(弁護士を通じた警告書の送付など)
特に影響力のある投稿者の場合、自身のSNSで企業の無断使用を批判する投稿をすることで、炎上に発展するケースも考えられます。
- 一般的な炎上例
-
アパレルや飲食業界などでは、ハッシュタグで集めた一般ユーザーの写真を許諾を得ずにマーケティング素材として使用し、該当ユーザーがSNSで抗議するケースが起こりえます。
- 予防策
-
- 明確な許諾取得プロセスの確立
- UGC利用規約の整備とユーザーへの周知
- キャンペーンハッシュタグを使用する際の利用条件の明示
- 社内におけるUGC活用ガイドラインの作成と運用
DMでの許諾トラブル(誤解・伝達ミス)
SNSのダイレクトメッセージ(DM)で許諾を得たつもりでも、コミュニケーション不足や誤解によりトラブルが発生するケースが少なくありません。
- DMでの許諾取得の問題点
-
- 口頭(文字)のみの約束となり、後から条件について争いが生じやすい
- 使用範囲や期間、媒体について詳細な合意がなされないことが多い
- DMのやりとりが消えてしまうプラットフォームもある
- 担当者の交代により合意内容が社内で共有されないリスク
- 典型的なトラブル例
-
企業がSNSユーザーとDMでやりとりし、「SNSでの紹介に使わせていただきます」という許諾を得たものの、実際にはSNS広告だけでなく、店頭POPや雑誌広告にも展開してしまうケースが考えられます。
このような場合、投稿者が「SNSだけの使用と思っていた」と主張し、追加報酬を要求したり、使用の差し止めを求めたりするトラブルに発展する可能性があります。
- 予防策
-
- DMで初期コンタクトした後、正式な許諾書や利用同意書を交わす
- 使用目的、媒体、期間、地域、報酬の有無を明確に記載する
- やりとりの記録を保存する習慣づけ
- 重要な合意事項は必ずメールなど記録に残る方法で確認する
企業の信頼失墜・法的措置のリスク
UGCの不適切な使用は、単なる削除要請にとどまらず、企業の信頼失墜や法的措置につながる可能性があります。
- 企業信頼失墜のリスク
-
消費者のSNS投稿を許可なく広告に使用し、さらにその投稿の一部を切り取って本来の文脈と異なる印象を与える編集を行った場合、「意図を歪めて使用された」として批判を受ける可能性があります。
こうした批判がSNS上で拡散されると、企業は公式謝罪やキャンペーン中止などの対応を迫られる可能性があるでしょう。
- 法的措置のリスク
-
個人の投稿した写真や文章を、クレジット表記なしで広告に使用した場合、著作権侵害として訴訟リスクがあります。このような場合、裁判所から損害賠償や謝罪広告の掲載を命じられる可能性があります。
- 企業が受けうる法的措置
-
- 著作権侵害に基づく差止請求と損害賠償請求
- 肖像権・プライバシー侵害に基づく損害賠償請求
- パブリシティ権侵害に基づく損害賠償請求
- 景品表示法違反による行政処分(誤認させる表示の場合)
- 予防策
-
- 法務部門を含めた社内承認フローの確立
- UGCの権利処理に関する社員教育の実施
- 権利処理の専門家やエージェンシーとの連携
- 許諾取得プロセスの文書化と厳格な運用
SNSプラットフォームのポリシー違反による削除
各SNSプラットフォームには独自の利用規約やコミュニティガイドラインがあり、これに違反したUGC活用は投稿や広告アカウント自体が削除されるリスクがあります。
- 主要SNSのポリシー概要
-
- Instagram
他者のコンテンツを自分のものとして表示することを禁止。リポストの場合も適切なクレジット表記が必要。 - Twitter(X)
他者のコンテンツを許可なく使用することを禁止。また、誤解を招く方法でのコンテンツの提示も規約違反。 - Facebook
権利侵害コンテンツの投稿を禁止。広告においてはさらに厳格な審査基準あり。 - TikTok:知的財産権を侵害するコンテンツの投稿を禁止。特に音楽や振付などの著作物に関して厳格。
- Instagram
- 一般的な削除リスク事例
-
企業がSNSで実施したキャンペーンで、ユーザーの投稿をハッシュタグで集め、優秀作品を公式アカウントでリポストする際、適切なクレジット表記する必要があります。
あたかも自社で制作したかのように見える投稿方法を取った場合、プラットフォームから投稿削除や一時的なアカウント制限といった措置を受ける可能性があります。
- プラットフォーム違反のリスク
-
該当投稿の削除や広告アカウントの一時停止、最悪の場合は企業アカウントが永久凍結されることもあるでしょう。
- 予防策
-
- 各プラットフォームの最新のポリシーを定期的に確認
- UGC活用前にプラットフォーム固有のガイドラインに照らしたチェック
- 適切なクレジット表記と出典の明示
- プラットフォームによるコンテンツ削除に備えたバックアップ体制
UGCを広告に活用する際は、これらのリスクを十分に理解し、適切な権利処理と運用ルールを確立することが重要です。
法的リスクの回避だけでなく、ユーザーとの信頼関係構築という観点からも、誠実なUGC活用を心がけましょう。
UGCを広告に使う際の確認事項
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を広告に活用する際には、様々な権利関係や規約に配慮する必要があります。
以下では、リスクを最小化するために確認すべき重要な確認事項について解説します。
使用許諾の有無(書面やDMでの明示確認)
UGCを広告に活用する際の最も基本的な確認事項は、投稿者からの明確な使用許諾を得ているかどうかです。
- 使用許諾取得の方法
-
正式な許諾書による取得が最も確実です。使用目的、使用媒体、使用期間、地域、報酬の有無などを明記し、双方が保管する形が望ましいでしょう。
SNSのDMやメールでの許諾取得も可能ですが、この場合も使用条件を具体的に明示し、相手の承諾を得ることが重要です。やりとりの記録は必ず保存しておきましょう。
- 許諾取得時のリスク
-
- 投稿者からの削除要請や損害賠償請求
- SNSプラットフォームからの投稿削除
- 広告素材としての使用中止による損失
- 企業イメージの低下
- 適切な対応方法
-
「宣伝に使わせていただきます」といった抽象的な表現は避け、「Webサイト、SNS広告、店頭POPでの使用」など具体的に記載しましょう。
未成年者の投稿を使用する場合は、保護者の同意も必要です。また、第三者(写り込んでいる人など)の権利処理も考慮する必要があります。
引用の範囲に該当しているか?商用利用か?
UGCを無断で使用できる可能性として「引用」が挙げられますが、商用広告での使用が「引用」として認められるケースは極めて限定的です。
- 引用と認められる条件
-
著作権法第32条では、以下の条件を満たす場合に「引用」として著作物の利用が認められています。
- 既に公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致していること
- 「引用の目的上正当な範囲内」であること
- 出所の明示がなされていること
- 引用部分と自己の著作物との主従関係が明確であること
- 商用利用における引用のリスク
-
広告目的でのUGC利用は以下の理由から「引用」として認められにくいため、リスクが高いと言えます。
- 商業目的の利用は「引用の目的上正当な範囲内」と認められにくい
- 広告ではUGCが主体となることが多く、主従関係が成立しない
- 単なる賞賛や宣伝のための利用は「批評」などに該当しない
企業のWebサイトやSNSアカウントでの掲載、広告・商品パッケージへの使用、販促物への使用などは「商用利用」と判断される可能性が高く、原則として許諾が必要です。
社内研修資料での使用などは「非商用」に近いと考えられますが、安全を期すなら許諾を得るべきでしょう。
肖像・著作物を含む投稿の利用可否
UGCに写り込んでいる人物や他の著作物についても、権利処理が必要かどうか確認する必要があります。投稿を広告利用する際は、写っている人物や著作物によって異なる対応が求められます。
- 人物が写っている場合の考慮点
-
投稿者本人のみが写っている場合は、投稿者の許諾があれば基本的には使用可能です。ただし、当初の投稿意図と大きく異なる文脈での使用は肖像権・プライバシー侵害となる可能性があるため注意が必要です。
投稿者以外の人物が写っている場合は、より慎重な対応が求められます。
- 原則として写っているすべての人の許諾が必要
- 公共の場での群衆として写っている場合など、例外となるケースもある
- 許諾なしでの使用は肖像権侵害の訴訟リスクがある
有名人が写っている投稿を使用する際には、パブリシティ権に配慮する必要があります。
有名人の氏名や肖像には経済的価値があり、無断使用は権利侵害となるため、通常は所属事務所を通じた正式な手続きが必要です。
また、未成年者が写っている場合は、本人の同意だけでなく親権者の同意も必須となります。
- 他の著作物が写り込んでいる場合の対応
-
著作権法第30条の2では、「付随対象著作物」の写り込みについて一定の許容がありますが、判断基準を理解することが重要です。
- その著作物が「主たる被写体」なのか「付随的」なのかが重要な判断ポイント
- 権利者の利益を不当に害さないことも条件
著作物の種類によっても対応が異なります。テレビ番組や映画の一部が写り込んでいる場合は原則として許諾が必要ですが、画面の小さな一部として偶然写り込んでいる程度なら「付随対象著作物」として問題ないケースもあります。
音楽は権利関係が複雑で、BGMとして流れている音楽でも権利処理が必要になることがあります。
商標・ブランドロゴの使用可否
UGCに他社の商標やブランドロゴが写り込んでいる場合、商標権侵害に当たるかどうかの確認が重要です。商標法上の侵害は「商標的使用」に該当するかどうかがポイントとなります。
- 商標利用の判断基準
-
商標の写り込みが単に背景として偶然映っている程度であれば、通常は「商標的使用」には当たらず問題ないケースが多いです。
しかし、他社のロゴや商標を自社商品と関連付けて使用する場合は注意が必要です。
- 競合他社の商標・ロゴの場合
-
- 競合製品の批判や比較に見える使い方は避けるべき
- 業界内での不必要な対立を生む可能性がある
また、ブランドイメージへの影響も考慮すべき重要な要素です。高級ブランドのロゴが映ったUGCを低価格商品の広告に使用すると、そのブランドイメージを毀損する可能性があります。
こうした使用は商標権侵害だけでなく、不正競争防止法違反となるケースもあります。
- 適切な対応方法
-
商標やブランドロゴの写り込みが問題になる可能性がある場合は、以下のような対応策があります。
- 問題となる部分にモザイク処理を施す
- より安全な別のUGCを選択する
- 状況によっては、該当するブランドに直接許諾を得る
これらの対応により、商標関連のリスクを最小限に抑えることができます。
利用規約・プライバシーポリシーの確認
UGCを収集・利用する際には、各SNSプラットフォームの利用規約やプライバシーポリシーを確認することも重要です。プラットフォームごとに異なるルールを理解し、遵守することが求められます。
- プラットフォームのルールと対応
-
各プラットフォームには、コンテンツ利用に関する独自のルールがあります。
- Instagram:他者のコンテンツを共有する際の適切なクレジット表記が必要
- Twitter(X):他者のコンテンツの無断使用や誤解を招く提示方法は規約違反
- Facebook:広告においては特に厳格な審査基準がある
- TikTok:音楽や振付などの著作物に関して特に厳格なルールがある
これらのルールに違反すると、投稿の削除要請や企業アカウントの一時停止、広告配信の制限などの措置を受ける可能性があります。
- プライバシー保護の観点
-
UGC活用においては、プライバシー保護も重要な考慮点です。位置情報が含まれる投稿を使用する場合は個人特定リスクに注意し、健康状態や政治的見解などのセンシティブな個人情報が含まれる投稿は避けるべきです。
- 効果的な運用のために
-
安全にUGCを活用するためには、以下のような対策が効果的です。
- 定期的に各プラットフォームの最新の利用規約を確認する
- 不明点があれば、プラットフォームの問い合わせ窓口に確認する
- 社内での規約情報共有体制を確立する
- プラットフォーム別のルールをまとめたチェックリストを活用する
UGCを広告に活用する際は、これらの確認実行を総合的に確認することで、リスクを管理しながら効果的な活用が可能になります。
適切な権利処理と運用ルールを確立し、ユーザーとの信頼関係構築を大切にしたUGC活用を目指しましょう。
トラブルが起きた際の対応方法と相談先
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を広告に活用する際、どれだけ慎重に準備しても、予期せぬトラブルが発生する可能性は常にあります。
トラブルが生じた場合の迅速かつ適切な対応は、被害の拡大を防ぎ、企業の信頼回復につながるでしょう。
クレーム対応の初動と企業としての謝罪対応
UGC活用に関するクレームが発生した場合、初動対応の適切さがその後の展開を大きく左右します。迅速かつ誠実な対応で、問題の早期解決と企業イメージの維持を図りましょう。
- 初動対応の基本ステップ
-
クレームへの対応は、まず情報収集と事実確認から始めます。確認すべきポイントは以下の通りです。
- クレーム発信者の属性(投稿者本人か、写り込んでいる第三者か)
- 問題となっているコンテンツの詳細と使用状況
- 使用許諾の有無や範囲
- 社内での決裁・確認プロセスの履歴
事実関係が明確になったら、マーケティング、法務、広報など関連部署で情報を共有し、対応方針を決定します。
まずはクレーム発信者への連絡と謝意を表明し、調査中であることを伝えます。状況によっては、一時的にコンテンツを削除したり広告出稿を停止したりする必要もあるでしょう。
- 謝罪対応のポイント
-
適切な謝罪は、問題の早期解決と信頼回復に不可欠です。誠実さと透明性を確保し、事実を隠したり責任を転嫁したりせず、誠実に対応することが重要です。
問題の規模や影響に応じて、適切な謝罪方法を選ぶことも大切です。
- 個別のクレームの場合:直接連絡による謝罪
- SNSで拡散している場合:公式アカウントでの謝罪文掲載
- 大規模な問題の場合:プレスリリースやWebサイトでの謝罪文掲載
単なる謝罪だけでなく、具体的な対応策と再発防止策を示すことで誠意を伝えることができます。
該当コンテンツの削除や修正、必要に応じた金銭的補償や代替措置の提案、社内ルールやチェック体制の見直しなど、具体的な行動を示すことが信頼回復につながります。
法的措置に備えた弁護士への相談
UGC活用におけるトラブルが深刻化し、法的措置に発展する可能性がある場合は、早期に弁護士に相談することが重要です。
適切なタイミングで専門家の助言を得ることで、リスクを最小限に抑えることができます。
- 弁護士への相談が必要なケース
-
以下のようなケースでは、弁護士への相談を検討すべきでしょう。
- 権利者から警告書や内容証明が届いた場合
- 高額な損害賠償請求を受けた場合
- 著作権法違反など刑事罰の対象となる行為について告訴の可能性が示唆された場合
- 複数の権利者から同時に指摘を受けるなど問題が複雑化した場合
- 海外の権利者やプラットフォームが関係するケース
これらの状況では、専門的な法的アドバイスが必要となります。警告書を受領した段階で弁護士に相談することで、適切な対応策を講じ、問題の拡大を防止できます。
- 弁護士選定のポイント
-
UGC活用に関するトラブルに対応するには、適切な専門性を持つ弁護士を選定することが望ましいです。
- 知的財産権(特に著作権)に強い弁護士
- SNSやデジタルプラットフォームに関連する法的問題に対応した経験のある弁護士
- 広告やマーケティングの法的側面に詳しいエンターテインメント法に精通した弁護士
これらの専門性を持つ弁護士は、UGC特有の法的課題に対して適切なアドバイスを提供できます。
- 弁護士との効果的な連携方法
-
弁護士に相談する際は、効果的な連携のために関連資料の整理と提供し有利不利にかかわらず事実関係を正確に説明することが重要です。
企業としての方針や優先事項を明確にし、特に予防法務としての弁護士相談はトラブルを未然に防ぐ上で非常に効果的です。
消費者庁・プラットフォームへの連絡
UGC活用に関するトラブルの中には、消費者庁や各SNSプラットフォームへの報告や相談が必要なケースもあります。適切な機関への適時の連絡は、問題の早期解決や二次被害の防止につながります。
- 消費者庁への連絡が必要なケース
-
以下のようなケースでは、消費者庁への連絡や報告を検討すべきです。
- UGCを活用した広告が景品表示法に関わる問題を含む場合(ステルスマーケティング等)
- 特定のUGC活用キャンペーンに対して消費者から大量の苦情が寄せられた場合
- UGC活用における法解釈やガイドラインの明確化が必要な場合
景品表示法違反となり得る「優良誤認」や「有利誤認」に該当する可能性がある場合は、自主的な報告や相談が望ましいでしょう。
また、業界全体に影響する問題については、消費者庁に相談することで適切な方向性を示してもらえる可能性があります。
- 消費者庁への連絡方法と対応のポイント
-
消費者庁には企業からの相談を受け付ける窓口があります。
相談の際は、問題の概要、発生原因、現在の対応状況、今後の対応方針などを整理し、簡潔に報告できるよう準備することが重要です。
また、問題解決に向けた自主的な改善策を検討し提示することで、行政指導や措置命令などの強制的な対応を回避できる可能性が高まります。
消費者庁 表示対策課 情報管理担当
電話:03-3507-8800(代表)
引用:景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口 | 消費者庁
(平日9:30~18:15。ただし、12:00~13:00を除く。)
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 7階 - SNSプラットフォームへの連絡が必要なケース
-
以下のようなケースでは、関連するSNSプラットフォームへの連絡が重要です。
- UGC活用方法がプラットフォームの利用規約やガイドラインに違反している可能性がある場合
- 権利侵害などの理由で特定の投稿の削除や修正が必要な場合
- なりすましやフェイクアカウントの問題がある場合
- API利用やプラットフォームの機能に関連する技術的な問題が発生した場合
これらの問題はプラットフォーム側のサポートを受けることで効果的に解決できる場合が多いです。
- プラットフォームへの連絡方法と対応のポイント
-
各プラットフォームには目的別の連絡窓口があります。効果的な連絡のためには以下が重要です。
- 状況に応じた適切な窓口を特定する(企業アカウント向けサポート、権利侵害報告フォームなど)
- 問題の内容、関連URL、アカウント情報などを具体的かつ簡潔に説明する
- 可能であれば企業認証されたアカウントから連絡する
- 状況の変化や追加情報があれば継続的に連絡し、問題解決まで粘り強くフォローアップする
適切な窓口への的確な情報提供により、プラットフォーム側の迅速な対応を促すことができます。
UGC活用におけるトラブルへの対応は、初動の迅速さと適切な専門家への相談が鍵となります。
社内での対応体制を整え、弁護士や関係機関との連携を強化することで、万が一のトラブル発生時にも適切に対応できるよう準備しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
ここでは、UGCと著作権問題に関するよくある質問を紹介します。
投稿者が許可したら商用利用しても問題ない?
投稿者の許可は必要ですが、それだけでは不十分な場合があります。
投稿者からの許可に加えて確認すべき点:
- 投稿に他の人物が写っている場合、その人の肖像権の許諾も必要
- 有名人が写っている場合はパブリシティ権の問題も考慮
- 背景に著作物が写り込んでいる場合、その権利者の許諾が必要な場合も
許諾取得時のポイントとしては、使用媒体、期間、地域、加工の可否を明確にします。
加えて、SNSプラットフォームの利用規約も確認するようにしましょう。
引用であれば著作権侵害にならない?
広告などの商用目的では「引用」として認められるケースは非常に限られます。
広告利用では以下の理由から「引用」として認められない可能性が高いです。
- 広告目的は「批評」や「研究」に当たらない
- 広告ではUGCが主体となりやすく、主従関係が成立しない
- 商用利用は「公正な慣行」に合致しないと判断される可能性が高い
商用利用の場合は「引用」に頼らず、明示的な許諾を得ることを推奨します。
まとめ|UGC広告活用にはルールと配慮が不可欠
本記事では、SNS投稿を広告に流用する際の著作権問題や肖像権・パブリシティ権の違い、起こりうるトラブル、確認事項、そして対応策について詳しく解説してきました。
UGCを広告に活用することは、消費者の共感を得て信頼性を高める効果的な手法ですが、他者の権利を尊重する姿勢が不可欠です。
権利侵害は法的リスクだけでなく、企業の信頼性や社会的評価を大きく損なう問題となります。
UGC広告活用における重要ポイントを以下にまとめます。
- 著作権・肖像権・パブリシティ権の違いを正しく理解
- 投稿者だけでなく写り込んでいる第三者の権利も考慮
- 「投稿者の許可」や「引用」の範囲と限界を理解
- 使用目的・媒体・期間を明確にした許諾取得
- SNSプラットフォームの利用規約にも配慮
- トラブル発生時の対応体制を構築
一見すると、これらの権利処理はマーケティング活動の制約や追加コストになるように思えるかもしれません。しかし、適切な権利処理は法的リスクを回避するだけでなく、ユーザーの権利を尊重する企業姿勢を示すことにもつながります。
「効果的なUGC活用」と「適正な権利処理」は決して相反するものではなく、むしろ持続可能なマーケティング活動のために必要不可欠な要素です。
権利処理を適切に行うことで、ユーザーとの信頼関係が構築され、より多くの良質なUGCが生まれる好循環を生み出すことができます。