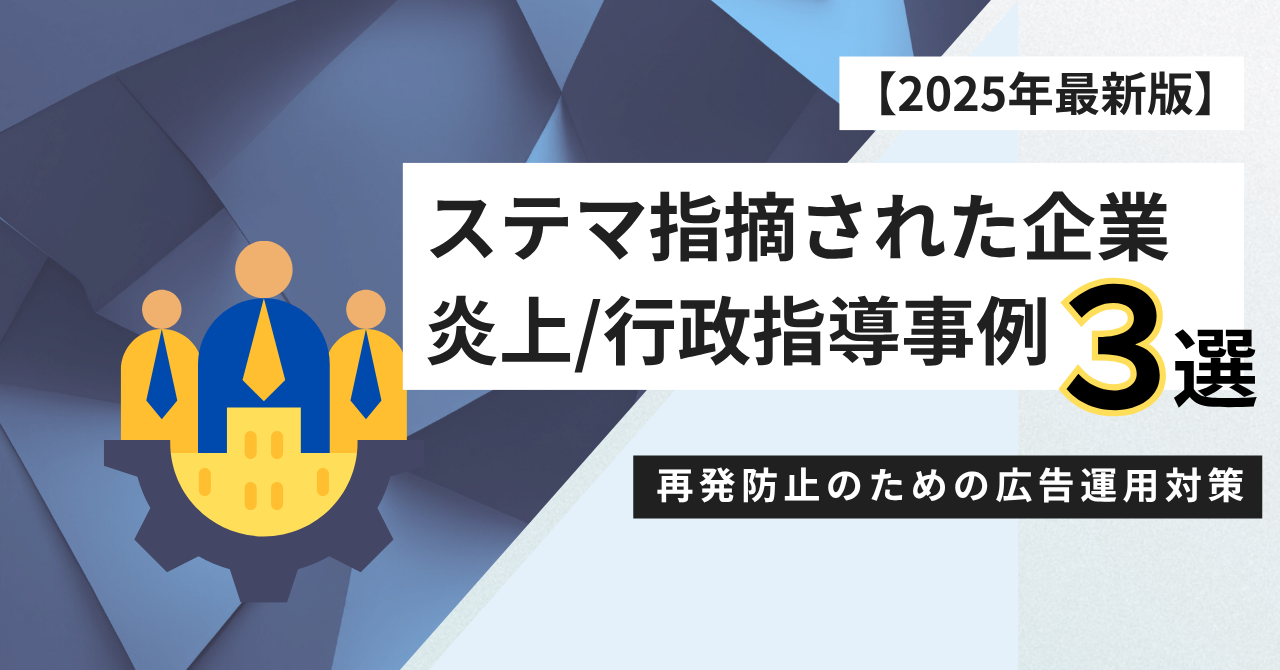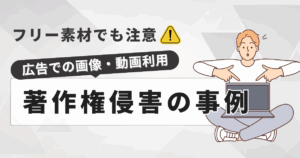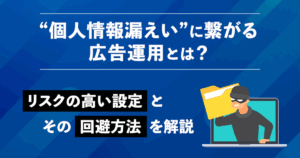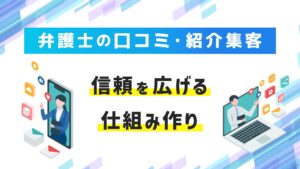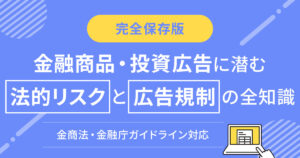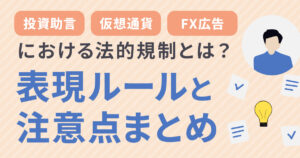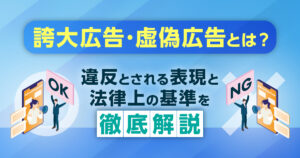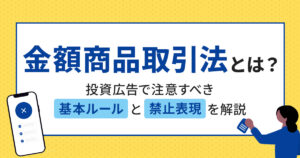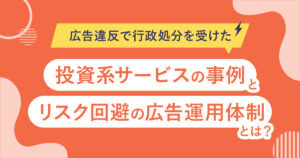SNSや口コミサイト、アフィリエイトを活用したプロモーションが当たり前となった今、企業が「ステルスマーケティング(ステマ)」と指摘され、炎上や行政指導を受けるケースが増えています。
自社では正しく運用しているつもりでも、PR表記の不備やインフルエンサーの投稿内容など、ちょっとした見落としがステマと判断され、信頼の失墜や売上への悪影響を招くことも。
とくに2023年10月からは、消費者庁により広告であることの明示が義務化され、違反には行政処分が下される時代となりました。
本記事では、実際に行政指導を受けた企業の事例やSNSで炎上した企業の失敗例を、信頼できる引用元をもとに紹介しながら、企業が講じるべき広告運用におけるステマ防止策をわかりやすく解説します。
「うちは大丈夫」と思っている方にこそ読んでいただきたい、広告担当者・広報・法務部門必見の内容です。
ステマとは?広告と認識されない宣伝のリスク
ステルスマーケティング、いわゆる「ステマ」とは、企業が宣伝であることを隠して商品やサービスを紹介するマーケティング手法です。近年では、SNSやブログ、動画投稿といったユーザー生成コンテンツの広がりにより、消費者が「自然な口コミ」や「中立なレビュー」と誤認しやすい状況が生まれています。
ステマと判断された場合、消費者の信頼を裏切ることになり、企業にとっては炎上によるイメージダウンや法的リスクが発生する恐れがあります。
また、2023年10月には、消費者庁が「ステマ行為」を景品表示法の規制対象に加えたことで、広告表示義務の法的ルールが明確化されました。
これは、インフルエンサーやアフィリエイターが企業から報酬を受け取って宣伝を行う際に、「#PR」や「広告」などの明示がされていないと違反となる可能性があるということを意味します。
ステマを避けるには、広告主や代理店だけでなく、投稿者自身にもルールを正しく伝え、運用体制を整えることが不可欠です。
この章では、まず「ステマ」の定義と具体的な問題点を明らかにし、さらに関連する法規制やガイドラインについて詳しく解説していきます。
ステルスマーケティングの定義と問題点
ステルスマーケティングとは、広告やプロモーションであることを隠して行う宣伝活動のことです。
たとえば、企業が自社商品を紹介するよう依頼したインフルエンサーが、報酬や提供品を受け取っていながら、それを明示せず「自発的なレビュー」として投稿した場合、これはステマに該当する可能性があります。
ステマの問題点は、消費者にとって「広告であると気づかずに情報を受け取る」ことにより、購買判断をミスリードされる恐れがあることです。企業にとっては、ステマが発覚した際に「消費者をだました」という印象を与えてしまい、炎上や不買運動につながるリスクもあります。
とくにSNSやYouTubeなど、一般ユーザーの信頼をベースにしたプラットフォームでは、透明性の欠如が強く批判されやすいため注意が必要です。
関係法令とガイドラインの整理
ステマに関連する法的な規制は、主に「景品表示法」に基づいています。
とくに2023年10月に施行された改正では、「広告であることを明確にしない表示」が不当表示として処罰対象となりました
これにより、企業から報酬を受け取っているインフルエンサーやアフィリエイターが、広告であることを明示せずに投稿した場合、企業側にも表示責任が生じるようになっています。
※広告主とアフィリエイターとの責任区分についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
消費者庁が公表している「ステルスマーケティングに関するQ&A」では、明示方法として「広告」「PR」「提供:〇〇株式会社」などの具体的な文言を提示しており、これらの表記が投稿の見出しや文頭に含まれている必要があるとされています。
また、SNSプラットフォーム各社(Instagram、X、YouTube等)でも、ステマ防止のための「PRタグ」や「広告表記ルール」が設けられており、広告主・代理店・投稿者すべてがこれらのルールに準拠する必要があります。
次章では、こうしたルールを破ったことでSNSで炎上した具体的な企業の事例を取り上げながら、どのような表現・体制が問題とされたのかを明らかにしていきます。
SNSで炎上した企業のステマ事例
行政処分には至らないまでも、企業がインフルエンサーやタレントを起用したプロモーションにおいて、PR表記の不備や情報の隠蔽と受け取られる投稿が原因でSNS上で炎上したケースも数多く存在します。
ステマと疑われた投稿が拡散されると、数時間で企業の評判は失墜し、謝罪、投稿削除、キャンペーン中止といった対応を余儀なくされる事態に発展することもあります。
ここでは、報道メディアにも掲載されている実際の炎上事例をもとに、何が問題だったのか、企業がどのように対応したのかを詳しく見ていきます。
ディズニー映画「アナと雪の女王2」の感想漫画投稿
2019年12月、ディズニー映画「アナと雪の女王2」の公開に合わせて、複数のクリエイターが感想漫画をTwitterに一斉投稿しました。
これらの投稿は、同じハッシュタグや投稿タイミングが重なり、不自然さから「ステマではないか」との疑念が広まりました。
実際、これらの投稿はディズニーからの依頼によるものでありながら、広告であることが明示されていませんでした
この件は、日本経済新聞などのメディアでも取り上げられており、
映画「アナと雪の女王2」を配給するウォルト・ディズニー・ジャパンは5日、PRと明記せずに、クリエーター7人に同映画の感想を漫画で表現してツイッターに投稿してもらっていたとして、ホームページで謝罪した。SNS(交流サイト)などで、宣伝を隠した「ステルスマーケティング(ステマ)」ではないかと批判の声が上がっていた。
ホームページによると、同社はクリエーターにPRであることを明記してもらう予定だったが、コミュニケーションが行き届かず、抜け落ちたと説明。「深く反省するとともに、再発防止策を講じていく」としている。〔共同〕
引用:日本経済新聞(「アナ雪2」PRで謝罪 ステマ批判にディズニー)
実際に、ウォルト・ディズニー・ジャパンは「PR表記が抜けていた」として次のような謝罪文を公表しました。
この度は、「『アナと雪の女王2』感想漫画企画」につきまして、ご参加いただきましたクリエイターのみなさま、ファンのみなさまに多大なご心配、ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。
引用:ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(「『アナと雪の女王2』感想漫画企画」に関するお詫び)
本企画は、クリエイター7名のみなさまに映画『アナと雪の女王2』をご覧いただき、ご感想を自由に表現いただいた漫画をTwitterに投稿いただく企画として実施したものです。
本企画に伴う投稿は、「PR」であることを明記していただくことを予定しておりましたが、関係者間でのコミュニケーションに行き届かない部分があり、当初の投稿において明記が抜け落ちる結果となってしまいました。
今後このような事がないよう、関係者一同、深く反省するとともに、コミュニケーション体制を見直し、再発防止策を講じてまいります。
この事例は、広告であることを明示しないことのリスクを示す典型例となりました。
ペニーオークション詐欺事件と芸能人の関与
2012年、ペニーオークションサイト「ワールドオークション」が、入札ごとに手数料が発生する仕組みを悪用し、利用者から不正に手数料を徴収していたことが発覚しました。
さらに、複数の芸能人が実際には落札していない商品を「安く落札できた」とブログに投稿していたことが判明し、これらの投稿は、業者からの依頼によるものでありながら、広告であることが明示されていませんでした。
この事件は、ステマの問題点を広く知らしめるきっかけとなり、「ステマ」という言葉が一般にも浸透する契機となりました。
参照:ぺ二オク詐欺事件から10年以上…「ステルスマーケティング規制」令和5年10月新設も、事業者側「広告作成」の戦々恐々【弁護士が解説】
豊胸サプリ「ジュエルアップ」「モテアンジュ」のInstagram投稿
2021年、豊胸効果を謳ったサプリメント「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」が、Instagram上で「2週間でバストアップした」といった投稿を通じて宣伝されていました。
これらの投稿は、企業からの依頼によるものでありながら、広告であることが明示されていませんでした。
また、商品の効果について科学的根拠が示されていなかったことから、消費者庁はこれらの表示が景品表示法に違反するとして、再発防止命令を出しました。この事例は、SNS上での広告表示の重要性と、誇大な効果表現のリスクを示しています。
サプリメントを摂取するだけで豊胸効果が得られるとうたった広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして消費者庁は10日までに、販売会社「アシスト」と同社の通販事業を運営する「アクガレージ」(いずれも東京)に再発防止命令を出した。
口コミを装った宣伝「ステルスマーケティング(ステマ)」も含まれており、同庁によるとステマに同法に基づく措置命令を出したのは初めて。
対象商品は「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」。2018年3月以降、写真共有アプリ「インスタグラム」や成功報酬型のアフィリエイト広告で、「#バストアップサプリ」「2週間で夢の谷間ができました」などと表示した。
インスタの投稿者には、商品モニターであることを隠して宣伝するよう指示していたという。
各地の消費生活センターには9月末までに、2商品に関する相談が約1800件寄せられた。
消費者庁は根拠となる資料の提出を求めたが、両社とも提出せず、同庁の調査に対し「命令を真摯に受け止めて表示の改善に努める」と話したという。〔共同〕
引用:日本経済新聞(豊胸サプリ、根拠なし 「ステマ」にも措置命令)
ステマによって企業が受けた信頼損失とその影響
ステルスマーケティングが発覚した場合、企業は法的リスクだけでなく、ブランドの信頼失墜や顧客離れ、売上低下といった深刻な影響を受けることになります。
ステマ問題は「気づかれなければいい」と考えて軽視されがちですが、発覚した際の代償は決して小さくありません。
この章では、これまで紹介してきた事例をもとに、企業が被った経済的損失やブランド価値への影響について掘り下げて解説します。
ステマは“炎上”で終わる話ではなく、長期的な経営リスクであることを認識する必要があります。
炎上の影響はブランド価値の低下と経済的損失
SNSでの炎上やメディア報道は瞬時に拡散し、企業イメージに大きな傷を残します。
大手企業でさえ、ステマと見なされたプロモーションに対し、批判が一気に広まり不買運動に発展するケースも存在します
こうした事態は、最悪の場合、直接的な売上減だけでなく、顧客の離脱、株価の下落、提携先や取引先からの信用喪失にも波及します。
「炎上マーケティング」の誤解とリスクのすり替え
一部では「炎上しても話題になれば良い」という“炎上マーケティング”的な考え方が存在しますが、これは極めて短期的で危険な戦略です。
ステマが発覚することで、消費者の企業に対する倫理観・誠実さへの評価が著しく低下し、以後のプロモーション施策に対する反発も強まります。
特に美容・健康・金融などの高関与商材では、信頼性が購買判断の大きな要素を占めるため、ステマ炎上による長期的な売上低下やブランド離脱は深刻な課題となります。
また、SNS上では一度失った信頼を回復することは非常に難しく、「再発防止策を講じても疑われ続ける」という風評被害も残りがちです。
ステマによる企業のレピュテーションリスクとは
企業にとっての「評判(レピュテーション)」は、単なるイメージ戦略ではなく、資産価値そのものです。
特に広告代理店・ブランド・商品提供者としての立場にある企業は、ユーザーとの信頼関係の上に成り立っているため、一度のステマ疑惑が致命傷となることもあります。
実際、過去に炎上した企業の一部では、SNSアカウントの運用停止や広告キャンペーンの全取り下げ、さらには販売停止まで追い込まれた事例もあります。これらはすべて、広告であることを明示しなかったことに端を発しています。
ステマを防ぐための広告運用対策と社内体制の整備
前章までで解説したように、ステマは一度でも発覚すると企業の信頼や売上に甚大な被害を及ぼします。
こうしたリスクは広告運用の段階から適切な対策を講じることで防ぐことが可能です。
ステマは“意図的に隠す”ケースだけでなく、“明示すべき表記が抜けていた”などの不注意や管理不足によっても発生します。
この章では、企業が広告運用においてステマを未然に防ぐために整備すべき社内体制や、具体的な管理フロー、インフルエンサーやアフィリエイト広告への対応策を紹介します。
広告表現チェック体制の導入
まず重要なのは、広告を公開する前にステマリスクを検知するためのチェック体制を社内に整備することです。SNS投稿やインフルエンサー活用、アフィリエイト広告など、さまざまな形式のプロモーションに共通して必要なのが、「これは消費者にとって広告と分かるか?」という視点です。
具体的には以下のような仕組みなどの導入が効果的です。
- 広告表現チェックリストの導入
(「PR」「提供」などの明示表記の有無、誇張表現の有無など) - 制作部署・法務部門・外部パートナーとの三者監修体制
- 広告公開前のダブルチェックフロー(例:社内稟議にチェック欄追加)
SNSや動画コンテンツにおいては、冒頭・テキスト・ハッシュタグ・概要欄のいずれかで広告であることを明示することが必須です。
アフィリエイト広告におけるガイドライン管理
アフィリエイト広告は特にステマとの境界が曖昧になりやすい領域です。第三者(アフィリエイター)が制作・発信する広告であっても、最終的な責任は広告主が負うと消費者庁は明言しています。
アフィリエイト広告の実施は次のような運用体制が必要不可欠です。
- ASPと連携した広告表現の事前承認制度
- 禁止表現リストの作成・配布(例:「飲むだけで痩せる」はNG等)
- アフィリエイター向けの明確なレギュレーションの策定
- 報酬条件に「広告表示遵守」を含める
管理が難しければ、アフィリエイト広告を得意とする広告代理店に相談するなども検討すると良いでしょう。
また、万が一違反が発覚した場合のために、掲載中広告の巡回監査(クローリング)ツールや違反報告窓口の整備も重要です。
社内・外部関係者への教育・研修の重要性
いかにチェック体制を整えても、実際に業務を担当するメンバーがステマリスクを正しく理解していなければ防止は難しいのが実情です。
実際に、担当者ベースで厳しい売上ノルマや広告指標のノルマなどが課せられている場合、わかっていてもノルマ達成のためにルールを逸脱してしまうケースも少なくありません。
そのため、社内における教育と啓発活動も重要です。
- 広告・マーケティング・PR部門向けのステマ対応研修
- ガイドラインを共有し、定期的にアップデートを通知
- 外部パートナー(代理店、インフルエンサー事務所など)との連携研修
ステマに関する法律やガイドラインは、年々厳格になってきています。
外注先も含めた全体の運用意識の統一が、ステマを防ぐ最も効果的な対策と言えるでしょう。
まとめ
ステルスマーケティングは、意図の有無に関わらず発生するリスクがあり、炎上や行政処分といった重大な問題に発展する可能性をはらんでいます。
SNSや口コミ、アフィリエイトなど、消費者との接点が多様化した今だからこそ、広告とわかる表現を徹底することが信頼の出発点となります。
これまでご紹介した事例から学べることは、「ルールを知らなかった」では済まされないという現実です。
特に2023年10月の法改正以降は、「広告であることの明示は“義務”」となっており、違反時には行政指導や措置命令が下される厳格な体制が整っています。
企業がステマを防止するためには、単なる表記の徹底にとどまらず、次の3つの観点で対策を講じることが求められます。
- 明示表記の徹底と表現管理
-
「広告」「PR」「提供:企業名」などの表示を、投稿の冒頭や分かりやすい位置に必ず明示すること。これは最低限のルールであり、視認性や文脈にも配慮した運用が必要です。
- 広告主責任を前提とした社内チェック体制
-
アフィリエイトやインフルエンサー投稿においても、最終的な責任は広告主にあります。法務・制作・マーケティングの連携による事前確認フローを導入し、「うっかりステマ」を防止しましょう。
- 関係者への教育と外部パートナーとの連携
-
社内スタッフだけでなく、広告代理店、ASP、インフルエンサー事務所など外部関係者に対しても、ステマ対策のルールと姿勢を共有することが、継続的なリスク回避につながります。
広告とは、本来、企業と消費者の信頼で成り立つコミュニケーション手段です。
その信頼を損なわないためには、「伝える技術」以上に、「伝える姿勢」が問われる時代となっています。
今回ご紹介した事例と対策を参考に、貴社の広告活動をいま一度見直し、信頼される情報発信を心がけましょう。