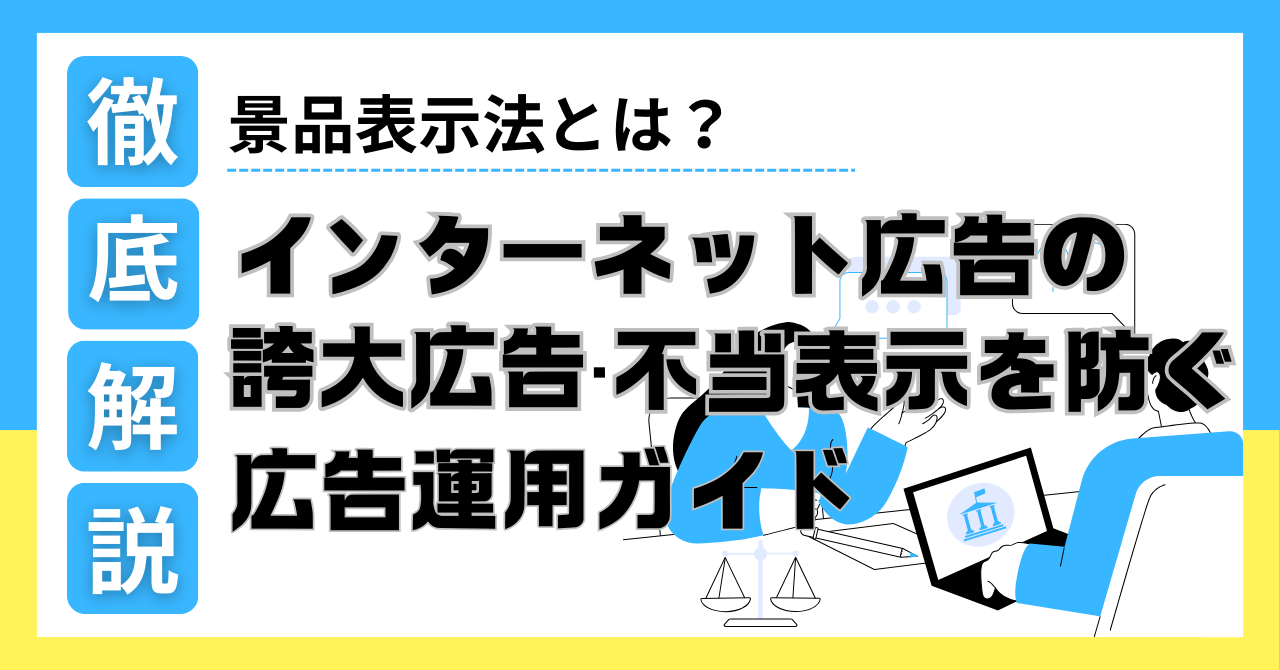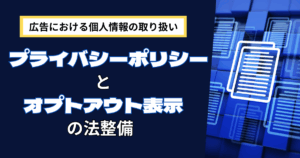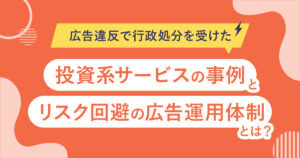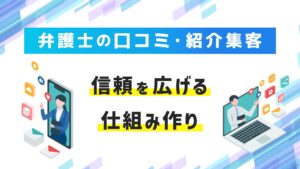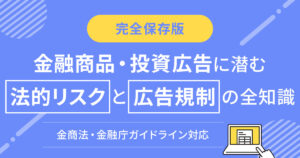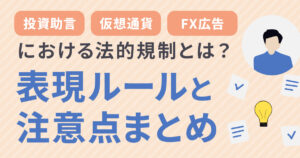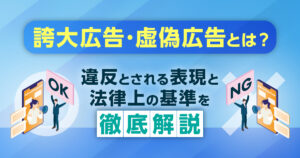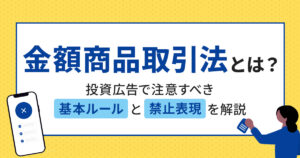景品表示法とは?
インターネット広告を運用するマーケティング担当者や企業のコンプライアンス担当者にとって、「景品表示法」の理解は避けて通れない課題です。
しかし、
- 「法律の細かい規定が複雑で、どのように広告をチェックすればいいのかわからない」
- 「誇大広告や不当表示で違反しないか不安」
といった悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
本記事では、景品表示法の基本から、特にネット広告を運用する上で重要なポイントや違反事例、具体的な広告表現のチェック方法まで網羅的に解説します。
さらに、企業が景品表示法違反を未然に防ぐためコンプライアンス体制の整備や、関連するその他の法律まで幅広くカバーしています。
この記事を読むことで、自社の広告表現が法的リスクを抱えていないか明確に判断でき、広告運用における法的なトラブルを事前に防ぐことができます。
「知らなかった」では済まされない法律違反を回避し、安心して広告を運用するための実践的な知識を、本記事でご確認ください。
景品表示法とは?基礎知識を徹底解説
インターネット広告を適切に運用するには、「景品表示法」の基礎を正しく理解することが必要不可欠です。
本章では、景品表示法の目的や背景、法律の核となる「景品規制」と「表示規制」の概要を分かりやすく解説します。
さらに、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」など、広告担当者が必ず理解しておくべき具体的な表示規制について、事例と根拠となる法令を交えながら説明します。
景品表示法の目的と背景
景品表示法(正式名称:「不当景品類及び不当表示防止法」)は、消費者が正確な情報に基づいて商品・サービスを選べるようにすること、そして企業間での公正な競争環境を整備することを目的として制定されました。
景表法(けいひょうほう)と略されることもあります。
この法律が作られた背景には、企業が売上を上げるため、過大な景品や事実と異なる誇大な表示を行い、それにより消費者が正しい判断を行えなくなるケースが頻発したことがあります。
景品表示法はこのような状況を是正し、消費者の利益を守ることを目指しています。
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
引用:不当景品類及び不当表示防止法 第1条(目的)
景品表示法が規制する2つの柱:「景品規制」と「表示規制」とは?
景品表示法が規制する対象は大きく「景品規制」と「表示規制」の2つに分類されます。
景品規制とは
景品規制とは、商品やサービスに付随して提供される景品(おまけやプレゼント)に対する規制です。
消費者の冷静な判断を妨げるほどの過大な景品提供を防ぐため、具体的な金額や提供条件に制限があります。法令では次のように記載されています。
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
引用:不当景品類及び不当表示防止法(第二十二条)
具体例を挙げると
- 一般懸賞(抽選など):景品額は商品の価格の20倍以内で、最大10万円まで。
- 総付景品(もれなくプレゼント):商品価格が1,000円未満なら200円まで、それ以上は価格の20%まで。
などが挙げられます。
表示規制とは
表示規制とは、商品やサービスの広告や表示で消費者に誤認を与える内容を禁止するものです。実際よりも商品が良く見えるような誤解を生む表示を防止するためのルールです。
インターネット広告に関わる表示規制でよく見聞きするのは、「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が代表的です。
もう少しわかりやすく、広告運用の担当者が特に注意すべき、表示規制の具体的な内容と事例を挙げて解説します。
- 優良誤認表示
-
優良誤認表示とは、商品の性能や品質を実際よりも著しく優れていると誤認させる表示を指します。
具体的には次のような表示で消費者の判断を錯誤可能性のあるような表記です
- 健康食品で「誰でも簡単に10kg痩せる」といった科学的根拠のない表現。
- 美容化粧品で「シミが完全に消える」といった過度な効果を訴える表現。
- 有利誤認表示
-
有利誤認表示とは、実際の価格や取引条件よりも著しく消費者にとって有利であるかのように表示することです。
具体的には次のような表示で消費者の判断を錯誤可能性のあるような表記です
- 「通常価格5万円→今だけ1万円!」と広告しつつ、実際には5万円で販売実績がない場合。
- 「期間限定特価」と称し、実際は常に同じ価格で販売しているケース。
- 不当表示(その他誤認されるおそれがある表示)
-
「優良誤認」「有利誤認」に当てはまらなくても、消費者を誤認させるおそれのある表示全般を指します。
- 「日本製」と表記しながら海外で生産された商品。
- 「無添加」と表示しながら、一部の添加物を排除しただけで他の添加物が入っている場合。
ここまで、主にインターネット広告にかかる、景品表示法について基礎的な知識について解説してきました。
次章以降で具体的な対策を詳しく解説していきますので、引き続き確認していきましょう。
ネット広告で注意すべき景品表示法のポイント
インターネット広告は手軽に始められる一方で、知らないうちに景品表示法に違反してしまうリスクも潜んでいます。
本章では、ネット広告特有の落とし穴として特に注意が必要なSNS広告、アフィリエイト広告、インフルエンサー広告の具体的事例を紹介します。
また、誇大広告や打ち消し表示の正しい扱い方、さらに広告審査で指摘されやすいポイントを解説し、法的リスクを防ぐための具体的な対策を解説します。
ネット広告特有の落とし穴(SNS広告、アフィリエイト広告、インフルエンサー広告)
インターネット広告では、企業が直接発信する広告だけでなく、SNSやインフルエンサー、アフィリエイターを介した広告にも注意が必要です。
これらは消費者が広告だと気づきにくいため、特に景品表示法違反につながりやすい傾向があります。
令和5年10月から景品表示法に明記された、ステルスマーケティングについての規制は特に注意が必要です。
SNS広告・インフルエンサー広告の注意点
InstagramやYouTubeなどで、フォロワー数の多いインフルエンサーが投稿する商品紹介が、広告であることを明記しない場合、「ステルスマーケティング(ステマ)」として景品表示法違反となります。
消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。
消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。
一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。
景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
引用:消費者庁(令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。)
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
具体的なケースとして次のようなケースが想定されます
- インフルエンサーが美容商品を宣伝する際、実際の使用感よりも効果を誇張した投稿を行い、「広告」と明記していないために消費者に誤認を与えた事例。
- 「個人的な口コミ」を装い、企業から報酬を得ていることを明示せずに商品を推薦する投稿。
アフィリエイト広告の注意点
アフィリエイト広告では、広告主が直接表現を管理しづらく、誇大表現が横行するケースがあります。
広告主は、アフィリエイターが違反表示をした場合も責任を問われるため、管理体制の整備が必要です。
広告主側は広告内容のについてレギュレーションを明確に定め、アフィリエイターはもちろんのこと、アフィリエイターを管理するASPや中間代理店への周知の徹底や有事の際の責任の所在などを明らかにしておきましょう。
特に違反が起きやすい「誇大広告」や「打ち消し表示」の扱い方
インターネット広告で特に問題になりやすい、「誇大広告」と「打ち消し表示」のについて具体的な事例を取り上げて、対策方法をまとめます。
誇大広告の具体例と注意点
改めて、誇大広告とは商品の性能や効果を、実際よりも過度に良く見せる訴求方法のことをいいます。
例えば、
- サプリメントで「1週間で10kg痩せる」といった過度な表現。
- 化粧品で「シワが100%消える」と断言するような表現。
消費者がこうした誇張した広告によって誤認すると、景品表示法の「優良誤認表示」に該当し、措置命令や課徴金の対象となります。
医薬品などは薬機法(医薬品医療機器等法)によっても、その効果効能に対する広告に対して禁止事項が定められているので、特に注意が必要な分野です。
打ち消し表示とは
打ち消し表示とは、広告で表示した内容を補足・訂正するための表示で、「個人差があります」「効果を保証するものではありません」といった注記のことです。
問題になるのは、
- 打ち消し表示の文字サイズが小さすぎる。
- 表示場所が目立たない位置にある。
- スマホ画面ではスクロールしないと見えない場所に記載されている。
こうした打ち消し表示は、「消費者が容易に認識できない」として不適切と判断されます。
具体的な実態については、『打消し表示に関する実態調査報告書』に消費者庁が詳細をまとめており、ルール違反となる基準の目安となりますので参考にされてください。
打ち消し表示は、メインの広告表現の近くに、明確で読みやすいサイズ(メイン表記の8ポイント以上)で表示することが適切とされています。
景品表示法の違反事例と具体的な罰則
前章では、インターネット広告でありがちな具体例についてみてきました。
本章では、実際に摘発された健康食品、美容業界、オンライン通販の具体的な違反事例を紹介するとともに、措置命令や課徴金の内容や額、違反後の企業への影響を解説します。
景品表示法違反は、摘発された企業に金銭的な負担を与えるだけでなく、ブランドイメージの毀損や消費者の信頼喪失など、長期的な悪影響をもたらします。
自社の広告運用で同様のリスクを負わないための参考にしてください。
実際に摘発された景品表示法違反の具体的事例
消費者庁は近年、特に健康食品、美容、オンライン通販などのインターネット広告において景品表示法違反の摘発を強化しています。
以下では、その代表的な事例を取り上げます。
- ① 健康食品の誇大広告事例(痩身サプリメント)
-
ある健康食品会社が、痩身サプリメントのインターネット広告で「1カ月で必ず10kg痩せる」「誰でも簡単にダイエットできる」と科学的根拠のない過度な表現を使用したため、消費者庁から優良誤認表示として措置命令を受けました。
摘発理由は、「合理的な根拠を示せないにもかかわらず、消費者が効果を誤認する表示を行った」という点でした。
- ② 美容化粧品の不当表示事例(美白化粧品)
-
ある大手化粧品メーカーは、販売する美白化粧品について「シミが完全に消える」「使った全員が美白効果を実感」と広告していました。しかし、消費者庁の調査により、実際には「全員が効果を実感」という客観的根拠が存在しないことが判明し、優良誤認表示として摘発されました。
- ③ オンライン通販サイトの有利誤認表示事例(価格表示)
-
オンライン通販サイトを運営する企業が、特定の商品を「通常価格2万円→特別価格5,000円!」と広告しましたが、調査の結果、実際には通常価格で販売した実績がなかったことが判明し、有利誤認表示で措置命令を受けました。
以上、具体例三つを見てきました。
例えばアフィリエイト広告では、アフィリエイターは稼げることを行動の源泉としていることが殆どで、「できる限り多くのコンバージョンを獲得したい」という思いから過剰な訴求になりがちです。
広告主側も「良くない」と思いながらも、できる限り多くの顧客を獲得したいという思いから、それを放置してしまうことも少なくありません。
では、景品表示法違反した場合、どのようなペナルティがあるのか見ていきましょう。
違反発覚後の措置命令や課徴金の具体的な内容
まず、景品表示法違反が発覚しかつ摘発されると、消費者庁から「措置命令」や「課徴金納付命令」が下されます。
措置命令とは、消費者庁が企業に対し、違反表示の中止、再発防止策の実施、消費者への周知などを義務付ける命令です。
例えば、違反広告を即刻削除し、ホームページ上に謝罪文の掲載を行うことが命じられるケースがあります。
課徴金の具体的な原則として違反表示による対象商品の売上額の3%相当額が課されます。
実際の事例として、
- 健康食品の販売会社が約1億円の売上を得ていた場合、約300万円の課徴金。
- 大手美容化粧品メーカーが摘発されたケースでは、対象商品の売上が約10億円あり、約3,000万円の課徴金を課されました。
という実例が存在します.
不当景品類及び不当表示防止法では、次のように明記されており、
事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
引用:不当景品類及び不当表示防止法(第八条)
実際の法令運用については、消費者庁の「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)
に関する考え方」をガイドラインとして運用されています。
コンプライアンス担当者は法令に合わせて実際の運用ガイドラインも確認しておくとよいでしょう。
違反企業に与え得る影響は?
摘発の具体例や罰則の内容について確認してきました。
ここでは、法令に違反し摘発されてしまった場合のその後の影響について、解説します。
景品表示法違反は金銭的な負担だけでなく、企業のブランドイメージや消費者からの信頼にも深刻なダメージを与えます。
- ブランドイメージの著しい低下
-
違反企業の名前は消費者庁やメディアで公表されるため、インターネット上でネガティブな情報が拡散し、企業の信頼性が大きく低下します。
特にSNS上では一度拡散すると、長期間にわたりネガティブな情報が残るケースが多く、ブランドの回復が困難になります。
- 経済的損失(売上減少、取引先の離脱)
-
消費者からの信頼低下により、売上が大幅に減少することがあります。また、流通業者や販売代理店から取引停止や契約解除を求められることもあります。
さらに、広告代理店が違反企業の広告掲載を拒否することもあり、その後の販路開拓に苦労するケースも少なくありません。
- コンプライアンス体制の再構築コスト
-
違反が発覚した企業は、再発防止策の徹底や法令遵守のための社内教育体制を一から構築し直す必要が生じます。
法的な対応や専門家の助言を受けるために新たな費用が発生し、企業にとってさらなる経済的な負担が生じます。
景品表示法違反によるダメージは想像以上に深刻です。売上や利益以上に、「消費者からの信頼」という企業にとって最も重要な資産を失うことにもなりかねません。自社が同じ状況に陥らないように、広告表現には細心の注意を払い、適切なコンプライアンス体制を構築することが求められます。
次章では、実務で役立つ「広告表現チェックリスト」を解説しますので、ぜひ広告運用に役立ててください。
誇大広告や不当表示を避けるための広告表現チェックリスト
インターネット広告を運用する際に、「誇大広告」や「不当表示」に該当しないよう十分な注意が必要です。
しかし、実際の広告運用現場では、
- 「どのような表現がNGなのか分からない」
- 「具体的なチェックポイントを教えてほしい」
という悩みをよく耳にします。
本章では、景品表示法に抵触する代表的なNG表現を解説するとともに、実務レベルで即座に活用できる「広告表現チェックリスト」を掲載します。
さらに、企業がスムーズに広告を運用するための社内チェック体制の具体的な整備手順についても紹介します。
景品表示法に抵触する可能性がある代表的なNG表現
インターネット広告で特に注意が必要な「NG表現」を具体的に紹介します。
以下のような表現が広告内にある場合、景品表示法の「優良誤認」「有利誤認」などに該当する可能性があります。
- 「絶対に」「100%効果がある」「誰でも痩せる」など断定的で過度な表現
- 「即効」「たった1日で」「短期間で劇的変化」など、即効性や効果を過剰に示唆する表現
- 「業界No.1」「日本一」「最も売れている」といった客観的根拠がない表現
- 「圧倒的効果」「他社の10倍以上の効果」など根拠が曖昧な比較表現
- 「期間限定価格」としながら、実際には常時割引価格で販売しているケース
- 「通常価格→特別価格」と記載しているが、通常価格での販売実績がないケース
これらの表現は、特にアフィリエイト広告でよく見る表現ですが、直ちにNGであると判断される表現です。
アフィリエイト広告を運用している企業の中には、担当者ごとに高いノルマが科されることや様々なインセンティブにより、「成果を出すためにはこのくらいしないと」「このくらいは大丈夫だろう」「指摘されたら変更しよう」などと良くないことを知りながら、景表法に抵触する訴求表現をしてしまうことが、実際に多く存在します。
属人的な判断や決定では、どうしてもルールからはみ出してしまうことがあるので、次に解説するような第三者目線がチェックする体制などを整えることが重要になります。
実務レベルで使える「広告表現チェックリスト」
以下に示すチェックリストを広告作成時、また広告公開前のチェック時に活用してください。
| 広告表現チェックリスト | YES / NO |
|---|---|
| 効果を示す表現に「絶対に」「必ず」などの断定表現を使っていないか? | Yes/No |
| 「痩せる」「治る」などの効果表現に、具体的かつ客観的な根拠があるか? | Yes/No |
| 価格表示(割引表示)は実際の販売実績に基づいたものか? | Yes/No |
| 「期間限定」「数量限定」は事実に基づいているか? | Yes/No |
| 比較表現(「No.1」「日本一」等)に明確な調査データや根拠資料が存在するか? | Yes/No |
| 打ち消し表示(※個人差があります、など)が広告表示の近くにあり、明瞭で見やすいサイズになっているか? | Yes/No |
| 広告内の画像(Before-Afterなど)は実際の効果を誤認させないものか? | Yes/No |
| アフィリエイト広告やインフルエンサー広告の場合、広告表記が明確にされているか? | Yes/No |
※上記チェックリストで一つでも「NO」がある場合は必ず修正を行いましょう。
広告主側でのチェックはもちろん、アフィリエイターや代理店に展開するレギュレーションにこのようなチェックリストを含めてあげると親切です。
社内チェック体制を整えるために必要な具体的ステップ
景品表示法違反を防ぐためには、広告ディレクターやクリエイター・運用者などの個人の裁量に任せると、様々なポジション上の理由からルール違反になる行為をしがちです。
社内での広告審査体制を明確化し、第三者目線で監督することが重要です。
ここでは社内チェック体制を整える具体的なステップを解説しますので、それぞれの社内体制に合わせて、ご活用ください。
広告作成担当者が景品表示法の基礎知識を持ち、NG表現のリストを理解していることを確認し、日頃からNG表現チェックリストを周知し、広告作成時にチェック項目を遵守させる。
広告作成後は、必ず複数名(広告担当者、マーケティング責任者、法務担当者)によるクロスチェックを行いましょう。明確なチェックリストに基づいて客観的な判断を行います。
※チェックする担当者は、制作担当やディレクターなどと利害関係のない第三者的な立場が望ましいです。
内部チェックで問題箇所が見つかった場合、明確な修正指示を広告作成担当者に伝え、迅速に修正対応を行わせます。
修正後の再チェックを義務付け、修正指示が確実に反映されていることを確認します。
広告チェックの過程や修正対応の結果を記録し、社内で共有・保管します。
過去のチェック記録を蓄積して分析し、定期的な社内研修や教育プログラムの改善に活用しましょう。
こうした明確なチェックリストと具体的な社内体制を構築することで、景品表示法違反のリスクを効果的に軽減できます。広告担当者だけでなく、経営者やコンプライアンス担当者も一丸となって、日頃から適切な広告運用を徹底していきましょう。
次章では、景品表示法以外のインターネット広告に関わる関連法令について、確認していきましょう。
景表法以外にも広告にかかる法令は多数存在します。
インターネット広告に関連する景表法以外の法律と注意点
インターネット広告を運用する際、景品表示法以外にも重要な法律が複数存在します。
特に「薬機法」「医療法」「健康増進法」「著作権法」は、広告表現において誤りが起きやすく、違反時のペナルティも重いため注意が必要です。
本章では、これらの法律について簡単に紹介し、それぞれの広告表現で特に注意すべき具体的なポイントを列挙します。
ネット広告を安心して運用するためにも、各法令の基本的なルールを押さえておきましょう。
景表法以外にもインターネット広告を扱う上で知っておくための法律
景品表示法以外にも、インターネット広告を取り扱うために押さえておくべき法令があります。
| 法令 | 法令の目的 |
|---|---|
| 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法) | 消費者の誤認を防ぐ |
| 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律) | 医薬品・化粧品などの効能表示規制 |
| 医療法 | 医療機関の広告規制 |
| 健康増進法 | 健康に関する誇大表現規制 |
| 著作権法 | 画像・コンテンツの無断使用防止 |
医療法や健康増進法など、広告に関係しないと思われる法令もピックアップしていますが、これらの法令の中にも広告についての規制が明記されています。
次は、それぞれの法令のインターネット広告で注意すべきポイントを簡単に解説します。
インターネット広告で注意すべき法律の概要とポイント
それぞれの法令の概要や具体的な注意点を簡単にまとめています。
自社で運用しているプロダクトの広告やクライアントの広告運用について、該当しそうな法令があれば、参考にしてください。
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
-
薬機法は、医薬品、化粧品、健康食品、医療機器などの広告表示を厳格に規制しています。
具体的には次のようなことが挙げられます
- 健康食品や化粧品などに対して、「病気が治る」「効果がある」といった医薬品的な効能を謳うことは禁止されています。
- 「がんが治る」「即効性がある」など根拠のない誇大表現は罰則対象です。
違反すると、措置命令や刑事罰(最大で懲役や数百万円の罰金)が科されることがあります。
- 医療法
-
医療法は、病院やクリニックなど医療機関の広告を規制する法律です。
具体的には次のようなことが挙げられます
- 医療広告では「日本一」「No.1」など、比較や優位性を示す表現が禁止されています。
- 「絶対安全」「無痛」「副作用なし」など断定的な安全性を謳う表現は認められていません。
違反すると厚生労働省や自治体から是正指導を受け、悪質な場合は行政処分や医療機関名の公表などのリスクがあります。
- 健康増進法
-
健康増進法は、食品やサプリメントの健康に関する誇大・虚偽の広告を禁止する法律です。
薬機法と内容が重なる点もありますが、「健康増進法」でも広告を制限する項目がありますので、関連商品の広告を取り扱う際には確認したい法令です。
具体的には次のようなことが挙げられます
- 「飲むだけで簡単に痩せる」「これだけで血圧が下がる」など、明確な科学的根拠がないまま健康効果を謳う広告表現は禁止されています。
- 表示には必ず明確な根拠(エビデンス)が必要となります。
違反すると厚生労働省から是正勧告や罰金を科されるリスクがあります。
- 著作権法
-
著作権法は、広告で使用する画像や文章、動画など他者が創作したコンテンツを無断で使用することを禁止しています。
具体的には次のようなことが挙げられます
- ネット上で拾った画像を無断で使用することは絶対に避けましょう。画像や動画素材は必ず正規の使用許可を取得する必要があります。
- 他社サイトのテキストを無断転載すると、著作権侵害になります。
違反した場合は、民事上の損害賠償請求に加え、刑事罰(最大で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
景品表示法に関するよくある質問
インターネット広告を運用していると、「この表現は景品表示法に違反するの?」と判断に困る場面がよくあります。
本章では、実務現場でよくある具体的な広告表現に関する疑問をQ&A形式で解説します。
さらに、措置命令や課徴金が発生する条件やプロセス、初心者が疑問に感じるポイントについても分かりやすく回答しますので、広告運用時の参考にしてください。
- 「満足度98%!」という広告表現は景品表示法に違反しますか?
-
「満足度98%」などの表現は、明確な根拠(調査の実施時期・対象人数・調査方法)があれば違反になりません。しかし、客観的な調査を行わずにこのような表現を使用すると、「優良誤認表示」と判断される可能性があります。広告に掲載する際は必ず根拠となる調査データを併記しましょう。
- 「期間限定価格」と書いたが、実際はずっとその価格のままです。これは問題ありますか?
-
「期間限定価格」と表示しながら、実際には期間が設定されていない場合や常時その価格で販売している場合、「有利誤認表示」として違反となります。消費者が誤認しないよう、期間限定や割引表示は必ず実態に即した内容を記載してください。
- アフィリエイト広告でパートナーサイトが誇張表現をしてしまった場合、広告主にも責任はありますか?
-
あります。アフィリエイト広告においても、広告主が監督責任を問われます。パートナーサイトが行った表示でも広告主が管理・修正する義務があるため、定期的なモニタリングを行い、違反があれば即座に是正指示を出す必要があります。
- 措置命令や課徴金が出るのはどんな場合ですか?
-
消費者庁が景品表示法違反の疑いがある表示を発見すると、まず企業に対し調査やヒアリングを実施します。その結果、違反が確認されると「措置命令」が出され、違反表示の停止、再発防止策の実施、消費者への告知などを命じられます。
さらに、違反表示に関連する商品の売上額が5,000万円以上ある場合、原則として売上額の3%の「課徴金」が科されます。
課徴金を支払った場合でも、措置命令で定められた改善措置は必ず実施しなければなりません。
- 打ち消し表示(※個人差があります等)はどの程度のサイズで表示すれば違反になりませんか?
-
打ち消し表示は「一般消費者が容易に認識できる」ことが条件です。具体的には、本文表示の文字サイズの8ポイント以上を目安に、近接した場所に記載する必要があります。スマートフォンなどのデバイスでも見えやすい位置に記載しましょう。
- 景品表示法違反はすぐに罰金になりますか? 初回は注意だけで済みますか?
-
初回だから注意だけで済むとは限りません。消費者庁は違反の悪質性や影響度を見て判断します。悪質と判断されれば初回でも措置命令や課徴金の対象になります。また、措置命令を受けた企業名は消費者庁のウェブサイト等で公表されるため、企業のブランドに深刻な影響を与えます。
- 個人のSNS投稿で企業の商品をPRする場合も「広告」と明記しないと違反になりますか?
-
企業から報酬や商品提供を受けてPRする場合は、個人のSNS投稿であっても「広告」と明示しないとステルスマーケティング(ステマ)となり、景品表示法違反の対象です。インフルエンサーや社員個人のSNS投稿も必ず「広告」「PR」などの表記を明確にしましょう。
景品表示法についてよくある疑問点を把握し、広告運用時の注意事項を理解することが大切です。
ADMAを運営する株式会社Adrimは、広告運用におけるリーディングカンパニーです。景品表示法や各種インターネット広告に関わる法令遵守について幅広い知識があり、社内運用体制も一から構築してきたノウハウがあります。
よくある質問でカバーしきれないご質問などお気軽にご相談ください。
まとめ
景品表示法を遵守することは、単に法的なリスクを回避するだけでなく、企業価値の向上やブランドの信頼性アップにもつながります。
逆に、一度でも法律違反を起こすと、措置命令や課徴金などの直接的なペナルティに加え、ブランドイメージの深刻な毀損など間接的な損害も生じます。
この記事では、景品表示法の基本知識やネット広告特有の注意点、実際の違反事例、具体的な広告チェックリスト、コンプライアンス体制の構築方法などを幅広く解説してきました。
特に、SNS広告やアフィリエイト広告では、自社だけでなく第三者の広告表現にも監督責任が発生することを忘れてはいけません。
法律遵守の意識は日常的な広告運用のなかで定着させることが重要です。定期的なチェックや社員教育、コンプライアンス体制の整備を徹底し、「知らなかった」では済まされない状況を未然に防ぎましょう。
本記事で紹介した広告チェックリストなどぜひ今日からご活用ください。
今すぐ自社の広告表現をチェックし、リスクを回避して、安全で安心な広告運用を実現しましょう。