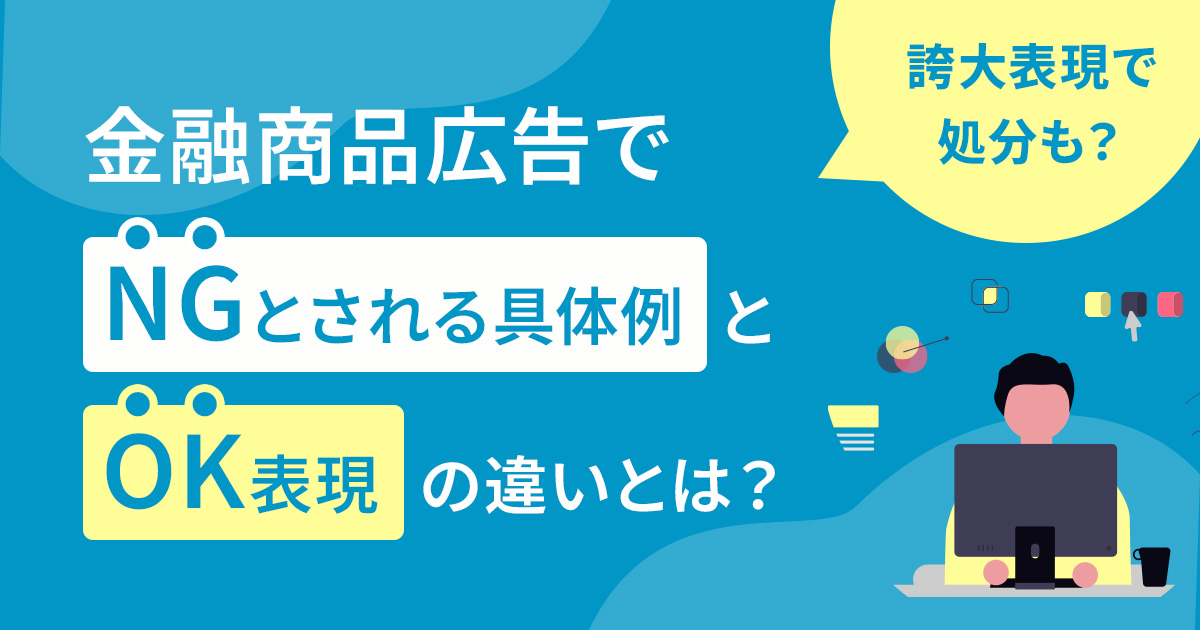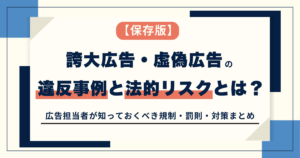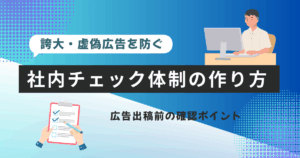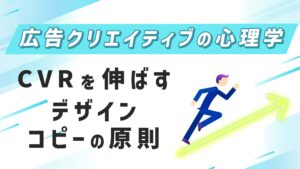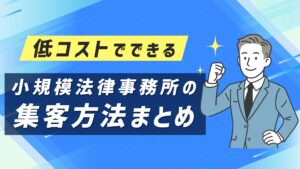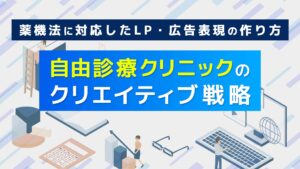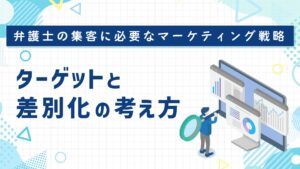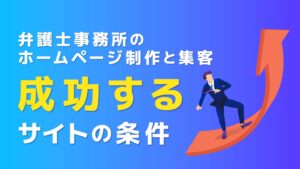「この表現は大丈夫かな?」
「審査に通るだろうか…」
金融商品の広告運用を担当していると、こんな悩みが尽きないものです。特に広告効果を高めたいがために魅力的な表現を使いたい一方で、規制の厳しい金融業界では一歩間違えば行政処分のリスクがあります。
金融庁は誇大広告を含む不適切な広告表現に対して厳しい姿勢を示しており、金融商品取引法に基づく業務改善命令などの行政処分が行われる可能性があります。
金融機関の適切な業務運営の確保を重視する金融行政の中で、広告表現の適切性はこれまで以上に厳しくチェックされています。しかし「NGとOKの境界線がわからない」「具体的な修正例が見当たらない」という声も聞かれるのが現状です。
本記事では、金融商品広告における誇大表現の規制の全体像から、商品別・媒体別のNG/OK事例、さらには実際の行政処分事例まで徹底解説。
この記事を読めば、コンプライアンスを遵守しながらも効果的な広告表現のポイントがわかり、審査通過率の向上と処分リスクの低減につながるでしょう。
金融広告と誇大表現の規制全体像
金融商品広告は一般商品より厳格な規制下にあります。「投資家保護」と「市場の公正性確保」を目的に、法律、金融庁の指針、自主規制団体のルールが重層的に機能しているのが特徴です。
ここでは、金融広告を取り巻く規制の枠組みとその関係性について解説していきます。
金融広告に関わる法律と規制
金融広告に関する規制の基盤となるのは主に以下の法律です。
1. 金融商品取引法
金融商品取引法は金融広告規制の中核となる法律です。同法では「広告等の規制」として、金融商品取引業者等が行う広告において、「虚偽の表示」「誤解を生じさせる表示」を禁止しています。特に、以下の事項については明確な表示が求められています。
- 手数料等の費用に関する事項
- 損失が生じるおそれがある旨
- 金融商品取引業者等の商号
- 登録番号
金融商品取引法に違反した場合、業務改善命令や業務停止命令、最悪の場合は登録取消しなどの行政処分を受ける可能性があります。
(禁止行為)
引用:金融商品取引法 | e-Gov 法令検索
第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
2. 保険業法
保険商品の広告については、保険業法第300条において「誤解させるおそれのある比較・事実と異なる表示」「将来の利益の約束・予想に関する断定的判断」などが禁止されています。
3. 銀行法
銀行商品の広告については、銀行法第13条の3および銀行法施行規則第14条の11の3において、預金等の受入れに関する広告等に係る規制が定められています。
4. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
「優良誤認」(実際よりも著しく優良であると誤認させる表示)や「有利誤認」(実際よりも著しく有利であると誤認させる表示)を禁止しています。金融商品広告も対象となります。
金融庁による監督指針
金融庁は「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、広告等の審査体制について具体的に言及しています。監督指針では以下のような項目に対してモニタリングが行われています。
- 社内における広告等の審査体制の整備状況
- 利益や損失に関する事項の表示方法
- リスク情報の表示方法(利益を強調する表現と同程度の文字の大きさ・明瞭さでリスクも表示されているか)
- 断定的判断の提供や確実性を保証する表現の有無
これらの規制に違反した場合、金融庁による行政処分(業務改善命令、業務停止命令など)を受ける可能性があります。例えば過去には、不適切な広告表現によって複数の金融機関が業務改善命令を受けた事例があります。
規制団体と広告審査の関係
金融広告の適正化を図る上で、法律や金融庁の規制に加えて、業界団体による自主規制も重要な役割を果たしています。これらの団体は、より具体的かつ実務的なガイドラインを設けることで、会員企業の広告活動をサポートしています。
1. 日本証券業協会(JSDA)
証券会社等が加入する自主規制団体で、「広告等に関する指針」および「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」を定めています。
JSDAは会員に対して定期的な広告審査を実施しており、問題のある広告については改善指導や処分を行うことがあります。
2. 投資信託協会
投資信託委託会社等が加入する自主規制団体で、「広告等に関するガイドライン」を定めています。
3. 日本投資顧問業協会
投資顧問業者が加入する自主規制団体で、「広告及び景品類の提供に関する自主規制基準」を定めています。
4. 金融先物取引業協会
FX取引業者等が加入する自主規制団体で、「金融先物取引業務取扱規則」の中で広告に関する規定を設けています。
5. 日本貸金業協会
貸金業者が加入する自主規制団体で、「貸金業の広告及び勧誘に関する規則」を定めています。
6. 生命保険協会・日本損害保険協会
生命保険会社、損害保険会社がそれぞれ加入する自主規制団体で、「生命保険商品の広告に関するガイドライン」「損害保険の募集文書等の表示に係るガイドライン」をそれぞれ定めています。
広告審査の流れと相互関係
金融広告は通常、以下のような多重チェック体制で審査されます。
- 社内審査:金融機関内の広告審査部門(コンプライアンス部門)による自主審査
- 社外審査:自主規制団体による事前審査(大規模キャンペーンなど)や事後審査
- 当局モニタリング:金融庁や証券取引等監視委員会による監視
特に重要なのは、これらが単に上下関係ではなく相互補完的な関係にあることです。例えば、自主規制団体のガイドラインは金融庁の監督指針を踏まえて作成され、逆に金融庁は自主規制団体の取組みを尊重しつつモニタリングを行います。
また、広告審査の実務では、法令や自主規制ルールの文言解釈について、業界団体と監督当局が定期的に意見交換を行い、解釈の明確化や運用の統一化が図られています。
このように、金融広告の規制は「法律」「監督指針」「自主規制」の3層構造になっており、それぞれが補完し合いながら投資家保護と市場の健全性確保に寄与しているのです。
金融広告の誇大表現NG/OK事例集(商品・媒体別)
金融商品の広告で誇大表現を避けるには、具体的な事例を知ることが効果的です。ここでは金融商品全般および各商品特有のNG表現とその修正例を紹介します。
金融広告に共通のNG表現と修正例
金融商品の種類を問わず、以下のような表現は誇大広告として規制対象となりやすいものです。
断定的な表現
NG例
「必ず儲かる」「確実に資産が増える」「絶対に損しない」
これらの表現は金融商品の将来のパフォーマンスを断定するもので、どんな金融商品でも将来の成果を保証することはできません。
修正例
「過去の実績では利益を上げています」「資産形成に役立つ可能性があります」「リスクを抑えた運用を目指しています」
修正例では断定せず、可能性や目標として表現しています。「過去の実績」を示す場合は、必ず「将来の成果を保証するものではありません」という注意書きを添えることが必要です。
誤解を招く比較表現
NG例
「他社よりも高い利回り」「業界最高水準の金利」(具体的な比較対象や条件を示さない場合)
単に「高い」「最高」と主張するだけでは、消費者に誤解を与える恐れがあります。
修正例
「2025年6月時点で国内主要10社の同種商品と比較して最高水準の金利」(調査日、比較対象、調査機関を明記)
修正例では、具体的な比較対象や調査時点を明記することで、主張の裏付けを示しています。
リスク情報の不十分な表示
NG例
(利益の可能性を大きく表示する一方で)リスク情報を小さな文字で目立たない場所に記載
修正例
リスク情報を利益の説明と同等の文字サイズ・目立ちやすさで表示し、「元本割れのリスクがあります」「為替変動により損失を被る可能性があります」などを明確に記載
金融庁の監督指針では、リスク情報は利益に関する情報と同等以上の文字の大きさ・明瞭さで表示することが求められています。
証券広告のNG表現と修正例
証券広告特有のNG表現と修正例を見ていきましょう。
株式投資に関する表現
NG例
「このテクニカル指標で買いシグナル点灯中!」「AI分析で銘柄を選定、成功率95%!」
特定の分析手法や指標の有効性を断定的に述べることは避けるべきです。
修正例
「当社が注目するテクニカル指標では買いシグナルの条件を満たしています」
「当社のAI分析モデルでは過去データに基づく検証で約95%の銘柄で利益となりました(期間:2023年1月〜12月)」
修正例では、分析の主体を明確にし、過去の結果であることを示しています。
FX・暗号資産広告のNG表現と修正例
FXや暗号資産取引は、ハイリスク・ハイリターンの性質上、特に慎重な広告表現が求められます。
FX取引に関する表現
NG例
「レバレッジ25倍で大儲け!」「FXで不労所得を実現」「1日1万円の簡単副収入」
レバレッジはリスクも増幅させる点に触れず、簡単に儲かるイメージを与える表現は不適切です。
修正例
「レバレッジ最大25倍で取引可能。ただし、損失もレバレッジ倍に拡大する可能性があります」
「取引の経験・知識・資金力に応じたリスク管理が必要です」
修正例では、レバレッジの両面性を説明し、取引に必要な条件を示しています。
暗号資産に関する表現
NG例
「今後1000倍になる可能性」「毎月〇%増加中」「将来性抜群の次世代コイン」
暗号資産の将来価値を断定的に述べることは非常に問題があります。
修正例
「過去に大きく価格が上昇した事例もありますが、暗号資産は価格変動が大きく、大幅な価値下落のリスクもあります」
「直近3ヶ月間で月平均〇%上昇していますが、今後も同様の上昇が続く保証はありません」
修正例では、過去の実績は示しつつも、将来の値動きについては断定せず、リスクにも言及しています。
保険広告のNG表現と修正例
保険商品は、将来の保障や資産形成など、長期的な視点で検討する商品です。特に注意すべき表現を見ていきましょう。
外貨建て保険に関する表現
NG例
「円建てより高い利回り」「為替差益で更にお得」
為替リスクに十分触れずに利点のみを強調することは避けるべきです。
修正例
「現在の金利情勢では円建てより高い利回りとなっていますが、為替変動により円換算の受取額が元本を下回るリスクがあります」
「為替差益が発生する可能性がありますが、為替差損となる可能性もあります」
修正例では、為替リスクについて明確に説明しています。
保険の保障内容に関する表現
NG例
「どんな病気でも安心の保障」「すべての入院に対応」
保険には免責事項や支払条件があるため、誤解を招く表現は避けるべきです。
修正例
「幅広い疾病を保障しますが、契約日から90日以内の発病や既往症など、お支払いできない場合があります」
「病気・ケガによる入院を保障します(所定の精神疾患など、一部対象外となる場合があります)」
修正例では、条件や例外について明記しています。
ローン広告のNG表現と修正例
ローン商品は借入を伴うため、特に慎重な広告表現が求められます。
金利に関する表現
NG例
「業界最低水準の金利」「驚きの低金利3.0%」(条件の明示なし)
修正例
「当社調べ:2025年7月現在、主要消費者金融5社の同条件商品との比較において最低水準」
「年3.0%〜18.0%(お借入額・審査結果により異なります)」
修正例では、比較の根拠や金利の適用条件を明記しています。
住宅ローンの表現
NG例
「全期間固定0.5%」「変動金利ずっと年1.0%」
金利の適用条件や将来の変動可能性に触れない表現は不適切です。
修正例
「当初5年間は年0.5%の固定金利、以降は店頭表示の固定金利型住宅ローンの金利を適用(借り換え含む全期間の適用には条件があります)」
「現在の変動金利は年1.0%ですが、市場金利の変動に応じて適用金利は変更されます」
修正例では、金利適用の期間や条件を明確にしています。
以上のように、金融広告ではリスクや条件を適切に示すことが重要です。誇大表現と見なされるか否かは文脈や全体のバランスによっても変わりますが、上記の修正例を参考に、読み手に誤解を与えない表現を心がけましょう。
金融広告の媒体別NG表現と留意点
金融広告の誇大表現は媒体ごとに特有の課題があります。表示スペースの制約、動画の視聴性、SNSの拡散性など、媒体の特性を踏まえた上で適切な表現を選ぶことが重要です。
ここでは、主要媒体ごとのNG表現と改善のポイントを解説します。
LPの誇大表現と改善のポイント
ランディングページ(LP)は情報量が多く、様々な表現を盛り込めるため、誇大表現が生じやすい媒体です。
キャッチコピーとリスク表示のバランス
NG例
ページ上部に大きく「月利30%達成!」「資産が確実に増える」などの断定的なキャッチコピーを表示し、リスク情報はページ最下部の小さな文字で記載。
改善ポイント
- キャッチコピーの近くにリスク情報を配置する
- リスク情報は読みやすい文字サイズで表示する
- 「当社の過去1年間の実績では~」など、実績の条件や期間を明記する
- 「資産が確実に増える」のような断定的表現を避け、「資産形成を目指す」など目標を示す表現に変更する
LP作成時は、魅力的な表現を追求するあまり、リスク情報や条件が後回しにならないよう注意が必要です。
バナー広告での誇大表現と改善ポイント
バナー広告は表示スペースが限られているため、簡潔でインパクトのある表現が求められますが、それが誇大表現につながりやすい面もあります。
スペース制約下での表示バランス
NG例
「年利10%!」「手数料0円!」などのメリットのみを強調し、リスク情報や条件の記載がない。
改善ポイント
- 小さなバナーでも「条件あり」「リスクあり」などの文言を入れる
- バナーの中で条件や注意書きを表示できない場合は、クリック後のランディングページの冒頭部分で明確に表示する
- 「年利10%(過去5年平均)」など、簡潔でも条件が分かる表現を工夫する
- 極端な強調表現(「驚異の」「破格の」など)を避ける
バナー広告では限られたスペースの中でも、誤解を与えない表現を心がけることが重要です。特にリスク情報や条件は省略せず、簡潔でも必ず表示するよう注意しましょう。
動画広告での誇大表現と改善ポイント
動画広告は視聴者の感情に訴える力が強い一方、一度流れてしまうと見直しができないというデメリットもあります。特に金融商品の動画広告では以下の点に注意が必要です。
ナレーションとテロップのバランス
NG例
ナレーションでは「月々5,000円から始められる」と利点を強調するのみで、リスク情報はナレーションなしの小さなテロップでしか表示しない。
改善ポイント
- 重要なリスク情報はナレーションでも伝える
- テロップは十分な表示時間と読みやすいサイズで表示する
- 「投資にはリスクがあります」などの基本的な注意喚起を動画内で複数回表示する
- 動画の最後に必ず注意事項のまとめを表示する
動画広告では、視聴者が一度見ただけで記憶に残る表現が多用されるため、その分リスク情報や条件も明確に伝わるよう工夫することが重要です。
SNS広告での誇大表現と改善ポイント
SNSは拡散性が高く、限られた文字数や画像内で情報を伝える必要があるため、誇大表現が生じやすい媒体です。
文字数制限下での表現
NG例
「投資で月10万円の副収入!」「今日始めれば翌月から配当金!」など、メリットだけを強調した短文。
改善ポイント
- 短文でもリスク情報を含める(「投資にはリスクがあります」など)
- 「詳細はプロフィールリンクから」など追加情報への誘導を入れる
- メリット表現も「可能性があります」「目指せます」など断定を避ける
- 複数投稿を活用し、メリットとリスクをバランスよく伝える
SNSは特に若年層へのリーチが高いため、金融リテラシーが十分でない層に対する配慮も必要です。また、プラットフォームごとに広告ポリシーが異なる場合もあるため、各SNSの規定も確認しておきましょう。
以上、各媒体における誇大表現と改善ポイントを紹介しました。媒体の特性を理解し、その制約の中でもバランスの取れた表現を追求することが、金融広告の信頼性を高め、結果的に顧客からの信頼獲得につながります。
誇大表現になりやすい広告表現の特徴
金融広告で誇大表現として指摘されやすい要素には共通パターンがあります。これらは効果的なマーケティング手法に見えますが、適切な根拠や条件提示がなければ規制対象となります。ここでは特に注意が必要な表現と対処法を解説します。
No.1や最短表記のリスクと対処法
「No.1」「業界最高水準」「最短」などのランキングや優位性を示す表現は、消費者の注目を集める効果がある一方で誇大広告のリスクも高いものです。
主なリスク
- 比較対象や調査条件が不明確
- 部分的なデータだけで全体を代表させる
- 最新性の欠如や条件の非表示
- 特殊なケースの一般化
効果的な対処法
No.1や最短表記を使用する際は、調査時期・調査主体・比較対象・条件を具体的に明示することが必須です。
自社調査の場合はその旨を明記し、できるだけ第三者機関による客観的データを用いるよう心がけましょう。また、定期的なデータの更新と最新性の確保も重要です。
金融広告での口コミ・体験談の注意点
顧客の体験談や口コミは金融商品の価値を伝える有効な手段ですが、誤用すると誇大広告となるリスクがあります。
主なリスク
- 架空または脚色された体験談
- 極端な成功例のみの紹介
- 体験談の日付や条件の非表示
- 個人的見解の一般化
効果的な対処法
体験談を使用する際は、実在の顧客の実際の体験のみを用い、属性・期間・条件を明記します。成功例だけでなく平均的な体験も含め、バランスの取れた選定を行いましょう。また、個人の感想であり成果を保証するものではないことを明記することが重要です。
実績表示の誇大化を防ぐ方法
運用実績やパフォーマンスデータは金融商品の魅力を伝える重要な要素ですが、表示方法によっては実態より良く見せてしまう「誇大化」のリスクがあります。
主なリスク
- 好調だった期間のみを選択的に表示
- グラフの縦軸操作による視覚的誇張
- 手数料等コスト控除前の数値のみの表示
- 将来予測と過去実績の区別の不明確さ
効果的な対処法
実績表示は、十分な長さの期間(最低1年以上)を設定し、グラフの縦軸はゼロから始めることが基本です。
総リターンだけでなく手数料・税金控除後の実質リターンも示し、過去実績と将来予測を明確に区別しましょう。上昇率だけでなく最大下落率も併記することで、リスクの実態も伝えます。
金融広告においてこれらの表現要素を使用する際は、客観的根拠の提示、条件の明示、バランスの取れた情報提供が不可欠です。広告の訴求力を維持しながらも誤解を招かない表現を追求することが、コンプライアンス遵守と顧客信頼の両立につながります。
金融広告審査に通すためのチェックフロー
金融広告の審査は厳格で、一度差し戻されると修正・再提出に時間がかかり、キャンペーンのスケジュールに影響を与えかねません。本章では、社内審査から自主規制団体、金融庁の監視まで、スムーズに審査を通過するためのプロセスとチェックポイントを解説します。
表現審査の基本ステップ
金融広告の表現審査を効率的に進めるための基本ステップを以下に示します。このプロセスは、企画段階から広告公開に至るまでの流れを網羅しています。
①企画段階での事前確認
広告制作の初期段階で、規制対応の基盤を整えることが重要です。
- 対象商品の規制区分を確認する(金融商品取引法、保険業法、銀行法など)
- 過去の類似広告や競合他社の表現方法を参考にする
- 訴求ポイントが規制に抵触しないか事前に確認する
この段階で問題点を把握しておけば、後工程での大幅な修正を避けられます。
②制作段階でのセルフチェック
広告素材を制作する段階で、以下のセルフチェックを行います。
- 各訴求ポイントに客観的な根拠があるか
- リスク情報と利益情報のバランスが取れているか
- 断定的表現や誤解を招く表現がないか
- 必要な注意書きや条件表示が含まれているか
制作者自身が基本的なコンプライアンスチェックを行うことで、審査の効率が高まります。
③部門内レビュー
マーケティング部門内での横断的なレビューを行います。
- 複数の目で表現の妥当性を確認する
- 消費者目線での誤解の可能性を検討する
- 過去の審査での指摘事項と照らし合わせる
異なる視点からのチェックにより、制作者が見落としがちな問題点を発見できます。
④社内審査(正式審査)
コンプライアンス部門や法務部門による正式な社内審査を受けます。
- 広告審査申請書と必要書類を提出する
- 審査基準に基づく厳格なチェックを受ける
- 指摘事項に対して速やかに対応する
社内審査は自主規制団体や監督官庁の視点を先取りしたチェックであり、ここでの承認は重要です。
⑤自主規制団体による審査(必要な場合)
商品やキャンペーンの規模によっては、自主規制団体による事前審査が必要です。
- 日本証券業協会、投資信託協会などの該当団体に審査申請を行う
- 審査基準に沿った資料を準備する
- 修正指示があれば迅速に対応する
自主規制団体の審査は、業界標準への適合性を確認する重要なステップです。
⑥広告掲載後のモニタリング
広告掲載後も継続的にチェックを行います。
- 消費者からのフィードバックを収集する
- 市場環境や規制変更に応じて表現を見直す
- 監督当局からの新たな指針に注意を払う
掲載後のモニタリングは将来の広告制作にも役立つ重要なプロセスです。
審査プロセス効率化のポイント
- 過去の審査指摘事項をデータベース化して参照する
- 定型的な注意書きや免責事項をテンプレート化しておく
- 審査スケジュールに余裕を持たせる
このような段階的なチェックプロセスを導入することで、金融広告の審査通過率を高め、効率的なマーケティング活動が可能になります。
NG表現の確認用チェックリスト
金融広告の審査をスムーズに通過するために、以下のチェックリストを活用しましょう。各項目をクリアすることで、誇大表現やコンプライアンス違反のリスクを大幅に減らすことができます。
1. 断定的表現のチェック
□ 「必ず」「確実に」「絶対」などの断定的表現を使用していないか
□ 「儲かる」「利益が出る」などの表現に条件や注意書きを付けているか
□ 将来の運用成果や相場動向について断定していないか
□ 「安全」「安心」という表現を無条件で使用していないか
□ 「有利」「お得」などの表現に具体的な根拠を示しているか
2. リスク情報の表示チェック
□ 元本割れのリスクがある商品は、そのリスクを明記しているか
□ リスク情報がメリット表示と同等以上の文字サイズ・明瞭さで表示されているか
□ リスク情報が商品説明の近くに配置されているか
□ 手数料や費用についての情報が明確に示されているか
3. 比較表現のチェック
□ 「最高」「最低」「No.1」などの最上級表現に根拠を示しているか
□ 比較の時期、対象、条件が明記されているか
□ 調査機関や情報源が明示されているか
□ 自社に有利な項目だけを選んだ恣意的な比較になっていないか
4. 実績表示のチェック
□ 過去の実績と将来の予測が明確に区別されているか
□ 「過去の実績は将来の成果を保証するものではありません」という注意書きがあるか
□ 特定期間のみを恣意的に選んだ実績表示になっていないか
□ 手数料等コスト控除後の実質リターンも示されているか
5. 限定表現・緊急性表現のチェック
□ 「期間限定」「数量限定」の表現に具体的な期間や数量を示しているか
□ 「今だけ」「急げ」などの緊急性を煽る表現が誇張になっていないか
□ 限定条件が事実に基づいているか
□ キャンペーン終了後の条件も明示されているか
6. 体験談・推薦文のチェック
□ 実在の顧客の実際の体験談であるか
□ 「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」という注意書きがあるか
□ 極端な成功例のみを選んでいないか
□ 体験談提供者の属性や利用条件が明記されているか
7. 専門用語・難解な表現のチェック
□ 専門用語に説明を付けているか
□ 一般消費者が理解できる平易な表現を使用しているか
□ 略語や業界用語を不用意に使用していないか
□ 誤解を招く比喩や例えを使用していないか
8. 総合チェック
□ 全体として誤解を招かない表現になっているか
□ 必要な法定表示事項(金融商品取引業者名、登録番号など)が含まれているか
□ 過去の審査で指摘された項目が改善されているか
□ 最新の法規制や自主規制に準拠しているか
□ 社内の広告ガイドラインに沿っているか
このチェックリストは、金融広告の主な審査ポイントを網羅していますが、商品や媒体によって追加のチェックが必要な場合もあります。社内の広告審査基準や自主規制団体のガイドラインと併せて活用することで、審査通過率を高めることができるでしょう。
仕組預金の有利誤認広告に関する行政処分事例
大手金融機関の仕組預金の広告表示が「有利誤認」に該当するとして公正取引委員会から排除命令を受けました。この事例では、デリバティブを組み込んだ金融商品(仕組預金)の広告において、リスク情報を適切に表示せず、利益面だけを強調した表現が問題となりました。
問題となった主な広告表現
- 高金利である点のみを強調し、為替リスクによる元本割れの可能性を小さな文字で表示
- 「年率○%」の表示を大きく目立たせ、条件付きであることを分かりにくく表示
- 銀行側に有利な特約条件の説明を目立たない場所に配置
これを受けて、全国銀行公正取引協議会は同年4月に「仕組預金にかかる表示について」というガイドラインを公表しました。
行政処分を防ぐための対策
上記のような事例を踏まえ、誇大表現による行政処分を防ぐための具体的な対策を以下に示します。
| 1. 金融商品のリスク情報の適切な表示 | 2. 特約条件の明確な表示 |
|---|---|
| リスク情報は利点と同等以上の文字サイズで表示 | 銀行側が選択権を持つ特約は明確に表示 |
| リスク情報を広告の目立つ場所に配置 | 満期日変更などの条件を具体的に説明 |
| 最悪のシナリオも明示(元本割れの可能性など) | 中途解約時のペナルティを明示 |
| 3. 表示バランスの確保 | 4. 内部チェック体制の強化 |
|---|---|
| 利益面とリスク面を同等に表示 | 法務・コンプライアンス部門による事前審査の徹底 |
| 「高金利」などの表現には必ず条件を付記 | 外部専門家(弁護士など)によるチェック |
| 誤解を招く強調表現を避ける | 広告担当者への定期的な研修実施 |
広告効果を追求するあまり、リスク情報を軽視すると行政処分のリスクが高まります。広告担当者は、「消費者が誤解しないか」という視点で常に広告表現を点検することが重要です。
金融広告の誇大表現に関するよくある質問
ここでは、金融広告の誇大表現に関するよくある質問を紹介します。
「必ず」「絶対」などの断定表現は全てNG?
基本的に金融商品の将来のパフォーマンスや成果について「必ず」「絶対」などの断定的表現は避けるべきです。ただし、以下のケースでは限定的に使用可能です。
- 事実に基づく客観的な内容(「お申込みには必ず本人確認書類が必要です」)
- 手続きに関する確定事項(「口座開設には絶対にマイナンバーの提示が必要です」)
- 条件付きで確定している事項(「満期まで保有すれば、預入元本は必ず円でお返しします」)
特に投資性商品のリターンや市場動向、為替レートなど不確実な事柄については、「必ず利益が出る」「絶対に元本割れしない」といった表現は誇大広告となるため使用できません。
実績や利回りはどこまで細かく注記すべき?
実績や利回りの表示には、実績の計測期間(「2020年1月~2024年12月の5年間」など)、手数料・税金控除前か後か(実質リターン)、計算方法(年率換算か単純合計か)、特殊条件や前提(「円安局面での実績」など)、そして将来の成果を保証するものではない旨の注意書きを明記すべきです。
適切な情報開示により、投資家が誤解なく判断できるようにすることが重要です。
まとめ:金融広告は根拠と明示でリスク回避
本記事では、金融商品広告における誇大表現の規制、様々な商品・媒体別のNG表現と修正例、審査フローやチェックリスト、そして行政処分事例について詳しく解説してきました。
金融広告は一般商品と異なり、目に見えない価値や将来の不確実なリターンを扱うため、より慎重な表現が求められます。特に「必ず儲かる」といった断定的表現や、リスク情報の不十分な表示は誇大広告として規制対象となります。
金融広告を適切に行うための重要ポイントは以下の通りです。
- 客観的根拠に基づいた表現を使用し、その出典や調査条件を明示する
- リスク情報をメリットと同等以上の明瞭さで表示する
- 断定的表現を避け、可能性や目標として表現する
- 特殊な条件や前提を小さな文字で隠さず明確に示す
- 実績表示は十分な期間と手数料控除後の実質リターンも示す
- 媒体特性に応じた表現方法を工夫し、スペースが限られていても重要情報は省略しない
- 社内審査体制を整備し、定期的なモニタリングを実施する
「効果的なマーケティング」と「コンプライアンス遵守」は対立するものではありません。むしろ、正確でバランスの取れた広告表現は、顧客の適切な判断を助け、後のトラブルを防止するという点で、企業にとっても顧客にとっても価値があります。
金融広告の本質は「誇大に見せること」ではなく「正確な情報提供」にあります。根拠を示し、条件を明示し、リスクと利益のバランスを取った広告表現が、持続可能な金融ビジネスの基盤となるのです。