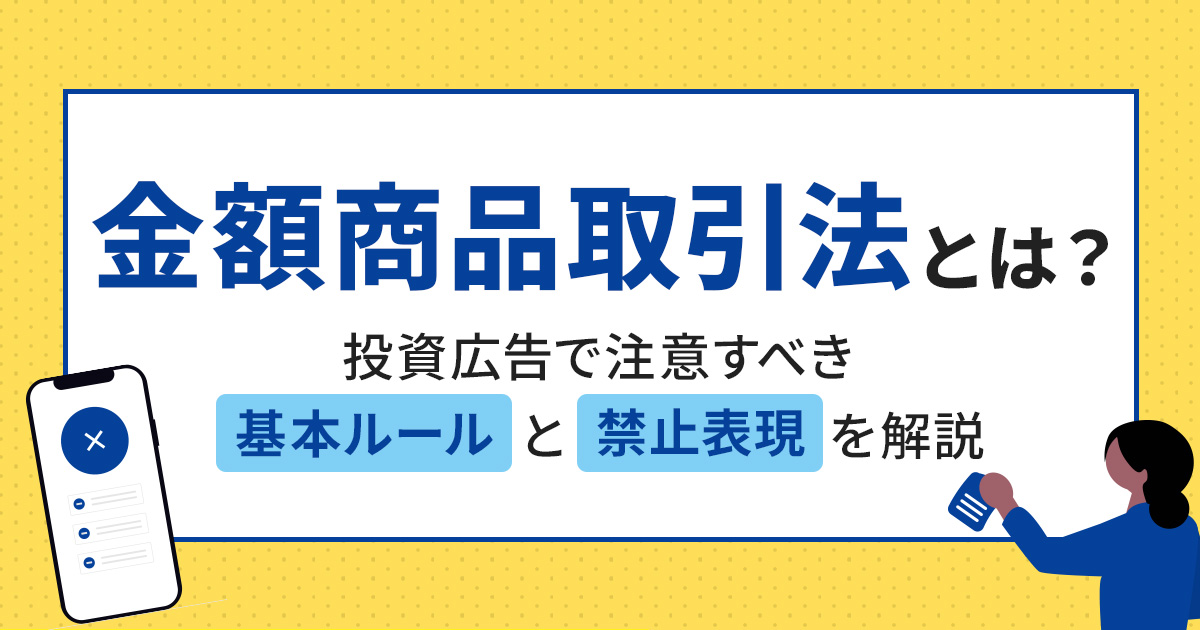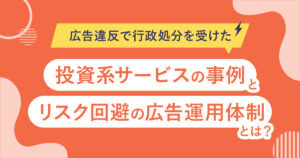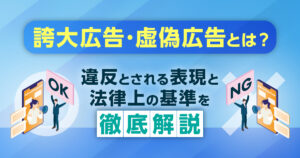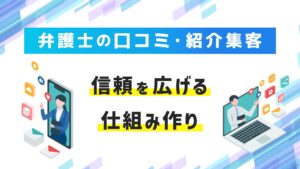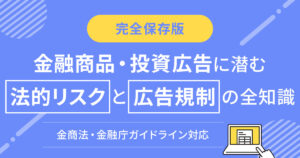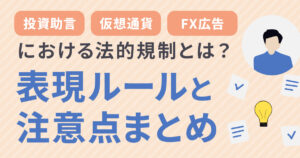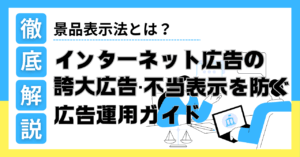「この広告表現、本当に大丈夫かな?」
「金融商品の広告って、特別なルールがあるって聞いたけど…」
金融商品やサービスの広告担当者であれば、このような不安を抱えたことがあるのではないでしょうか。一般的な広告と異なり、金融商品の広告には金融商品取引法(金商法)という特別な法律が適用されます。
この規制を知らずに広告を出稿すると、思わぬところで法令違反となり、厳しい処分を受けるリスクがあるのです。
本記事では、ネット広告担当者が知っておくべき金融商品取引法の基本から、投資広告における禁止表現、Web・SNS広告での注意点まで、わかりやすく解説します。
「何が言ってよくて、何がダメなのか」「どんな表現が禁止されているのか」など、実務で即役立つ知識を身につけることができるでしょう。
金融広告のコンプライアンスを守りながら、効果的なマーケティング活動を行うためのポイントをマスターし、安心して業務に取り組めるようになりましょう。
金融商品取引法(金商法)の基本を理解しよう
金融商品取引法(以下、金商法)は、投資家を保護し、金融・資本市場の健全な発展を促進するための重要な法律です。
広告担当者として金融商品の宣伝を行う際には、この法律の基本を理解することが必須となります。まずは金商法の背景と規制対象について押さえておきましょう。
金商法が制定された背景と「投資家保護」の目的
金商法は、2006年に証券取引法を全面改正する形で制定され、2007年9月に施行されました。この法改正が行われた背景には、次のような社会的要因があります。
まず、金融技術の発展により多様な金融商品が登場し、従来の証券取引法では対応しきれなくなったことが挙げられます。金融商品によってバラバラだった法体系を横断的にまとめ、規制の隙間ができないようにする必要がありました。
この法律の最大の目的は、「利用者保護を徹底し、取引の公正性・透明性を確保して市場に対する国民の信頼を確保する」ことにあります。
金商法で規制される主な金融商品
金融商品取引法の規制対象は非常に幅広く、主に投資性のある金融商品が対象となっています。具体的には以下のような商品が含まれます。
- 有価証券(国債証券、地方債証券、社債券、株券など):従来から証券取引法で規制されていた伝統的な金融商品です。
- デリバティブ取引:先物・先渡取引、オプション取引、スワップ取引、クレジット・デリバティブ(CDS取引など)が含まれます。
- 投資性のある預金・保険商品:仕組預金、外貨預金、変額年金保険など、投資性のある金融商品も規制の対象となっています。
- FXや差金決済取引:FX(外国為替証拠金取引)やCFD(差金決済取引)もデリバティブ取引の一種として規制対象です。
金融広告担当者としては、これらの金融商品に関する広告を作成する際に、金商法の規制を正確に理解し、コンプライアンスを守ることが極めて重要です。
第一章 総則
引用:金融商品取引法 | e-Gov 法令検索
(目的)
第一条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
金商法における広告規制の基本ルール
金融商品取引法(金商法)では、投資家保護の観点から、金融商品の広告に関する厳格なルールが定められています。広告担当者は、これらのルールを理解し遵守することで、法令違反のリスクを回避し、投資家に適切な情報を提供することができます。
広告に適用される金商法の基本原則
金商法における広告規制の基本原則は、大きく分けて「表示義務」と「禁止行為」の2つから構成されています。
1. 表示義務(必ず記載すべき事項)
金商法第37条では、金融商品取引業者等が広告を行う際に、必ず表示しなければならない事項が定められています。具体的には以下の項目です。
- 金融商品取引業者等の商号、名称または氏名
- 金融商品取引業者等である旨およびその登録番号
- 金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
さらに、政令や内閣府令では以下のような具体的な記載事項が定められています。
- 手数料等の費用に関する事項
- 損失が生じるおそれがあるときは、その旨
- 元本割れのリスクがある場合はその旨と理由
- 金利・為替・株式相場等の変動により損失が生じるおそれがある旨
- 発行者の業務や財産状況の変化により損失が生じるおそれがある旨
これらの情報は、投資家が金融商品のリスクと費用を正確に理解するために必要不可欠な情報です。また、表示の方法についても、文字の大きさや表示位置に関する規定があり、投資家が容易に認識できるように配慮することが求められます。
2. 禁止行為(してはならない表現)
金商法では、以下のような広告表現が禁止されています。
金融商品取引業者等が行う金融商品取引業の内容について広告を実施するときは、利益の見込み、契約の解除に関する事項、損失負担・利益保証に関する事項、損害賠償額の予定に関する事項などについて「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と規制されています。
金融商品取引業者等が広告等をする場合にリスク情報(元本損失・元本超過損が生じるおそれがある旨・その直接原因の指標・その理由)や顧客が支払うべき手数料等などの所定事項の表示義務を課すとともに、いわゆる虚偽・誇大広告等を禁止しています。
具体的には、以下のような表現が禁止されています。
- 虚偽の表示
- 不確実な事項についての断定的判断の提供
- 誤解を生じさせるような表示
- 利益を保証するような表示
- リスクを著しく軽視した表示
広告掲載前に必ず確認すべき項目
金融商品の広告を掲載する前に、以下の項目を必ずチェックしましょう。
| 法定表示事項の確認 |
|---|
| 業者の商号・名称・登録番号が正確に記載されているか |
| 手数料やリスク情報など、法令で定められた必須表示事項が適切に記載されているか |
| 文字の大きさや配置が法令の要件を満たしているか |
| 表現内容の適正性確認 |
|---|
| 断定的な表現や保証を匂わせる表現がないか |
| 利益が出ることを確約するような表現がないか |
| リスクや損失の可能性が適切に説明されているか |
| 比較広告の場合、その根拠が明示されているか |
| 専門用語が適切に説明されているか |
| 最新の法令・ガイドラインの確認 |
|---|
| 金商法や関連法令の改正に対応しているか |
| 金融庁や業界団体から出されている最新のガイドラインに準拠しているか |
| 自主規制団体(日本証券業協会など)のルールに従っているか |
広告等とは、一般的な「広告」を指すだけではなく、インターネットのホームページや投資情報の提供、メールマガジン等も含みます。
このように、広告の概念は幅広く解釈されているため、SNSでの投稿やメールマガジンなどの媒体も規制の対象になることを認識しておく必要があります。
投資広告で絶対に避けるべき禁止表現と事例
金融商品取引法(金商法)では、投資家保護の観点から、特定の広告表現が厳しく禁止されています。広告担当者としては、これらの禁止表現を正確に理解し、コンプライアンス違反を避けることが重要です。ここでは、特に注意すべき禁止表現と具体的な事例を解説します。
誇大広告や断定的表現の禁止
金商法では、事実に反する表示や誤解を招くような表現を厳しく規制しています。特に「断定的判断の提供」は禁止行為の代表例です。
禁止される表現の具体例は以下になります。
将来の利益を断定する表現
- 「必ず利益が出る」「確実に儲かる」
- 「○%の利回りを保証」「間違いなく値上がりする」
根拠のない優位性を主張する表現
- 「業界No.1の運用実績」(客観的な根拠なし)
- 「他社を圧倒する運用チーム」(比較の根拠不明)
リスクを軽視させる表現
- 「リスクは極めて小さい」
- 「ほぼ安全な投資方法」
金融商品取引業者等が行う広告では、利益の見込み、契約の解除に関する事項、損失負担・利益保証に関する事項、損害賠償額の予定に関する事項などについて「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と規制されています。
実際の処分事例
- A証券会社は、投資信託の広告で「安定した高利回り」と表示し、リスクが小さいかのように表現したことで行政処分を受けました。
- B投資顧問会社は、「当社の投資助言サービスを利用した顧客の9割以上が利益を得ている」という事実と異なる表現を用いて業務改善命令を受けました。
利益保証や元本保証を匂わせる表現の禁止
金融商品は基本的に元本保証がなく、将来の利益も確約できないものです。そのため、そのような保証や確約を匂わせる表現は厳格に禁止されています。
禁止される表現の具体例は以下になります。
元本保証を暗示する表現
- 「元本割れの心配はありません」
- 「投資元本は確保されます」
利益保証を暗示する表現
- 「毎月○万円の収入を確保」
- 「年利○%を実現します」
損失補填を暗示する表現
- 「損が出た場合は当社が責任を持ちます」
- 「損失が発生した場合は次回の投資で取り戻せます」
「元本保証」や「必ず儲かる」という言葉で出資を集めることは金融商品取引法上、禁止されています。このようなフレーズを謳っている会社は、詐欺や法律違反をしている可能性が高いといえます。
実際の処分事例
- D投資会社は「元本保証型投資信託」という名称を用いて、実際には元本保証のない商品を販売したとして業務停止命令を受けました。
- E証券会社は「最低でも年5%の配当が期待できる」と断定的な表現を用いて投資家を勧誘し、行政処分の対象となりました。
重要事項を記載しない不十分な広告表現
投資判断に影響を与える重要事項を記載しないことも、禁止されています。投資家が正確な判断ができるよう、リスクや手数料などの重要情報は必ず明記する必要があります。
記載すべき重要事項の例
| リスク情報 | 費用・手数料情報 |
|---|---|
| 元本割れリスク | 購入時手数料 |
| 為替リスク(外貨建て商品の場合) | 運用管理費用(信託報酬) |
| 信用リスク(発行体の倒産リスクなど) | 解約手数料 |
| 流動性リスク(換金制限や市場動向による売買困難性) | その他かかる費用 |
| 取引条件 | 運用者・発行者情報 |
|---|---|
| 最低投資金額 | 運用会社の名称・登録番号 |
| 契約期間・解約条件 | 資産管理の方法 |
| クーリングオフの有無・条件 | 運用担当者の変更可能性 |
| 中途解約時のペナルティ | 運用実績の算出方法 |
不適切な広告事例
F投資顧問会社は、投資助言サービスの広告で「月額1万円から始められる」と表示しながら、別途かかる高額な成功報酬について小さな文字で記載し、実質的に見えないようにしていたことで行政指導を受けました。
投資広告においては、投資家保護の観点から禁止表現を厳守し、誠実で透明性のある情報提供を心がけることが、法令遵守だけでなく、長期的な信頼関係の構築にもつながります。
Web・SNS広告で特に注意すべきポイント
インターネットやSNSの普及により、金融商品の広告・勧誘手法も多様化しています。デジタル媒体特有のリスクや注意点を理解し、金融商品取引法に則った適切な広告運用が求められます。
SNSでの投資勧誘や広告の注意点
SNSを活用した金融商品の広告や勧誘は、その手軽さと拡散力から急速に増加していますが、同時に様々な問題も発生しています。
SNSにおける広告規制の適用範囲
SNS上の投稿やメッセージであっても、金融商品の勧誘に該当する場合は金商法の規制対象となります。
- 投資商品の紹介ポスト
- 運用実績の報告ツイート
- 投資セミナーの告知
- グループチャットでの投資勧誘
SNS特有の投資詐欺への警戒
近年、SNSを通じた投資詐欺が急増しています。金融庁は「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」を設置し、対策を強化しています。特に注意すべき手口は以下の通りです。
- 著名人になりすました投資広告
- 「必ずもうかる投資方法」などの誇大広告
- マッチングアプリを通じた投資勧誘(ロマンス投資詐欺)
金融商品の広告主としては、企業の公式アカウントであることを明確に表示し、会社名・登録番号などの基本情報を明示することで、詐欺と誤認されるリスクを軽減できます。
Web広告における表示義務と必要記載事項
Web広告では、SNSよりも多くの情報を掲載できますが、その分詳細な表示義務が課されます。
Web広告における必須記載事項
金商法第37条に基づき、以下の事項を必ず記載する必要があります。
- 事業者情報
- 金融商品取引業者の商号・名称・登録番号
- 手数料・リスク情報
- 手数料の概要
- 元本割れリスクの有無
- 市場変動による損失の可能性
Web広告における表示方法のルール
- リスク情報は、広告の最大文字と同等の大きさで表示
- 小さな文字でページの隅に表示する不適切な表示は禁止
- バナー広告は、クリック先に必要事項を記載
Web広告特有の注意点
Web広告特有の注意点としては、効果的なランディングページの設計が重要です。重要情報はユーザーがスクロールせずに見える位置に配置し、リスク情報と利益情報のバランスを考慮したレイアウトにすべきです。
また、アフィリエイト広告についても、その内容は金融商品取引業者の責任となるため、適切に管理・監督する必要があります。
Web・SNS広告は効果的なマーケティング手段ですが、適切なコンプライアンス体制のもとで運用することが不可欠です。法令遵守と顧客保護を両立した広告展開を心がけましょう。
金商法に違反した際のリスクと処分事例
金融商品取引法(金商法)に違反した場合、企業や個人は厳しい行政処分や刑事罰の対象となります。広告担当者として法令を遵守することは、罰則回避と投資家の信頼維持のために極めて重要です。
行政処分や罰則の具体例
金商法違反に対する処分は、違反の内容や程度によって様々な形態をとります。主な処分の種類は以下の通りです。
行政処分
金融庁は金商法違反を行った金融商品取引業者に対して行政処分を行う権限を持っています。
「業務改善命令」では、広告表現の是正や社内管理体制の強化、役職員への研修実施などが命じられ、改善報告書の提出が義務付けられます(金商法51条)。
「業務停止命令」は、違反の程度が重い場合に特定業務や全業務の停止が命じられるもので、期間は違反の重大性に応じて決定されます(金商法52条)。
最も重い「登録取消」は、金融商品取引業の登録を取り消され、業務継続が不可能となる処分です。
課徴金制度
課徴金は、不公正取引や虚偽記載などへの行政上の措置で、違反行為による経済的利益を剥奪する目的があります。金額は数万円から数百億円に及び、過去5年以内の再犯は1.5倍に加算されます。
刑事罰
無登録営業には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」またはその両方、法人には「5億円以下の罰金」が科されます。虚偽広告には1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が課されます。
違反事例から学ぶ注意ポイント
3つの処分事例から、金融商品の広告担当者が特に注意すべきポイントを見ていきましょう。
1.誤解を招く広告表現の事例
ある金融商品取引業者が「安全で確実な投資」と表現し、元本保証を暗示した広告を掲載。実際には元本割れリスクがある商品でしたが、このリスク情報を目立たない形で記載していました。金融庁は金商法第37条違反と認定し、業務改善命令を発出しました。
学ぶべきポイント
- リスク情報は広告の最大文字と同等の大きさで表示する
- 「安全」「確実」などの断定的表現は避ける
- 元本割れリスクを明確に伝える
2.重要事項の不記載に関する事例
ある証券会社が「手数料無料」と宣伝したものの、実際には信託報酬などの間接的手数料が発生し、この情報が小さな文字で記載されていました。金融庁は重要事項の不十分な表示として業務改善命令を出しました。
学ぶべきポイント
- 「無料」表現使用時は条件や例外を明確表示
- 間接的コストも含めたトータルコストを明示
- 注釈は目立つ場所に配置
3.インサイダー取引の事例
ある会社役員が自社の第三者割当増資の未公表情報を基に自社株購入、情報公表後の株価上昇時に売却し利益獲得。証券取引等監視委員会は98万円の課徴金納付命令を勧告しました。
学ぶべきポイント
- 重要情報管理と取引規制の徹底
- 情報アクセス権限者への教育が重要
- 社会的信用失墜は甚大
企業における予防策
金商法違反を防止するためには、企業として適切な体制整備が重要です。まず広告審査体制としては、広告掲載前のコンプライアンス部門による内容チェック、法務部や外部専門家によるリーガルチェック、そして審査履歴の文書化と保管が必要です。
また、広告担当者への定期的な法令研修、事例研究を通じた実践的な教育、最新の法改正動向の共有など、社内研修の実施も欠かせません。
金融商品の広告は投資家の投資判断に大きな影響を与えるため、正確性と誠実性が特に求められます。
金融商品広告でコンプライアンスを守るためのチェックリスト
金融商品の広告担当者が金融商品取引法(金商法)を遵守し、適切な広告を作成するためのチェックリストを以下に示します。このチェックリストを活用することで、法令違反のリスクを低減し、投資家に適切な情報を提供することができます。
1. 基本情報の記載確認
□ 金融商品取引業者等の商号・名称が正確に記載されているか
□ 金融商品取引業者である旨と登録番号が明記されているか
□ 所属する金融商品取引業協会名が記載されているか
□ 問い合わせ先(電話番号等)が明記されているか
□ 苦情・相談窓口についての情報が記載されているか
2. リスク情報の開示確認
□ 元本割れリスクがある場合、その旨を明確に記載しているか
□ 元本を上回る損失が生じる可能性がある場合、その旨を記載しているか
□ 市場リスク(金利・為替・株価変動等)についての説明があるか
□ 信用リスク(発行体の経営・財務状況変化)についての説明があるか
□ その他商品特有のリスクが適切に説明されているか
□ リスク情報が広告内の最大文字と著しく異ならない大きさで表示されているか
3. 手数料・費用に関する記載確認
□ 顧客が支払う手数料等の金額・計算方法が記載されているか
□ 手数料が表示できない場合、その理由が説明されているか
□ 間接的に負担する費用(信託報酬等)についても記載されているか
□ 「無料」「ゼロ」等の表現を使用する場合、条件や例外が明示されているか
□ 手数料等の表示が分かりやすく、誤解を招かない方法で行われているか
4. 禁止表現の回避確認
□ 利益の確実性を示唆するような断定的表現がないか (例:「必ず儲かる」等)
□ 元本保証があるかのような誤解を招く表現がないか (例:「元本安全」等)
□ リスクを過小評価するような表現がないか (例:「リスクは極めて小さい」等)
□ 根拠のない比較優位性を主張していないか (例:「業界No.1」等の根拠不明な表現)
□ 投資判断を誤らせるような誤解を招く表現がないか
5. 数値・データの表示確認
□ 過去の運用実績を示す場合、適切な期間のデータを使用しているか
□ データの出所・根拠が明記されているか
□ 過去の実績が将来の成果を保証するものではない旨の注意書きがあるか
□ グラフ・表などが誤解を招くような加工・編集をされていないか
□ 一部の有利な数値だけを恣意的に抽出していないか
□ 予想・シミュレーション結果を示す場合、前提条件が明記されているか
6. 広告表示方法の確認
□ 重要事項が適切な文字サイズ・色・位置で表示されているか
□ 注釈や但し書きが見えにくい場所や小さな文字で記載されていないか
□ リスク情報と利益情報のバランスが適切か
□ スクロールせずに見える位置(ファーストビュー)に重要情報があるか
□ 動画広告の場合、十分な視認時間と文字サイズが確保されているか
□ リスク情報を利益情報よりも小さく/目立たなく表示していないか
7. SNS・Web広告特有の確認事項
□ 文字数制限のあるプラットフォームでは、リンク先に必要事項を全て記載しているか
□ SNS広告であっても金商法の表示義務を免除されないことを理解しているか
□ インフルエンサーを起用した広告でも、金融商品取引業者としての表示責任があることを認識しているか
□ バナー広告は、クリック先のランディングページに必要事項を全て記載しているか
□ 「広告である」旨が明示され、ステルスマーケティングになっていないか
□ 短期間で大きな利益を得られるかのような表現で若年層を誘引していないか
8. 法令改正・ガイドライン対応確認
□ 最新の金商法改正内容を把握・反映しているか
□ 金融庁のガイドラインや監督指針の最新版を確認しているか
□ 所属する自主規制団体(日本証券業協会等)のルールに準拠しているか
□ 過去の行政処分事例から学ぶべき教訓を反映しているか
□ 広告チェック体制を定期的に見直し・更新しているか
9. 社内承認プロセスの確認
□ コンプライアンス部門による事前審査を受けているか
□ 法務部や外部専門家によるリーガルチェックを実施しているか
□ 審査履歴を文書化・保管しているか
□ 修正指示があった場合、適切に対応しているか
□ 広告の公開後も定期的にモニタリングを行う体制があるか
10. 対象顧客への配慮確認
□ 対象となる顧客層の知識・経験・財産状況に適した内容か(適合性の原則)
□ 複雑な商品の場合、専門用語に適切な説明を付しているか
□ 高齢者向けの広告では、特に分かりやすい説明を心がけているか
□ 若年投資家向けの広告では、リスク説明をより丁寧に行っているか
□ 特定の顧客層に誤解を与えるような表現がないか
このチェックリストを活用することで、広告担当者は金融商品取引法を遵守し、投資家に適切な情報を提供する広告を作成することができます。
また、社内のコンプライアンス体制強化にも役立ちます。チェックリストは定期的に見直し、法令改正や新たな事例に基づいて更新することが重要です。
金融商品広告に関するよくある質問
金融商品の広告を作成・掲載する際には、様々な疑問や懸念が生じることがあります。ここでは、特に多く寄せられる質問について回答します。
金融商品広告に掲載が義務付けられている情報はありますか?
はい、金融商品取引法(金商法)第37条に基づき、以下の情報を必ず掲載する義務があります。
1. 事業者に関する基本情報
- 金融商品取引業者等の商号、名称または氏名
- 金融商品取引業者等である旨および登録番号
2. 顧客の判断に影響を及ぼす重要事項
- 手数料・報酬などの合計額または計算方法
- 保証金の額(該当する場合)
- 金利等の変動による損失発生のおそれ
- 元本割れリスクがある場合はその旨と理由
- 元本を上回る損失の可能性
- 発行者の状況変化による損失の可能性
テレビCMやラジオCMなどでは、「金利等変動による損失発生のおそれ」と「契約締結前交付書面等を読むべき旨」の2点の表示で足りるとされていますが、誘導先のウェブサイト等では全情報の表示が必要です。
個人がSNSで投資情報を発信する際も金商法は適用されますか?
個人の投資情報発信でも、活動の性質によっては金商法が適用される場合があります。
金商法が適用される可能性がある場合
金商法は、有償で投資助言を行うなど金融商品取引業に該当する場合に適用され、この場合は登録が必要となります。
また、根拠のない噂や虚偽情報を広める「風説の流布」に該当する行為や、インサイダー情報の伝達・取引推奨行為、さらに相場操縦を目的とした情報発信を行った場合も金商法違反となる可能性があります。
金商法の適用が限定的または適用されない場合
一方で、単に個人的な投資経験や分析を無償で共有するだけの場合や、公開情報に基づいた客観的な分析・考察を共有するような場合は、一般的に金商法の適用は限定的か、適用されないことが多いでしょう。
個人でも「必ず儲かる」などの断定的表現や根拠のない噂の拡散は避け、情報の正確性や客観性を心がけるべきです。SNSでの投資詐欺的行為に対しては金融庁も対策を強化しています。
【まとめ】安全で効果的な金融商品広告のために
本記事では、金融商品取引法における広告規制の基本原則から、Web・SNS時代の広告の注意点、違反時のリスク、コンプライアンスチェックリストまで、金融商品広告に関する重要事項を詳しく解説してきました。
金融商品広告は投資家の判断に直接影響を与えるため、適切な情報開示と公正な表現が不可欠です。法令遵守は単なる義務ではなく、投資家との信頼関係構築の基盤となります。
金融商品広告を安全かつ効果的に活用するための重要ポイントを以下にまとめます。
- 金商法第37条の表示義務と禁止表現を正確に理解する
- リスク情報と利益情報のバランスを適切に保つ
- 断定的表現や誇大広告を厳に慎む
- Web・SNS広告の特性を理解し、適切な表示方法を選択する
- 社内の広告審査体制を確立し、定期的に見直す
- 最新の法令改正や行政処分事例から学ぶ
一見すると、これらの規制はマーケティング活動の制約や追加コストになるように思えるかもしれません。しかし、適切なコンプライアンス体制は法的リスクを回避するだけでなく、投資家の権利を尊重する企業姿勢を示すことにもつながります。
「効果的な広告活動」と「適切なコンプライアンス」は決して相反するものではなく、むしろ持続可能な金融ビジネスのために必要不可欠な要素です。法令遵守を基盤とした適切な広告活動は、投資家からの信頼獲得につながり、より健全な金融市場の発展に貢献します。