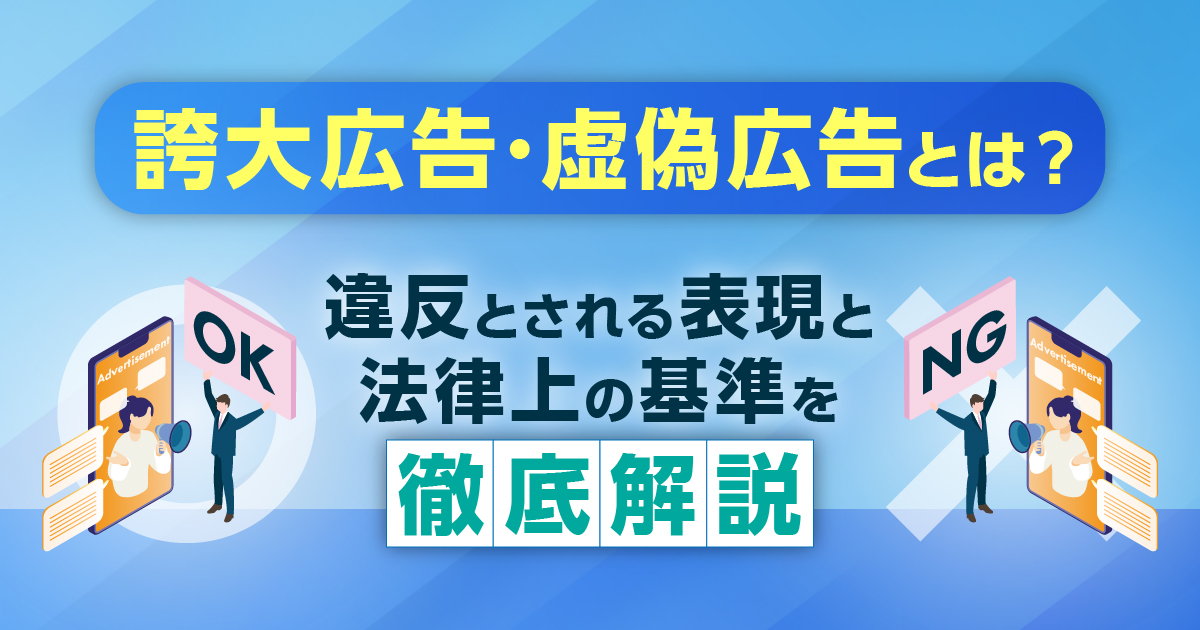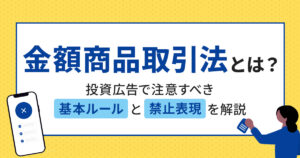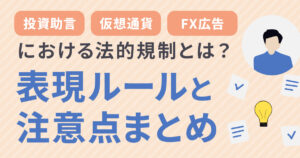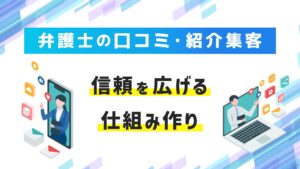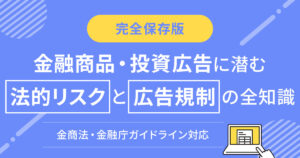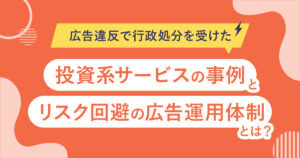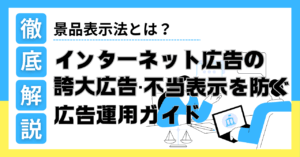「この表現は大丈夫?」「これって誇大広告になる?」
広告担当者なら、このような疑問や不安を抱えたことがあるのではないでしょうか。
広告表現は効果的であることが求められる一方で、法律の範囲内に収める必要があります。その境界線は時に曖昧で、判断に迷うケースも少なくありません。
特に近年、消費者庁による景品表示法の執行は厳格に行われており、SNS広告やインフルエンサーマーケティングなど新たな広告手法における規制も注目されています。
一度違反が認定されれば、経済的損失だけでなく、企業イメージの低下や信頼の喪失など、長期的な悪影響をもたらす可能性があるのです。
本記事では、誇大広告・虚偽広告の定義から違反となる具体的な表現例、判断基準、実際の処分事例まで徹底解説。さらに、実務担当者がすぐに活用できるチェックリストや社内体制の構築方法もご紹介します。
この記事を読めば、法律に抵触せず、かつ効果的な広告表現のバランスを取るためのポイントが理解できるでしょう。
誇大広告・虚偽広告とは?その定義と違い
広告担当者として「誇大広告」や「虚偽広告」という言葉を聞いたことがあるでしょうが、その明確な定義や両者の違いを正確に説明できる方は意外と少ないものです。
法的リスクを回避するためには、これらの概念を正しく理解することが不可欠です。
誇大広告の定義
誇大広告とは、商品やサービスの内容・効果・性能などについて、事実よりも著しく優良であると消費者に誤認させるような表現を用いた広告のことを指します。景品表示法では「優良誤認表示」と呼ばれ、第5条第1号に規定されています。
重要なポイントは「著しく」という部分です。広告においては、ある程度の誇張表現(いわゆるパフ)は許容されています。たとえば「最高の味わい」「驚きの効果」といった抽象的な表現は、一般消費者が社会通念上、誇張と理解できる範囲であれば問題とされないケースが多いのです。
しかし、「1週間で確実に5kg減量」「使用後すぐにシミが消える」など、具体的な数値や効果を断定的に表現し、それが事実と大きくかけ離れている場合は、誇大広告として規制の対象となります。
(不当な表示の禁止)
引用:不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov 法令検索
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
虚偽広告との違い
虚偽広告とは、端的に言えば「嘘の広告」です。存在しない商品やサービス、まったく事実と異なる効果や性能を謳うなど、広告内容に真実性がまったくない場合を指します。
誇大広告と虚偽広告の最大の違いは、「事実の有無」にあります。誇大広告は実際の商品やサービスが存在し、一定の効果や性能はあるものの、それを過大に表現しているケースです。一方、虚偽広告は最初から事実に基づかない、完全な虚偽の内容を含んでいます。
法的には、誇大広告は主に景品表示法の規制対象となりますが、虚偽広告はより悪質な場合、詐欺罪(刑法第246条)など、刑事罰の対象となることもあるのです。
違反広告が問題視される理由
違反広告が厳しく規制される理由は、主に以下の3つの観点から説明できます。
- 消費者保護の観点
誤った情報に基づいて購入判断をした消費者は、期待した効果や性能が得られず、経済的・時間的損失を被ります。特に健康食品や医薬品、美容サービスなどの分野では、身体的な悪影響を受けるリスクもあり、消費者の安全を脅かす可能性があります。 - 公正な競争環境の維持
虚偽・誇大な表現を用いた広告は、適正な表示を行っている事業者との間で不公平な競争を生じさせます。これにより市場の健全性が損なわれ、長期的には業界全体の信頼低下につながるおそれがあります。 - 企業の信頼性とブランド価値の毀損
違反広告を行った企業は、行政処分や罰則を受けるだけでなく、報道などを通じて社会的信用を大きく失います。一度失った消費者からの信頼を回復するには、長い時間と多大なコストがかかるのです。
このように、違反広告は単に法律違反というだけでなく、消費者、市場、そして企業自身にとっても大きな損失をもたらすものであり、広告業界全体の健全な発展を阻害する要因となっています。
だからこそ、広告担当者は法令遵守の視点を持ちながら、効果的かつ誠実な広告制作に取り組むことが求められるのです。
違反とされる広告表現の具体例
広告制作において、知らず知らずのうちに法令違反となるような表現を使用してしまうリスクは常に存在します。ここでは、過去の措置命令事例などを参考に、特に注意すべき表現や媒体別の留意点について解説します。
よくあるNGワード・NGフレーズ
景品表示法違反として指摘されやすい表現には、いくつかの共通するパターンがあります。以下に代表的なNGワード・フレーズを分野別に示します。
| 効果・性能の断定的表現 |
| ・「確実に」「絶対に」「必ず」「100%」などの断定的な言葉 ・「〇日で△kg減量」「即効性」など、具体的な期間と効果を約束する表現 ・「誰でも」「どんな人でも」など、個人差を無視した万能性を示す表現 |
| 比較表現 |
| ・「業界No.1」「最高」「最大」など、根拠なく優位性を主張する表現 ・「他社製品の〇倍効果的」など、比較データなしで具体的数値を用いる表現 ・「当社比」など、比較対象が不明確な表現 |
| 医学的・科学的表現 |
| ・「医学的に証明された」「臨床試験済み」など、不十分な根拠での科学的権威づけ ・「副作用なし」「リスクゼロ」など、安全性を過度に強調する表現 ・医薬品的な効能効果を暗示する表現(健康食品等での「治す」「改善する」など) |
| 希少性・限定性の表現 |
| ・「通常価格」が実際には存在しない割引表示 ・「限定」「特別」が事実と異なる場合 ・「完売間近」「残りわずか」などの虚偽の在庫状況 |
こうした表現は、単独では問題なくても、商品の種類や文脈によっては違反となる可能性があります。特に美容・健康・ダイエット関連商品では、厳しく判断される傾向があります。
媒体別に見る注意点
広告媒体によって、表現上の制約や注意点が異なります。主な媒体別のポイントを見ていきましょう。
| Webサイト・ランディングページ |
| ・ファーストビュー(最初に見える画面)だけでなく、スクロールして表示される部分も含めて全体で審査される ・「詳しくはこちら」などのリンク先も広告の一部とみなされる ・ユーザーレビューも事実に基づかないものは違反の対象となる ・打消し表示(※印の注釈など)が小さすぎたり、離れた場所にあると効果がないとみなされる |
| テレビCM・動画広告 |
| ・画面に表示される注釈が短時間すぎると認識できないと判断される ・ナレーションの速度が速すぎる場合も同様 ・視聴者が受ける印象全体で判断されるため、映像やBGMも含めた総合的な印象が重要 |
| 印刷媒体(チラシ・雑誌広告など) |
| ・大きな文字の強調表示と、小さな文字の打消し表示のバランスが不適切な場合 ・写真やイラストが実際の商品と著しく異なる場合 ・「編集タイアップ」と明記せずに広告と気づかれにくくしている場合 |
| ラジオCM |
| ・早口での注釈や条件提示は聞き取れないとみなされることがある ・過度に感情的な表現で印象操作をする場合 |
どの媒体においても共通するのは、「一般消費者が通常受け取るであろう印象」が基準となることです。専門家の目ではなく、一般の消費者が広告から受ける全体的な印象で判断されることを常に意識しましょう。
SNS広告やインフルエンサー投稿での注意点
近年特に注目されているのが、SNS広告やインフルエンサーマーケティングにおける表示の問題です。2023年10月には、いわゆる「ステルスマーケティング」(広告であることを隠した宣伝)が景品表示法で明確に禁止され、規制が強化されました。
SNS広告での主な注意点
- 広告であることを明記する必要がある(「PR」「広告」などの表示)
- 画像加工が過度な場合は実際の効果と異なるとみなされることがある
- シェア・いいね数などの数値を不正に操作することも違反となる
- コメント欄の否定的な意見だけを恣意的に削除することも問題視される
インフルエンサー投稿での注意点
- 企業から対価(商品提供含む)を受けている場合は広告である旨を明示する必要がある
- 自身の体験談のように見せかけた投稿(実際には使用していない場合)は虚偽表示となる
- 「個人の感想です」との断りがあっても、全体として誤認させる表現は違反となる
- 企業側の指示がなくても、インフルエンサー自身の表現が誇大であれば、依頼した企業も責任を問われる可能性がある
特に注意すべき点として、2024年10月から施行された改正景品表示法では、違反の疑いがある場合に消費者庁が事業者に対して資料の提出を求める権限が強化されました。
SNS上の表現においても、効果や性能に関する表現の裏付けとなる「合理的な根拠資料」を求められた場合、30日以内に提出できない場合、その表示は不当表示とみなさます。
このように、媒体を問わず「誠実な広告」が求められる時代となっています。特に新しい広告手法においては、法規制が追いついていない面もありますが、「消費者を誤認させない」という基本原則に立ち返ることが、リスク回避の鍵となるでしょう。
誇大広告・虚偽広告に該当するかの判断基準
広告表現が法律に違反するかどうかの判断は必ずしも簡単ではありません。ここでは、具体的な判断基準や関連法規、そして最も重要な「合理的根拠資料」について解説していきます。
景品表示法のガイドラインを元にした判断軸
景品表示法に基づく判断の基本となるのは、「一般消費者が通常受け取るであろう表示の意味」です。専門家や業界関係者ではなく、一般的な消費者の目線で広告が与える印象が基準となります。
消費者庁が公表している「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」などを参考に、主な判断軸を整理すると以下のようになります。
優良誤認表示の判断軸
- 商品・サービスの「品質」「規格」「効能」「効果」「性能」「安全性」などについて
- 実際のものよりも「著しく優良」であると示す表示
- または事実に反して「事業者間の競争関係における優位性」を示す表示
有利誤認表示の判断軸
- 商品・サービスの「価格」「取引条件」などについて
- 実際のものよりも「著しく有利」であると示す表示
- または事実に反して「競争事業者に対する取引上の優位性」を示す表示
判断の具体的なポイント
- 表示全体からの印象: 強調表示と打消し表示を総合的に見て判断
- 一般消費者の理解度: 専門知識がない消費者が通常理解する意味
- 著しさの程度: 一般消費者の選択に影響を及ぼす程度かどうか
- 客観性: 主観的評価か客観的事実の表示か
特に問題となりやすいのは「打消し表示」の効果です。メインの強調表示と比べて、注釈等の打消し表示が小さすぎる、離れた場所にある、理解しづらい表現である場合などは、打消し表示が十分に機能していないとみなされることがあります。
また、「業界No.1」「最高品質」などの最上級表現や比較表現を用いる場合は、市場調査データなど客観的な裏付けが必要です。調査の母集団、調査方法、時期などが適切でなければ、有効な根拠とは認められません。
薬機法・特商法・健康増進法など関連法規も確認
広告に関連する法規制は景品表示法だけではありません。商品やサービスの種類、販売方法によって、さまざまな法律が適用されます。特に以下の法律は広告担当者が押さえておくべき重要な関連法規です。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
- 医薬品的な効能効果を標ぼうする表現の規制
- 化粧品・医薬部外品の広告表現に関する制限
- 承認を受けていない効能効果の表示禁止
例えば、健康食品で「血圧を下げる」「糖尿病に効く」などの疾病の治療効果を示唆する表現を使用すると、薬機法違反となります。また、化粧品で「シミを消す」「しわを改善する」という表現も、承認された効能効果の範囲を超えるため問題となります。
特定商取引法(特定商取引に関する法律)
- 通信販売、訪問販売等の特定の取引形態に関する規制
- 広告に表示すべき事項(返品条件、送料等)の明示義務
- 誇大広告等の禁止
通販サイトやランディングページでは、特商法に基づく表記が適切に行われているか確認が必要です。販売業者名、所在地、電話番号、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期などの明示が義務付けられています。
健康増進法
- 健康の保持増進の効果に関する虚偽・誇大な表示の禁止
- 食品の広告表現に関する制限
「食べるだけで痩せる」「〇〇を飲むだけで健康になる」などの表現は、健康増進法の観点からも問題となる可能性があります。
その他の関連法規
- 金融商品取引法(金融商品の広告規制)
- 不正競争防止法(虚偽の表示、著名表示の冒用等)
- 著作権法・商標法(他社の知的財産権侵害)
- 個人情報保護法(顧客データの取扱い)
これらの法律は対象範囲や規制内容が異なるため、自社の商品・サービスに関連する法規をしっかりと把握し、法務部門や専門家と連携して対応することが重要です。特に、複数の法律に抵触するリスクがある健康食品、化粧品、金融商品などの広告は、特に慎重な検討が必要となります。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
引用:特定商取引法とは|特定商取引法ガイド
「合理的根拠資料」の有無が判断のカギ
景品表示法の運用において、最も重要な概念の一つが「合理的根拠資料」です。消費者庁は、優良誤認につながる可能性のある表示について、事業者に対してその裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(第7条第2項)。
要求を受けてから原則30日以内に資料を提出できない場合や、提出された資料が合理的な根拠とは認められない場合、その表示は不当表示とみなされます。
| 合理的根拠資料として認められるための要件 |
| 1. 客観性: 専門家、専門機関による客観的な実験・調査によるものであること 2. 実証方法の適切性: 学術的に確立された方法、または社会通念上妥当と認められる方法で実証されていること 3. 表示との関連性: 表示内容を実証するのに適切なものであること |
| 合理的根拠として認められない例 |
| ・社内関係者だけの体験談やアンケート ・サンプル数が極端に少ない調査 ・表示とは無関係または間接的な内容の研究 ・科学的に確立されていない理論や仮説 ・一般的な文献からの抜粋のみ |
例えば、「使用者の95%が満足」という表示をするには、統計学的に有意なサンプル数、無作為抽出などの適切な調査方法、具体的な質問内容が明らかで、調査結果が保存されている必要があります。
広告作成前に「この表現に対する合理的根拠資料はあるか?」という視点でチェックすることが、リスク回避の基本です。特に効果・性能に関する表現については、事前にマーケティング部門と法務部門が連携して根拠資料を整理しておくことをお勧めします。
実際に行政処分された広告の事例
理論的な知識だけでなく、実際に行政処分された具体的な事例を学ぶことで、より実践的な広告表現の判断力を養うことができます。ここでは、近年の主な違反事例を紹介し、そのポイントを解説します。
消費者庁の措置命令・課徴金対象となった事例の紹介
事例は実際の行政処分をモデルにした事例です。
- 事例1: ダイエットサプリメントの効果表示
-
ある会社が販売するダイエットサプリメントについて、「何もしなくても痩せる」「寝ている間に脂肪燃焼」「95%の人が効果実感」などと表示していた事例です。
消費者庁は、これらの表示について合理的な根拠資料の提出を求めましたが、提出された資料は試験方法やサンプル数に問題があり、効果を裏付けるものとは認められませんでした。結果として措置命令と約1億2,000万円の課徴金納付命令が出されました。
- 事例2: 家電製品の省エネ性能表示
-
大手家電メーカーが「業界トップクラスの省エネ性能」「電気代が従来製品の半分」などと表示していたエアコンについて、実際には他社製品より省エネ性能が劣っており、電気代の削減効果も限定的な条件下でのみ達成される数値だったことが問題となりました。表示に関する合理的な根拠がなく、優良誤認表示として措置命令の対象となった事例です。
- 事例3: 通信サービスの料金表示
-
「業界最安値」「月額980円から」と表示していた通信サービスについて、実際には別途必要となる初期費用や端末代金、オプション料金などを含めると、決して安価とは言えない料金体系だったことが問題となりました。打消し表示も小さく、一般消費者が気づきにくい形で表示されていたことから、有利誤認表示として措置命令と課徴金納付命令の対象となりました。
これらの事例に共通するのは、「一般消費者が通常受け取るであろう意味」と「実際の商品・サービスの内容」との間に大きな乖離があることです。また、表示の根拠となる実験・調査が不十分であったり、限定的な条件下でのみ当てはまる結果を一般化して表示したりしている点も特徴的です。
違反となったポイントと改善後の表現
上記の事例を含め、違反となった広告表現とその改善例を具体的に見ていきましょう。
- 事例1: 断定的な効果表現
-
「確実に痩せる」「必ず効果が出る」
→ 限定条件なしに断定的表現を使用改善例:
「運動や食事管理と併せて利用することで、ダイエットをサポートします」
→ 断定を避け、使用条件を明示 - 事例2: 不適切な比較表現
-
「従来品より30%効果的」(自社製品との比較だが、それが明示されていない)
→ 比較対象が不明確改善例:
「当社従来品(2022年モデル)と比較して、除菌テスト※では30%効果的」
「※第三者機関による試験結果に基づく(試験番号XXX)」
→ 比較対象を明確にし、試験根拠を示す - 違反例3: 誤解を招く価格表示
-
「月額980円~」(実際には別途初期費用5,000円、端末代金24,000円が必要)
→ 一部費用のみを強調し、総額を誤認させる改善例:
「月額料金980円~(別途、初期費用5,000円、端末代金24,000円等が必要です)」
→ 付帯費用を適切な大きさで併記
改善例に共通するのは、「透明性」と「具体性」です。抽象的な表現を避け、根拠となるデータの出所や試験条件、対象、時期などを明示することで、消費者に誤解を与えない表示となります。また、個人差や効果の限界についても適切に表示することが重要です。
EC・健康食品・美容ジャンルで特に多い傾向
消費者庁が公表する措置命令や課徴金納付命令の事例を分析すると、特定の業界・分野に違反事例が集中する傾向が見られます。特に問題が多いのは以下の3つのジャンルです。
- ①健康食品・サプリメント業界の特徴的な違反
-
健康食品業界では、以下のような違反が多く見られます。
- 医薬品的効能効果の標ぼう(「血糖値を下げる」「高血圧を改善」など)
- 痩身効果の過度な強調(「食べても太らない」「就寝中に脂肪燃焼」など)
- 体験談の不適切な利用(極端な成功例のみを紹介)
- 根拠不足の数値表示(「〇%の人が効果実感」「△kg減量」など)
この業界では、景品表示法だけでなく薬機法や健康増進法も関係するため、規制のグレーゾーンが多く、違反リスクが高くなっています。また、効果が実感しにくい商品特性から、過度の効果訴求に走りがちな面もあります。
- ②美容・化粧品業界の特徴的な違反
-
美容業界では、以下のような違反事例が見られます。
- 承認されていない効能効果の標ぼう(「シミを消す」「しわを改善する」など)
- ビフォーアフター写真の加工・演出
- 「全額返金保証」などの不実な返金制度
- 医学的根拠のない美容効果の主張(「幹細胞活性化」「遺伝子レベルの若返り」など)
化粧品は薬機法上で認められた効能効果の範囲が限定されており、それを超える表現は違反となります。また、視覚的イメージに頼る広告が多いため、画像の加工や演出による誤認も問題となっています。
- ③EC・通信販売業界の特徴的な違反
-
EC業界では、以下のような違反が多く見られます。
- 「送料無料」などの条件付きサービスの条件不明示
- 在庫状況の虚偽表示(「残りわずか」「完売間近」)
- セール価格の根拠不明確(実際には値引き前の価格で販売されていない)
- レビュー・口コミの不正操作(自作自演、否定的レビューの削除など)
- 特商法に基づく表記の不備
オンラインでの購入では消費者が商品を直接確認できないため、表示への依存度が高く、それだけに表示の適正さが重要となります。特に価格や在庫に関する虚偽表示は、消費者の購買意欲を不当に刺激するものとして厳しく取り締まられています。
- 近年の新たな傾向
-
特に2023年6月の景品表示法改正でステルスマーケティングが明確に規制対象となったことから、SNSやインフルエンサーを活用したマーケティングにおいては、広告であることの明示がより重要になっています。
これらの業界で広告を作成する際は、特に慎重な確認が必要です。過去の違反事例を参考に、類似の表現を避けるとともに、業界特有のリスク要因を理解し、予防策を講じることが重要です。
消費者庁のウェブサイトで公表されている措置命令事例集などを定期的にチェックし、最新の傾向を把握することをお勧めします。
誇大広告を防ぐために実務でできること
広告表現のリスク管理は、ビジネスを守るためだけでなく、消費者との信頼関係を構築するためにも不可欠です。行政処分を受けてからでは遅すぎるため、事前の予防策が重要となります。本章では、実務担当者がすぐに取り入れられる具体的な予防策を紹介します。
広告入稿前のチェックリスト
広告・販促物を制作する際は、以下のチェックリストを活用して法的リスクを低減しましょう。このリストは制作の各段階で使用できるよう設計されています。
1. 企画段階でのチェック項目
□ 訴求したい商品・サービスの特長や効果について、客観的な根拠資料はあるか
□ 比較表現や最上級表現(「最高」「No.1」など)を使用する場合、その裏付けとなるデータは十分か
□ 使用予定の数値データ(効果率、満足度など)の調査方法・対象・時期は明確か
□ 体験談やユーザーレビューを使用する場合、典型的な事例と言えるか、また極端な成功例のみを紹介していないか
2. 制作段階でのチェック項目
□ 断定的な表現(「必ず」「絶対」「確実」など)を避け、個人差がある旨を記載しているか
□ 写真やイラストが実際の商品・効果と著しく乖離していないか
□ 打消し表示(注釈・注意書き)は、本文と近接した場所に、十分な文字サイズで表示されているか
□ 専門用語や業界用語は、一般消費者にも理解できる表現になっているか
□ 広告・PR表示が必要な場合(SNS投稿、インフルエンサーマーケティングなど)、明確に表示されているか
3. 法的観点からのチェック項目
□ 景品表示法上の優良誤認・有利誤認に該当する可能性はないか
□ 業界特有の法規制(薬機法、健康増進法、特商法など)に抵触していないか
□ キャンペーンや懸賞を実施する場合、景品類の提供条件や上限額は適切か
□ 必要な表示事項(原産国、成分、効能・性能の限界など)は漏れなく記載されているか
□ 返品・解約条件がある場合、それらを明確に表示しているか
4. 最終確認項目
□ 全体を通して、一般消費者が受け取る印象として誤解を招く要素はないか
□ 社内の承認フローや確認手続きは適切に完了しているか
□ 過去の類似広告で問題となった点は修正されているか
□ 業界内で最近問題となった事例と類似した表現はないか
□ 問い合わせ窓口や連絡先は正確に記載されているか
このチェックリストは、商品やサービスの特性に応じてカスタマイズすることが効果的です。特に健康食品、美容、金融サービスなど、規制が厳しい業界では、業界特有のチェック項目を追加することをお勧めします。
「景表法・薬機法対応」の表現監修
法令に準拠した広告表現を実現するためには、専門家による監修が有効です。特に規制が複雑な業界では、外部の専門家の目を通すことで、社内では気づかなかったリスクを発見できる場合があります。
- 外部専門家の活用
-
専門家による監修を受ける際は、以下のポイントを押さえましょう。
- 弁護士による監修
景品表示法や各種業法に精通した弁護士に依頼することで、法的リスクを包括的に評価できます。特に新商品のローンチや大規模なキャンペーン実施前には、弁護士によるレビューを検討すべきです。 - 薬事法務コンサルタントの活用
健康食品や化粧品など、薬機法の規制対象となる商品では、薬事法務の専門家による確認が効果的です。薬機法違反は景品表示法違反と重複することも多いため、両方の視点からのチェックが望ましいでしょう。 - 業界団体のガイドライン活用
多くの業界団体は、広告表現に関するガイドラインや自主規制を設けています。これらを参考にしつつ、業界特有のルールに準拠しているか確認することも重要です。
- 弁護士による監修
- NGワードとOKワードの整理
-
監修の過程で得られた知見を体系化し、社内で共有することが重要です。
- NGワード集の作成
過去に問題となった表現や、専門家から修正を指摘された表現を業種・商品カテゴリー別に整理します。 - 代替表現(OKワード)の用意
NGワードに対応する、法的リスクの低い代替表現をストックしておくことで、クリエイティブ担当者の負担を減らせます。 - 事例集の構築
消費者庁の処分事例や、競合他社の修正事例なども収集し、具体的な参考材料として活用します。
例えば、健康食品の広告では以下のような整理が有効です。
- NGワード集の作成
| NGワード | 理由 | OKワード(代替表現) |
| 「血糖値を下げる」 | 医薬品的効能効果の標ぼう (薬機法違反) | 「健康的な血糖値の維持をサポート」 |
| 「1週間で5kg減量」 | 根拠不足の断定的表現(景表法違反) | 「健康的な体重管理をサポート」 |
| 「満足度98%」 | 調査方法が不明確 (景表法違反のおそれ) | 「使用者アンケートで高評価」 (調査方法・対象を明記) |
このように、問題のある表現と代替表現のペアを蓄積していくことで、クリエイティブの質を維持しながらもリスクを低減することが可能になります。
景品表示法違反による行政処分は、金銭的コストだけでなく、企業の信用失墜という大きな代償を伴います。適切な社内チェック体制を構築し、問題のある広告表現をあらかじめ防止することが、持続可能なビジネス運営の基盤となるのです
誇大広告に関するよくある質問
ここでは誇大広告や虚偽広告に関する質問を紹介いたします。
誇大広告と虚偽広告の違いは何ですか?
虚偽広告は「事実と異なる虚偽の内容」、誇大広告は「事実を大げさに見せて誤認させる内容」です。
例えば、「全員が1週間で5kg痩せた」と事実と異なる記述は虚偽広告、一方で「短期間で劇的に痩せる!」のような過剰な印象づけは誇大広告に該当する可能性があります。
GoogleやSNS広告でも誇大表現は問題になりますか?
はい、問題になります。
各媒体には独自の広告ポリシーがあり、特に健康・金融・美容関連は厳しく審査されます。媒体側での審査落ちだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
正しい広告表現で信頼性と成果を両立させよう
本記事では、誇大広告・虚偽広告の定義から法的判断基準、違反事例、そして実務的な対策まで詳しく解説してきました。
広告担当者にとって、インパクトのある表現で成果を上げることは重要ですが、法令を遵守し消費者に誤解を与えない誠実な姿勢もまた不可欠です。
誇大広告・虚偽広告を防ぐための重要なポイントを以下にまとめます。
- 表示内容に対する「合理的根拠資料」を事前に準備し保管すること
- 「最大」「最高」などの最上級表現は客観的なデータに基づいて使用すること
- 断定的な表現や効果の保証につながる言葉は慎重に選ぶこと
- 消費者が実際に得られる結果と期待値のギャップを最小限にすること
- 広告表現のチェック体制と責任所在を社内で明確にすること
厳格な法規制は広告表現の自由を制約し、マーケティング活動の障壁になるように思えるかもしれません。しかし、適切なコンプライアンス体制は単なるリスク回避策ではなく、消費者との信頼関係を構築するための基盤となります。
デジタル時代においては、不適切な広告はSNSを通じて瞬時に拡散し、企業の評判に致命的なダメージを与える可能性があります。一方で、誠実な広告活動は消費者からの信頼を獲得し、ブランド価値の向上につながります。
広告に携わるすべての関係者が景品表示法などの法規制への理解を深め、クリエイティブな表現と適正な情報提供を両立させることで、消費者と企業の双方にとって有益な広告活動を展開できるようになるのです。