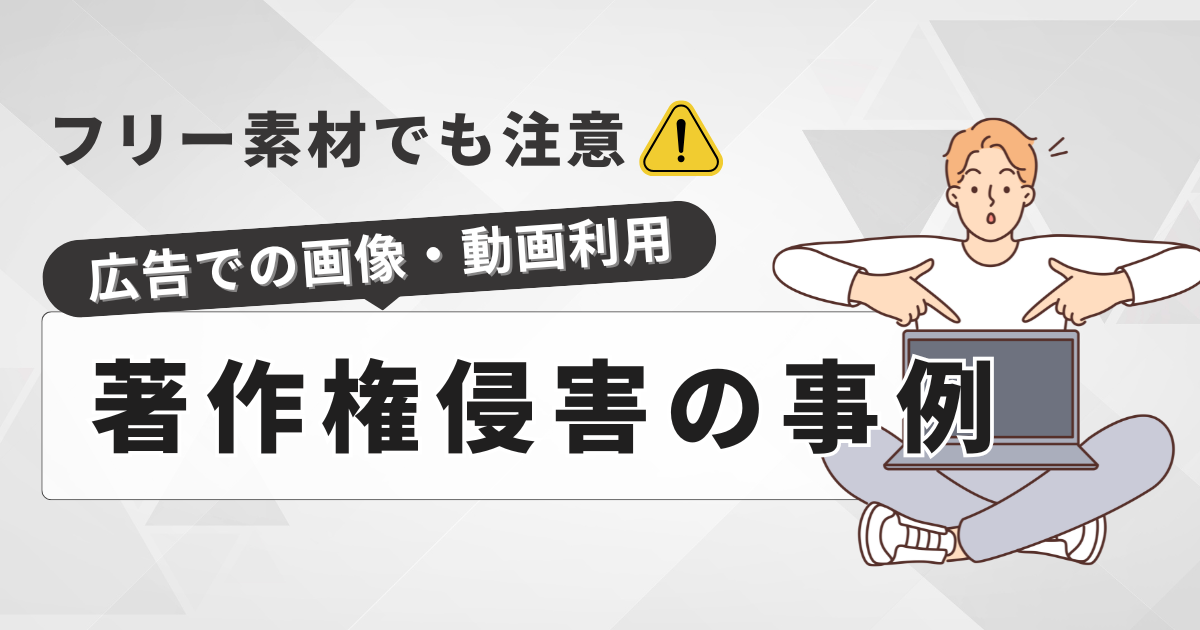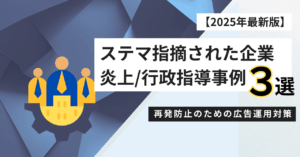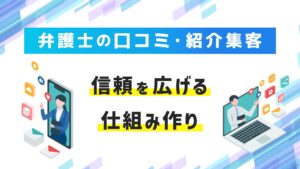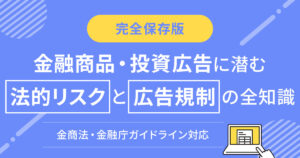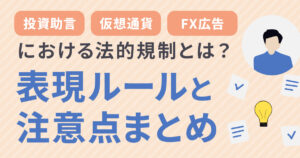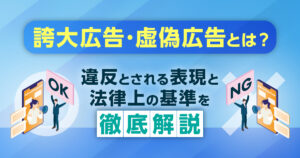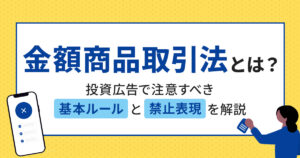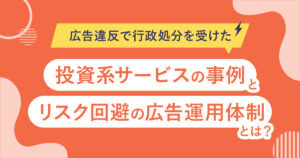「フリー素材なら自由に使ってOKでしょ?」──そんな認識のまま、画像や動画を広告に使ってしまい、思わぬトラブルに発展してしまうケースが増えています。
近年では、SNS広告やYouTube広告など動画活用の場面が広がる一方で、「商用利用可」と記載された素材でも、利用方法によっては著作権侵害や肖像権侵害と見なされる可能性があるのです。
特に広告や販促に使用する場合、素材の出典や利用範囲を誤解していたことで、削除要請や損害賠償といった深刻な問題に発展する例も少なくありません。
さらに、「著作権フリー」や「ロイヤリティフリー」といった言葉も、実は正確に理解しておかないと危険な“落とし穴”になります。
この記事では、フリー素材を広告で利用する際の注意点や実際のトラブル事例、そしてリスクを回避するためのチェックポイントを詳しく解説していきます。
マーケターやデザイナー、事業者の方々が安心して素材を活用できるよう、具体的なサイト例や対応策も交えて丁寧に紹介します。フリー素材=リスクゼロではないことを、まずは知ることから始めましょう。
なぜ「フリー素材」でも著作権トラブルが起きるのか
フリー素材と聞くと、「誰でも自由に、制限なく使える便利な素材」と思いがちですが、実際には多くの誤解や落とし穴が存在します。
特に商用利用や広告利用の場面では、些細なルール違反が大きな法的トラブルにつながることもあります。
この章では、そもそもなぜフリー素材がトラブルの原因になるのか、用語や仕組みを整理しながら、具体的な背景を解説していきます。
「フリー素材」と「著作権フリー」は同じではない
まず混同されがちな言葉として、「フリー素材」「著作権フリー」「ロイヤリティフリー」があります。
これらはいずれも「無料」「自由に使える」というイメージを持たれがちですが、実際には意味が大きく異なります。
- フリー素材
-
無料または制限付きで使用可能な素材。著作権が放棄されているわけではなく、配布元が提示する利用規約に従う必要があります。
- 著作権フリー
-
本来の意味では著作権が放棄されている状態を指しますが、実際には「一定の範囲で使える」「著作権者が使用を許諾している」だけのケースも多く、完全なフリーではありません。
- ロイヤリティフリー
-
一度ライセンス料を払えば追加料金なしで繰り返し使えるライセンス形態のこと。無料という意味ではなく、商用でも条件付き利用が一般的です。
このように、表現は似ていても実際の使用範囲には厳格なルールや制限が設けられていることが多いため、「フリー」という言葉だけを信じて無断利用すると、著作権侵害に問われる可能性があります。
利用規約を読まないことがトラブルの火種に
フリー素材サイトの多くは、素材ごとに細かな利用規約や制限事項を設けています。
しかし、利用者の多くが「無料」「商用利用OK」といった一文だけを見て利用を開始してしまい、実際の禁止事項を見落とすことが少なくありません。
たとえば、
- 「再配布は不可」
- 「加工しても著作権表示が必要」
- 「アダルト・宗教・政治関連での使用は禁止」
といった条件があるにもかかわらず、それを破ってしまうとトラブルの原因になります。
配布元の変更・素材の削除にも要注意
もうひとつの見落とされがちなリスクとして、素材の配布元が予告なく変更・閉鎖されることがあります。
利用していた素材が後日削除され、「本来は使用不可の素材だった」とされてしまうと、過去に使用した自社広告が違反扱いとなる場合もあります。
また、配布元が第三者からの著作権侵害の申し立てにより素材の提供を停止するケースもあり、ユーザー側が意図せず違法コンテンツを使用していたことになる可能性もあります。
広告利用で要注意!フリー素材の「商用利用」の落とし穴
フリー素材を使ううえで「商用利用可」と記載されているかどうかを確認する人は多いですが、その文言だけでは安全とは言い切れません。
実は「商用利用OK」の裏には、広告利用の文脈で見落としやすい制限が含まれている場合があり、正しい理解がなければトラブルに発展するリスクがあります。
広告制作の現場では、WebバナーやSNS広告、動画広告、チラシやポスターなど、素材の利用範囲が広く、影響力も大きいため、素材選定には慎重さが求められます。
この章では、「商用利用可」という表記に潜む落とし穴や、媒体ごとの注意点、そして実際のNG事例について詳しく解説します。
「商用利用可」は広告利用を全面的に保証するわけではない
「商用利用」とは、一般的に収益を目的とした活動に素材を使うことを指します。
企業やフリーランスが広告物に素材を使うことはこの定義に該当しますが、サイトごとに「商用」の範囲が微妙に異なる点に注意が必要です。
たとえば、
- 自社ホームページやパンフレットへの掲載はOKだが、SNS広告や外部プラットフォームでの配信は禁止
- 商品パッケージやグッズへの利用は禁止
- デザインテンプレートへの組み込み・再販は禁止
など、細かい禁止事項が設けられているケースがあります。
「商用利用可」という言葉に安心して飛びついてしまうと、素材の使い方によっては配布元の規約違反になることもあり得ます。
特に広告配信プラットフォームでの使用については、明確に「禁止」とされている素材もあるため要注意です。
媒体別に異なる「利用リスク」を知っておこう
媒体の掲載特性などによってリスクは様々です。ここでは広告媒体毎のリスクを整理しておきます。
- SNS広告(Instagram/Facebook/Xなど)
-
SNS広告での利用は素材の拡散範囲が広く、素材が他者の目に触れる機会も多いため、著作権者やモデル本人から指摘を受けるリスクが高い媒体です。
たとえ「フリー素材」でも、人物が写っている場合は肖像権やパブリシティ権の侵害に該当する可能性があるため、素材サイトのモデルリリース(使用許可)の有無は必ず確認すべきポイントです。
- YouTube広告・動画広告
-
動画広告で使用する素材には、動画そのものだけでなく、音声・音楽・効果音など複数の権利が絡む場合があります。
たとえば、BGM付きの動画素材を使って編集したものが、商用での再利用を禁じられていたという事例もあります。また、使用プラットフォーム(例:YouTubeのみOK/テレビCM不可)まで指定されていることもあります。
- リスティング広告やバナー広告
-
Google広告やYahoo!広告などのリスティング広告では、画像バナーなどにも素材が使われますが、掲載先媒体が多岐にわたるため、配布元が「利用範囲を制限している」ケースがあります。
特に、広告代理店が代行で制作・運用する場合、「第三者による利用」に該当し、制限違反となることがあります。
このように、媒体の出稿先による特性や動画・静止画などの特性によって、ケアするべきリスクは様々です。
広告クリエイティブを作成する際に押さえておきたいポイントです。
実際にあったNG事例とリスク
以下は、広告におけるフリー素材利用で実際に発生したトラブル例です。
事例1:人物素材のSNS広告使用で肖像権侵害の警告
無料写真素材サイトからダウンロードしたモデル写真をFacebook広告に使用したところ、モデル本人から「広告利用の許可をしていない」と申し立てを受け、掲載停止となった。
配布元は商用利用可としていたが、モデルリリース(肖像権使用許諾)の取得が不十分だったため、肖像権侵害と判断されたケースです。
出典:弁護士ドットコムニュース「フリー素材の人物写真を広告に使用、肖像権侵害でトラブルに」
事例2:フリー動画素材の音楽が著作権侵害に該当
動画制作時に使用したフリー動画素材に含まれるBGMが、商用利用不可のライセンスだったため、YouTube側から広告の停止と警告を受けた。
動画自体はフリーだったが、音楽の権利が別であり、商用利用が禁止されていたため、著作権侵害と判断された事例です。
出典:NHKニュース「YouTube広告で使用したフリー動画のBGMが著作権侵害に」
事例3:バナー素材に有名ブランドのロゴが映り込み、掲載NGに
街中の風景写真を使用したバナー広告で、遠くに写っていた看板のロゴが問題視され、広告媒体の審査に通らなかった。
広告媒体によっては、商標権の配慮が必須であり、意図せず映り込んだロゴでも掲載不可となる場合があります。
出典:CNET Japan「広告バナーに映り込んだロゴが原因で掲載拒否」
次章では、さらに具体的な著作権侵害トラブルとその実例について解説していきます。
よくある著作権侵害トラブルと実例
フリー素材を利用する際、著作権に関する誤解や不注意から、思わぬトラブルに発展するケースが少なくありません。
この章では、実際に発生した著作権侵害の事例を通じて、どのような点に注意すべきかを解説します。
フリー素材の誤用による損害賠償請求
ある企業が、自社ホームページに使用するバナー画像として、ネット上に「フリー素材」として掲載されていた写真をダウンロードして利用しました。最初は問題なかったのですが、ある日、著作権者から「無断使用だ」との連絡が入り、画像の削除と損害賠償を請求されました。
実際にはその画像は「フリー素材風」に見せかけたもので、著作権者の明示的な許諾がなかったことが判明。企業側は「フリー素材だと思った」と主張しましたが、著作権侵害の責任を免れることはできませんでした。
このケースでは20万円の損害賠償が発生しています。素材の出所があいまいなまま使用することは、企業の信頼と資産を大きく損なうリスクがあるのです。特に、著作権フリーと記載されている=完全に自由に使える、ではないことを改めて認識する必要があります。
無断使用による著作権侵害の判決
2015年、東京地方裁判所にて、ある中小企業が他社の所有する写真素材を無断で商品パンフレットに使用したとして、著作権侵害の判決が下されました。企業側は「フリー素材サイトで見つけた画像だ」と主張したものの、ライセンス内容を確認せずに使用したことが問題視され、結果的に損害賠償の支払いを命じられました。
この判例は、「インターネット上で見つけた素材=自由に使えるもの」と勘違いしてしまうことの危険性を浮き彫りにしています。また、広告や販促物など商業的利用の場合、裁判所はより厳しく判断する傾向があります。
さらに、企業が「素材の出典を正しく管理していなかった」ことも過失として認定されており、素材の出所管理や利用許諾の記録を残すことの重要性も示されました。小さなミスが大きな賠償リスクを生むことを、この事例は教えてくれます。
音楽の無断使用による著作権侵害
2011年、札幌市のある理容室が、BGMとして市販CDの音楽を店内で流していたことが問題視され、日本音楽著作権協会(JASRAC)から訴えを起こされました。理容室側は「一般に売られているCDだから問題ないと思った」と主張しましたが、裁判では著作権侵害が認定され、約24万円の損害賠償が命じられました。
この事例は、音楽や効果音といった音素材にも、厳格な著作権管理が存在することを教えてくれます。特に広告や店舗BGMなど不特定多数が聴く環境での使用は“公の場での演奏”と見なされ、管理団体への許諾が必要になるケースがほとんどです。
同様の問題は、フリー音楽素材の利用時にも発生します。たとえ「無料ダウンロード」と書かれていても、「個人利用のみ」や「クレジット表記が必要」など、制限があることが多いため、使用前に必ずライセンス規約を確認することが重要です。
出典: Back Media「著作権侵害の事例10選|身近な事例や罰則・成立要件・侵害を解説」
動画広告・YouTubeでの「フリー動画」使用時の注意点
動画コンテンツがマーケティングにおいて重要性を増す中で、コストを抑えるために「フリー動画素材」や「無料BGM」「フリー効果音」を活用するケースが増えています。
しかし、フリーといえども、動画に関する著作権は非常に複雑で、音・映像・人物・背景の全てに別々の権利が関わっていることを理解しておく必要があります。
特に広告やYouTubeなど不特定多数に配信される媒体では、「商用利用可」とされる素材であっても、使用条件を満たしていないと著作権侵害や配信停止の対象となる場合があります。
フリー動画素材の配布元ごとの規約の違いに注意
フリー動画素材の多くは、Pexels、Pixabay、Videvo、Mixkitなどのプラットフォームから提供されていますが、それぞれのサイトごとにライセンスの考え方が異なります。
たとえば
- Pixabayでは商用利用可の動画が多いものの、一部には「再配布不可」や「販売・広告での使用制限」がある場合があります。
- Videvoは動画ごとに「Videvo Attribution License」「Royalty-Free License」「Creative Commons License」など複数のライセンスが混在しており、誤って使用するとトラブルに繋がる恐れがあります。
広告として配信する場合、「商用利用可」かつ「再編集・再配信可能」であることを明記している素材を選ぶ必要があります。
一つの動画内でも映像と音楽が別々のライセンスとなっていることがあるため、特にBGMの権利は見落とされがちなので注意が必要です。
音楽・効果音の著作権にも細心の注意を
動画内に含まれる音素材、特にBGMや効果音は、多くの場合で著作権管理団体(JASRACなど)または個人クリエイターの許諾が必要です。
たとえば、「YouTubeで使ってもOK」と明記されていても、「商用利用不可」「企業アカウントでの利用禁止」といった制限がついている場合があります。
特にYouTube広告では、自動的にコンテンツIDで著作権の照合が行われるため、問題のある音楽が含まれていると即座に収益化停止・配信停止の処置が取られる可能性があります。
人物・建物・ロゴの映り込みにも注意が必要
動画素材の中に「人の顔」「商業施設」「ロゴ・看板」などが映り込んでいる場合、肖像権やパブリシティ権、商標権が問題になる可能性があります。
たとえば、無償配布されている街頭映像の中に有名ブランドのロゴが入っていた場合、広告で使用すると訴訟や掲載拒否につながるケースもあります。
使用前には「モデルリリース(肖像権同意)」「プロパティリリース(施設利用の同意)」の有無を確認し、不安な場合は人物が映っていない素材や、背景が抽象的なものを選ぶのが安全です。
フリー動画素材を安全に使うには、動画本体・音楽・人物・背景それぞれの権利を個別に確認する習慣が必要です。
危険な「著作権フリー」の罠と見分け方
「著作権フリー」「ロイヤリティフリー」──一見すると自由に使える安心素材のように感じられるこれらの言葉。
しかし実は、多くの広告トラブルがこの言葉の“誤解”から始まっています。
特にマーケティングや広告の現場では、使用範囲の誤認や素材サイトの規約違反が原因で、掲載停止や賠償問題に発展することもあるため、正しい理解が必要です。
「著作権フリー」は著作権が消滅したわけではない
「著作権フリー」という表現は本来、著作権が完全に放棄されたか、すでに著作権保護期間が終了している素材を指します。
しかし、インターネット上では「無料で使える素材」と同義に使われていることが多く、実際には制作者が一部の利用を許可しているだけというケースが大半です。
たとえば、あるフリー素材サイトで「著作権フリー」と記載された画像を商用広告で使用したところ、制作者から「商業利用は対象外」とクレームを受けたというトラブルがあります。
これは、素材配布ページの文言と利用規約が一致していなかったことが原因で、使用者の過失とされました。
よくある“罠”パターンとそのリスク
次のようなケースは、著作権トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
- 誤認しやすい表示
-
「自由に使えます」「ご自由にどうぞ」など、曖昧な記載だけで規約が見つからない素材
- ライセンス表記の欠落
-
画像や動画は自由に使えても、BGMや効果音が別ライセンスで管理されている場合
- 海外サイトからの素材取得
-
英語圏の素材サイトには、国ごとに異なる著作権概念があるため、日本での広告利用に不向きなケースも
- 転載素材の再配布サイト
-
元の権利者が許可していないにも関わらず、他者が「フリー素材」として掲載している場合(いわゆる“無断転載サイト”)
これらの罠に共通しているのは、出所の不透明さと使用条件の曖昧さです。特に、検索エンジンの画像検索から直接ダウンロードした素材などは、誰が作ったのか・誰が権利を持っているのかが不明な場合が多く、広告への利用は極めて危険です。
正しい素材を見分ける3つのポイント
- 配布元の明示的な利用規約があること
-
商用利用、編集の可否、再配布の可否などが明記されているかを必ずチェック。
- ライセンス種別が具体的に記載されていること
-
「CC0(著作権放棄)」「CC-BY(クレジット必須)」など、Creative Commonsの形式であれば信頼性が高い。
- 素材の出典や作者情報が確認できること
-
誰がアップロードし、どのような意図で配布しているかが明らかな素材を選びましょう。
広告や広報活動で安心して素材を使用するには、「無料だから」「著作権フリーだから」と鵜呑みにせず、自らの目でライセンスと利用規約を確認することが何より大切です。
著作権トラブルを防ぐ5つのチェックポイント
「知らなかった」「フリー素材だと思った」では通用しないのが著作権の世界です。
広告やマーケティングの現場では、素材の選定・利用の段階で細心の注意を払うことが求められます。
ここでは、著作権トラブルを未然に防ぐために、プロが実践している5つのチェックポイントを紹介します。
素材を使う前に、必ず以下の観点から確認しましょう。
- ライセンスの種類を必ず確認する
- 使用目的と一致しているか確認する(広告・販売物・Webなど)
- 肖像権・パブリシティ権に注意する(人物・著名人・商品等)
- 加工・編集の可否を確認する
- クレジット表記の有無・方法を確認する
順番に解説していきます。
ライセンスの種類を必ず確認する
素材を使用する前に、配布元のライセンス情報をしっかりと確認しましょう。たとえば、「CC0(パブリックドメイン)」はクレジット表記なしで自由に使えますが、「CC-BY」は必ず出典や作者名の表記が必要です。
また、「ロイヤリティフリー」=「著作権フリー」ではなく、使用回数や媒体に制限があることもあります。
さらに、サイトによっては動画・音楽・画像それぞれに異なるライセンスが設定されているため、「何を」「どの媒体で」「どこまで」使えるかを素材ごとに確認することが重要です。
使用目的と一致しているか確認する(広告・販売物・Webなど)
商用利用が可能かどうかだけでなく、具体的な用途(例:SNS広告・動画広告・ECサイト・印刷物)に合致しているかをチェックする必要があります。
中には「商用利用可」と書かれていても、「YouTubeやSNS広告での使用は禁止」や「テンプレートとしての再販はNG」といった例外がある場合もあります。
広告運用においては特に、使用媒体が広範にわたるため、利用規約の解釈に迷ったら必ず事前に確認・問い合わせを行いましょう。
肖像権・パブリシティ権に注意する(人物・著名人・商品等)
人物が写っている素材の場合、その人物の肖像権やパブリシティ権が関わってきます。モデルリリース(使用同意書)が取得されている素材でなければ、商用利用は避けるべきです。
また、芸能人や著名人が写り込んだ画像を無断で使うと、損害賠償請求の対象になることもあります。
背景にブランド品やロゴが映っている場合も、商標権の侵害に発展するリスクがあるため注意が必要です。
加工・編集の可否を確認する
広告用に使用する場合、画像や動画にテキストを載せたり、トリミングやカラー調整などの加工を施すことも多いですが、一部のライセンスでは「加工不可」「二次利用不可」とされていることがあります。
加工自体は許可されていても、加工後の再配布や販売が禁止されているケースもあるため、素材使用前にはその範囲まで確認しましょう。
クレジット表記の有無・方法を確認する
「商用利用可」であっても、「クレジット表記を条件とする」素材は多く存在します。
特にSNS広告やバナー広告ではクレジット表記が難しいため、クレジット不要の素材を選ぶか、使用を避ける判断が必要になることもあります。
トラブルになってしまった場合の対処法
万全の確認を行っていても、思わぬ見落としや誤解から著作権や肖像権の侵害トラブルが発生することがあります。
特に広告や販促活動での素材利用は注目度が高く、第三者からの指摘が入りやすい領域です。
この章では、万が一トラブルになってしまった場合の具体的な対処フローと、法的リスクを回避するための対応策を解説します。
使用停止・削除要請には迅速に対応する
まず、著作権者や権利保持者から削除要請やクレームの連絡を受けた場合は、速やかに該当コンテンツの使用を停止または削除しましょう。たとえ自身に非がないと感じたとしても、対応が遅れると損害拡大や訴訟リスクにつながります。
また、素材サイト経由ではなく、SNSのDMや問い合わせフォームなどを通じて連絡が来ることもあります。
連絡元の信憑性を確認しつつも、まずは一時的な掲載停止など、誠実な対応を示すことが信頼回復の第一歩になります。
謝罪文・連絡文を丁寧に作成する
削除対応後は、著作権者など関係者に対して正式な謝罪文や説明文を送ることが望まれます。
この際、「素材がフリーと誤認していたこと」「非営利目的であったこと」「すぐに削除対応を行ったこと」などを簡潔に伝え、誠意をもって謝罪することが重要です。
著作権や肖像権に関わる通知は保存・記録する
削除要請や著作権主張の通知メール、チャットの履歴などはすべて時系列順に保管しておくことが大切です。
特に、後に法的な対応や調停が必要になった際に、やり取りの記録が証拠として役立ちます。
また、社内で共有するための報告書として「発生日」「経緯」「対応内容」「再発防止策」などをまとめておくと、組織としての対策にもつながります。
法的リスクがある場合は専門家へ相談する
削除や謝罪だけでは解決しない場合、損害賠償請求や訴訟予告など、法的措置の話が出た場合には弁護士への相談が必須です。
特に商用利用によって経済的な損失が発生したと主張されるケースでは、プロの判断が求められます。
「どこまでが侵害にあたるのか」「本当に賠償の対象となるのか」など、専門的な知識が必要になるため、知的財産権に詳しい弁護士やIT法務の専門家への早期相談が推奨されます。
今後の再発防止体制を整える
トラブルが収束した後も、組織として再発防止策を明文化し、業務フローに組み込むことが非常に重要です。
例えば
- 使用前に第三者チェックを入れる
- 使用素材とライセンス情報を一覧で記録・管理する
- 社内マニュアルや教育資料を整備する
素材の利用に関する意識を全社で共有することで、同じようなリスクの再発を防ぐことができます。
万が一トラブルが発生してしまった場合でも、迅速かつ誠実な対応を取ることで、被害の拡大を防ぎ、信頼回復につなげることが可能です。
まとめ
ここまで、フリー素材に関する著作権の基礎知識から、広告や動画での具体的なトラブル事例、安心して使える素材サイト、トラブル時の対応方法までを一通り解説してきました。
「フリー素材=完全に自由に使える」という認識は、もはや通用しません。
とくに広告や販促といった商用目的での使用は、素材のライセンスや権利関係を一つひとつ丁寧に確認することが求められます。
たとえ無料で提供されているものであっても、その背景には著作権・肖像権・商標権といった複雑な権利が絡んでいるのです。
フリー素材は、正しく使えば非常に便利でコストパフォーマンスにも優れたクリエイティブリソースです。しかし、ルールを知らずに使用すると、思わぬリスクや損害を招いてしまう可能性があります。
特に広告やプロモーションのように“多くの人の目に触れる”シーンでは、素材選定の段階から著作権リスクを意識することが、信頼性のあるマーケティングの第一歩です。
本記事が、フリー素材の正しい使い方とリスク回避の参考になれば幸いです。
今後も法令やライセンス条件は変化していくため、常に最新情報を確認しながら、安全で効果的な素材活用を実践していきましょう。